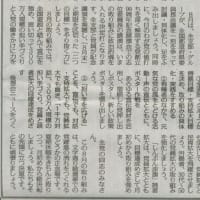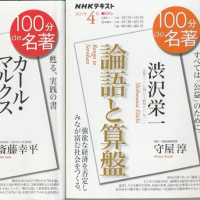第183回国会 予算委員会 第6号 平成二十五年二月二十六日(火曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/183/0014/18302260014006c.html
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/183/0014/18302260014006c.html
藤末健三君 憲法九条、お手元に配付資料一がございますが、自民党の憲法改正案、国防軍をつくるということを書いてございますが、その意義を総理に伺いたいと思います。お願いします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 自由民主党の憲法改正草案、これは昨年の四月二十八日に決定をしたものでありますが、その中において、自衛隊を国防軍として位置付けることにしております。自衛隊は、国内では軍隊とは呼ばれていない、軍隊ではないという位置付けでありますが、国際法上は軍隊として扱われているわけであります。私たちは、このような矛盾を実態に合わせて解消することが必要であると、こう考えております。もとより、シビリアンコントロールの鉄則を変えるつもりはもちろんございませんし、憲法の平和主義や戦争の放棄を変えるつもりも全くないわけであります。他方、憲法の改正については党派ごとに異なる意見がございますので、まずは、多くの党派が主張している憲法九十六条の改正から取り組んでいきたいと、こう考えております。
藤末健三君 二つの点を御指摘申し上げたいと思います。一つは、国際基準と合わないから直すということなんですが、我々は、やはり自衛隊、憲法に基づく自衛隊というものを説明する方が先じゃないでしょうか。まず一つございます。あともう一つございますのは、ここで国防軍という軍に名前を変えるということは余分な摩擦を起こすだけであって、何のプラスもないと考えますが、その点はいかがでしょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、この説明をするという今委員のお話でございますが、国内において自衛隊であって軍でないと、こう言っているわけでありますが、一方、海外における自衛隊の存在は軍隊として取り扱われる必要があるわけであります。また、場合によって、もし他国から侵略を受けた際に交戦したときに軍隊でなければ軍隊として取り扱われない、つまり捕虜として扱われるかどうかという、そうした問題も出てくるわけでございます。何よりも、自衛隊の諸君のこれは誇りの問題でもあると私は考えるわけであります。むしろ、国際社会においてはそれが常識でありますから、そこに合わせることによって逆にこれは矛盾が出てくるものではないと、このように思うわけであります。
藤末健三君 総理に申し上げますが、私は一義的に、私は防衛力は必要だと思っています。ただ、一義的に、国防軍になりますよということをもっていろんなものが解決するということは私はないと思います。具体的に我が国に必要な防衛はどうあるべきか、何が問題か、何が足りないかということを議論した上で、最後の答えとして国防軍というのが常識だと思いますけれども、いかがですか、その点について。
内閣総理大臣(安倍晋三君) もちろん、今、藤末議員が言われたように、安全保障については冷静な議論が必要でしょうし、何が必要かということも大切なんだろうと、このように思います。我が党での議論においては、これは実際に、今自衛隊はセルフディフェンスフォースと、こう言われているわけでありますが、実際に自衛隊の方々は海外で活動していく上において、これセルフディフェンス、つまり自分自身を守るんではないかというやゆがあるのも事実なんですね。自衛隊の諸君の誇りは、自分の命を懸けて国を守る、あるいは平和を維持する、それが彼らの誇りであります。まさに、国民のために命を懸ける彼らに必要なものは、何といっても私は誇りではないのかと思うわけでありまして、憲法を改正する際には、これは他国と同じように国防軍という記述が正しいのではないかと、私はこのように思うところでございます。
藤末健三君 その自衛隊の方々の意思を高めることだけをもって国防軍にするような話ではないと思います。私は、もし海外に行かれた自衛隊の方々が、セルフディフェンスフォースという名前に問題があるならば、法律で、例えばピースキーピングユニットとかと言うことできると思います。いかがですか、その点。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 世界中どこの自国を守る言わば実力組織も、基本的には大体どこも国防軍という、そういう名称を持っているわけでありまして、だからといってそれが侵略的なことではないわけでありまして、むしろこれが世界のグローバルスタンダードであろうと、このように思うわけでありまして、そこでやはり、彼らは、これは自衛隊の諸君、東日本大震災におきましても本当に大変な活躍をしてくれました。彼らが、まさに危険を顧みず、事に当たって危険を顧みず任務を遂行すると、もって国民の負託にこたえてまいりますという宣誓をする、言わば自分は命を懸けますよということを宣誓する唯一の公務員と言ってもいいわけでありまして、その士気を維持する、これはまさに日本の国民の命を守ることに最も大切なことではないのかなと、このように思うわけでございます。
藤末健三君 私は、士気を維持するために国防軍に変えるというのは余りにも短絡な議論だと思います、総理、正直申し上げて。まず必要なことは、例えば防衛予算がどれだけあり、そして防衛の装備はどれだけあり、そしてどれだけの自衛隊の方々の数が必要か、そういう議論をまずすべきではないですか、いかがですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) もちろん我々はそういう議論もしております。と同時に、生身の人間がそこでは働いている、まさに国を守っているわけであります。家族もいる、また愛する人もいるわけであります。その彼らのことも私は十分に考えるべきではないのかなと、こう思うわけでありまして、一方、では、国防軍にするということにどこに問題があるのかということであります。そうすると、ほかの国もみんな国防軍でありますから、あなたのところは問題があるということなのかといえば、それはそんなことはないわけでありまして、殊更日本だけが国防軍にしていけないという理由は見当たらないのではないかと、このように思います。
藤末健三君 二つのことを申し上げたいと思います。一つは、やはり国際標準という話にしてしまえば、全部憲法も国際標準に変えるという話になりかねませんか。全部、じゃ、国際標準に合わせた憲法に変えてしまえばいいという話になりかねないと思いますし、そしてまた、国防軍というそんな非常に重要な議論を士気を高めますというだけの話で進めてよろしいんですか。そこを二点お聞かせください。
内閣総理大臣(安倍晋三君) もちろんこれは簡単な議論ではなくて、今の状況でただ国防軍に名前を変えるのではなくて、これ憲法改正が必要であります。逐条ごとに改正をしなければいけませんから、これは国民投票も必要でしょうし、そして九十六条を変えていないのであれば三分の二の発議が必要であります、衆参それぞれの。ですから、これは相当の議論を経なければ、それは成し遂げない。つまり、相当の議論をしてもそれは成し遂げるべきだと我々は考えているわけでございまして、そういう議論を、これはまずは九十六条を変えていくべきだというのが我々の考えでありますが、それと国際標準との関係ということでおっしゃっておられましたが、もちろんこれは全て国際標準に合わせる必要は全くないわけであります。また、憲法の九条についても、第一項は我々も残していくわけであります。同時に、言わばこの実力組織においては、なぜ、では海外と標準を合わせなければいけないかといえば、PKO活動等においては一緒に活動する部隊があって、我が方だけが別の規定で動いているということになると、果たしてそれはうまくいくのかどうかという議論は根強く残っているわけでありますし、そして我が国を防衛する中においては、これは、我が国の事情だけで完結するのではなくて、相手があることであります。よって、これは国際的な標準ということを考えるべきであろうと。特に軍隊、海外でいえば軍隊、自衛隊が活動する上において、国際法的な観点をこれは当然考慮するのは当たり前のことではないかと、このように思うわけであります。
藤末健三君 安倍総理に二つのことを指摘させていただきたいんですが、一つは、自民党の憲法改正案、九条の一項は書き換えていますので、それは御理解いただきたいということが一つ。そして、もう一つございますのは、基本的な考え方を変えないのであれば、今まで、後で議論しますけれども、様々な議論があって、政府解釈などがあります。六十年間の議論が積み重なっている。そういう議論をないがしろにすることにもつながりかねないんじゃないかということを考えることを申し上げます。私はちょっと、ここで御質問でございますけれど、総理は、国防軍にします、じゃ、防衛費をどれぐらい増やさなきゃいけないとお考えでしょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 防衛力については、これは安全保障環境の状況も考慮しながら、また当然財政状況というのも考慮しながら総合的に判断をしていくべきだろうと、このように思います。
藤末健三君 GDPの一%枠というのがございましたけれど、その点についてはいかがでしょうか。総理にお聞きします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 防衛費は何のために使われるかといえば、国民の生命、財産、領土、領海、領空を断固として守り抜いていくためであります。自衛隊がその持てる現在の能力を最大限に発揮をすることは当然でありますが、その上において、政府としては、我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増していることなどを踏まえて、防衛体制の強化のために平成二十五年度予算案では防衛費の増額を図っているわけであります。今、そこで、委員の御指摘のあったGDP一%枠でありますが、それは既に昭和六十一年に廃止をされて、御承知のとおりでありますが、ただ、防衛費の在り方については、先ほどお話をさせていただきましたように、安全保障環境等の対外的な要因を踏まえる必要があります。防衛費をGDPと機械的に結び付けることは私は適切ではないと考えております。もちろん、厳しい財政事情を踏まえて、効果的、効率的な防衛力整備を行っていくことは不可欠でありますが、そうしたことを総合的に勘案をしていくべきであろうと思います。
藤末健三君 安倍総理のこの二年、三年の、二年ですね、のいろいろな憲法改正、国防軍に関する資料を集めさせていただいたんですが、やはり多くのところで防衛費を増額しなけりゃいけないということをずっとおっしゃっているんですよ。その点はもう変わられたんですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 防衛費は増額しなければならないと考えておりましたから、だからこそ来年度予算については、本予算において十一年ぶりに防衛費を増額することにしたところであります。
藤末健三君 防衛大臣に伺いますが、陸海空の予算の配分のこの三十年間の推移をお教えください。お願いします。
国務大臣(小野寺五典君) 陸海空の各自衛隊の歳出予算の割合ですが、例えば昭和五十九年の時点では、陸が四二・四、海上自衛隊が二七・八、航空自衛隊が二九・八ということですが、平成二十五年は、陸上自衛隊が四四・一、海上自衛隊が二九・二、航空自衛隊が二六・七ということになっています。
藤末健三君 今の説明では非常に分かりにくいんですが、この三十年間ほとんど変わっていません。一、二%です、変動は。ずっと陸海空の防衛予算の配分の割合は変わっていないという状況でございますが、安倍総理はこのような状況をどのようにお考えでしょうか。お願いします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) この十年間、財政状況が非常に厳しい中で、日本の場合は大体各省庁同じように横並びで減らしていくわけでありまして、そういう中において、事実上少しずつ防衛費を減らしてきたという状況があります。ところが、このアジア太平洋地域の安全保障環境は厳しさを増しているわけでありまして、そういう中において、対外的な要因をしっかりとこれは勘案するべきだというのが私の考え方でありまして、その考え方にのっとって来年度予算について我々は予算編成を行ったということであります。
藤末健三君 私が申し上げたいのは、冷戦が終了し、そして北朝鮮の問題が起き、先ほど御指摘いただきましたようにアジア太平洋地域の緊張が高まっているという中、陸海空の予算配分は全然変わらないという状況でございます。それについてどう考えているかということをお聞きしております。
国務大臣(小野寺五典君) 予算につきましては、実はその比率、各年度で若干違います。例えば、航空自衛隊等で新しい装備を買う、あるいは海上自衛隊でイージス艦を建造する、こういう場合には多少比率は違っています。ただ、全体としていえば、実はこの防衛予算の八割が人件費等ということになりますので、残りの二割で実は各種装備の更新等を行ってきている、新しい装備がなかなか充実できない、これがここ二十年ずっと我が国が抱えてきた問題だと思っております。
藤末健三君 総理に申し上げたいのは、そのような問題をまず解決することが先であり、国防軍という名前を変えて士気を上げるということについて先に議論すべきでは私はないと思います。続きまして、九条に関しましてその解釈について議論させていただきたいと思います。資料の二と三というのがございますが、この集団的自衛権の行使を含む九条の解釈について様々な政府の解釈がございますが、その解釈につきまして、法制局長官、御説明をお願いいたします。
政府特別補佐人(山本庸幸君) お答えいたします。憲法九条につきましては、従来から自衛隊に関する様々な法律、条約、そして予算が国会で審議される過程におきまして、いろいろな議論が積み重なってきております。その基本となるものとしては、憲法九条の下においては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、これを排除するための必要最小限度の武力の行使を除いて、武力の行使は一般に禁じられているというものでございます。そこで、御指摘のまず海外派兵でございますが、これは、武力の行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することでありますし、集団的自衛権の行使、これは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、我が国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利を行使することにつきましては、そもそも我が国に対する武力攻撃が発生していない場合でございますので、憲法九条の下においては従来から許されないというふうに解釈されてきたわけであります。最後に、御指摘の攻撃的兵器の保有の禁止につきましては、憲法九条の下においても、個別的自衛権の行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは禁止されておりませんけれども、しかしながら、その性能上、相手国の領土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるそういう兵器の使用は、これは憲法上許されないというふうに解釈されてきたというわけでございます。
藤末健三君 このように、憲法に関する議論はもう長年の積み重ねがあるということは御理解いただけたと思いますが、このように、先人たちの長年の解釈の積み重ねがあった憲法の解釈を変えることについて、法制局長官はいかがお考えでしょうか。お願いします。
政府特別補佐人(山本庸幸君) いろんな観点で憲法について議論されることは結構でございますし、現に、現在、最近の安全保障環境を考慮して安保法制懇というところで議論されているところでございますが、私どもとしてはその結論を待っていろいろと検討させていただきたいと思っております。
藤末健三君 また総理にお聞きしたいんですけど、やはり私が思いますのは、いろんなところが変わりませんということで部分的に変わっているのが自民党憲法の改正案でございまして、変わらぬところは変える必要はないと思いますし、また、変えるところも、長年のいろんな議論があったわけでございますので、そういう議論を踏まえて検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 長年の議論を重視したら何にも変わらないんですね、世の中。つまり、変わるべきものはしっかりと変えていきたいし、言わば、先ほど申し上げましたように、我が国のこの平和主義については、我々それは不動のものであると、このように考えているわけでありますが、同時に、政府また国家は国民の命を守る、生命、財産を守るという大きな義務を負っているわけでありまして、安全保障環境が大きく変わっている中において、それをどう果たしていくかということについて不断の努力、検討していくのは当然の義務ではないかと、このように思っております。 (略)
藤末健三君 安倍総理は、徴兵制度は必要だとお考えでしょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 必要であるとは考えておりません。
藤末健三君 これ、総理としてじゃなくて自民党総裁としてお聞きすることになりますけれど、自民党憲法改正案では十三条、十八条、ここを改正することになっていますが、その意味は何でございましょうか。十三条と十八条です。資料の三ですね。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 自民党が取りまとめた日本国憲法改正草案において十三条及び十八条について改正案を示しておりますが、それは、その条文をより分かりやすくするため文言を改めたものであります。
藤末健三君 より分かりやすくするために文言を改めたとございますが、例えば十三条では「公益及び公の秩序に反しない限り、」とわざわざ書き換えておられますけど、この公の秩序というのはどういう意味ですか。これ、中には、これが徴兵制度につながるんではないかと、わざわざ書き換えているということを言う人もいますので、お願いします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、純粋に、公の秩序に反しないというのは当然のことであろうと、それを書き入れたわけでありまして、それと、先ほど申し上げましたように、徴兵というのは今の世界の趨勢において多くの国はそういう制度を取っておりません。むしろ、現代においてはそれは必ずしもうまく機能するとは限らないわけでありますし、私は全くそれは必要がないと、このように考えております。
藤末健三君 また、自民党の憲法の案の前文の第三パラグラフの方に「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、」とございます。そして、十三条の改正ということで、非常にその徴兵制度は心配じゃないかという方がおられますけれども、その点いかがでしょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) それは杞憂だろうと思います。
藤末健三君 私が申し上げたいのは、例えば先ほどの十三条の改正、公共の福祉という話をわざわざ書き換えておられるじゃないですか。その十三条についても、長年の議論があるわけじゃないですか、総理。そして、解釈されているものをわざわざ書き換えている。それは九条についても同じだと思います。ですから、その長年の議論があるものをきちんとわきまえた上で次のことを考えなきゃいけないと思いますが、いかがですか、総理。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 長年の議論等々というのは私も意味がよく分からないんですが、我々は、憲法についてはもう一度更にして、まあ言わば清らかな水のように、最初から、何が大切か、あらかじめ頭にインプットされたものではなくて、何が我が国のために大切か、日本の伝統と文化の中に根差したものについても思いをはせながら自由民主党の草案を考えたわけであります。
藤末健三君 それは聞き方によっては、今までの議論は全然考えずに、もう更から全部考えようというふうに聞こえますが、それでよろしいんですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 自由民主党は相当の議論を行っているんですね。憲法改正の議論を全く行っていない党もあるかもしれませんが、我が党は違います。相当の議論、真摯な議論を行いました。議論をするというのは、党においては時には相当の意見の対立もありますが、そういう中において取りまとめられたものが今度の自由民主党の憲法改正草案であります。その前に第一回目の改正草案もありました。そして、そういう長年の議論を経て、自由民主党は結党の際に憲法改正ということを掲げておりました。それから延々と五十年以上ずっと議論をしているわけでありますから、突然出てきたものでは全くないということは御理解をいただきたいと思います。 (略)
藤末健三君 総理にお聞きします。総理は九十六条の改正によく言及されておりますが、どのような改正の内容であり、そしてその理由、必要性は何かということを御説明いただけますでしょうか。お願いします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 今の法制局長官の説明にあったように、各国三分の二というのがあるんですが、一方、三分の二プラス国民投票ではないんですね。フランスもそれに代替の方法があるわけでありまして、日本のみが三分の二プラス国民投票なんですね。であるからこそ硬性憲法と言われています。我が党の案においては二分の一、そして更に国民の過半数、これが我が党の案でございます。なぜかといえば、国民の六割が、あるいは七割が改正したいと考えていたとしても、三分の一をちょっと超える国会議員が反対をすれば議論すらできないのはおかしいだろうというのが我々自由民主党の考え方であります。 (略)
藤末健三君 総理、いかがですか。アメリカ、ドイツ、フランス、同じような国会議員の要件が入っています、賛成の要件が。それでも、それぞれ六回、二十七回、五十八回と憲法を改正しているわけでございますけれども、その点についてはいかがですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) それは、各政党が現実的なアプローチをしていたんだろうと思います。日本のように不磨の大典として指一本触れてはならないと思うような政党がなかったからであろうと思いますね。
藤末健三君 あえて申し上げますが、私は憲法改正、指一本触れてはいけないということは申し上げていません。安易な改正がよくないと申し上げているんですよ。ほかの国では、三分の二の議員の賛成によってきちんと改正しているわけじゃないですか。安易に国防軍とか、安易なことをおっしゃれば国民は警戒するだけじゃないですか。きちんとした議論をして、深い議論をする中で初めて憲法を改正する。私は、憲法の改正の要件を変えるのではなく、議論を深めることが必要だと思いますが、いかがですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 議論を深めるのは当然のことだろうと思います。だからこそ、憲法調査会でしっかりと深い議論をお願いをしたいと思います。 (略)
藤末健三君 総理、私、資料五というのを配っておりまして、そこに憲法の前文がございます。そこで、一番初めにございます、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」ということがございますが、この点について総理はいかがお考えでしょうか。お願いいたします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) それはそのとおりなんだろうと思います。 (略)
藤末健三君 総理にお聞きしたいんですが、この条文をいかがお考えでしょうか。「新しい国へ」、読まさせていただきまして、ダッカの事件のことが書かれておりますけど、その見解をお聞かせください。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 私は行政府の長でございますから、当然、憲法遵守義務がございます。それを申し上げた上において、自由民主党においてこの前文はふさわしくないと、こう考えたわけであります。我が国の国民の平和とそして生命を守るためには、これはやはり我が国自身がしっかりと責任を持って守っていくべきだと、こう決意を表すべきだと、こう考えたわけであります。
藤末健三君 後ろの自民党議員の方からも北朝鮮を信用するのかというやじをいただきましたけど、私は、国を信用するんではなく、これは国民では、国、諸国ではなく諸国民と書いてございます。ですから、私は、国を信用するかどうかという議論ではなく、国民一人一人が平和を望んでいる、戦争したくないと望んでいるということは信用できると考えております。これはもう、そこだけは指摘させていただきます。また、この条文、経済的なつながりを、諸国民でございますから、国境を越えて諸国民がつながること、それによって平和を安定するというのは、私は総合安全保障の考え方につながると思います。経済を交流させ、そして平和を安定させるということ、これはまさしくTPPなどの自由貿易協定にもつながる考え方だと思うんですが、その点、いかがですか、総理。
内閣総理大臣(安倍晋三君) TPPについては、これは経済連携協定ですから、言わば自由な貿易を通じてお互いの利益を拡大させていこうという考え方なんだろうと思いますが。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し」というのは、言わば、自由民主党としては、やはり自国の国民の安全そして命を守ることについては、それは、他国に任せる、あるいは他国民、他国の人々に任せるのではなくて、それはやはり私たち自身が守らなければならないということだろうと、こう考えた。そう考えたことによって、我々の……(発言する者あり)少し静かにしていただけますか、我々の憲法を、草案を作ったところであります。
藤末健三君 今の平和憲法も、国防、防衛、自衛ということについては全く否定していないわけじゃないですか。その中において、このように諸国民が信頼するという言葉をわざわざ消すというのは、いろんな考え方を否定しているわけですよ、総理。その点、いかがですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) なかなか難解な質問をされておられるわけでありますが、これは自由民主党、私、今、総理大臣というよりも、自由民主党のかつての、自由民主党の昨年の草案についての解説を今質問されておられるんだろうと、このように思いますが、言わば「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」ということ、この言葉そのものにおいて、それは言わば政府の責任で国民の生命と財産を守る責任がそもそもないのかという考え方自体もこれは発生してくるわけでありまして、そう考えたわけであります。そういう議論を経て自由民主党の案ができたと、このようなことではないかと思います。
藤末健三君 私は、平和を愛する諸国民、それぞれの国民を信頼して平和を築いていくという考え方が必ず必要だと私は考えます。次に御質問したいのは、次の憲法の前文の項目で、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」とございますが、この解釈につきまして、法制局長官、お願いいたします。
○政府特別補佐人(山本庸幸君) その「恐怖と欠乏」という言葉でございますが、これは時代背景などから考えますと、平和のうちに生存する権利の言わば全く対極にある戦争によってもたらされる様々な惨禍のことをいうものと思っております。
藤末健三君 この条文に関します総理のお考えをお聞かせいただいてよろしいでしょうか。お願いします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 私の考え方を聞かれたわけでありますが、この平和のうちに生存する権利、当然その平和のうちに生存する権利というのはあるんだろうと思います。ただ、それは権利を主張するだけではその権利は確保されないわけでありまして、それはそれぞれの努力の結果であろうと思います。
藤末健三君 これは、それぞれの努力というよりも、我々日本国民が、全世界の国民がひとしく紛争や戦争といった恐怖、そして食事ができない、水が飲めない、教育が受けられないという欠乏から逃れるようにしていきますよということを書いてあるわけでございまして、それは私は逆に、日本が世界のための、平和のためにやると、それも武力を使わずに貢献していくことを書いていることだと思うんですが、その点、総理、いかがでございますか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) まさに我々、戦後、海外への援助等を通じてそうした世界をつくるために努力をしてきたところだろうと、このように思います。
藤末健三君 これはソニーの元CEOをされていた出井さんもおっしゃっていたことなんですが、平和国家宣言というのを日本はやるべきではないかということをおっしゃっております。私も同感でございます。例えば、今議論がありました、全世界の国民が平和に生存する権利を有し、それを実現すると、日本は実現していくんだということ、そしてまた、今まで議論がございました、例えば攻撃型兵器を日本は持っていない、専守防衛であるということ、そういうことがほとんどこのアジアの国々の方に知られていないのが私は現状だと思います、いろんな国を回って。その中におきまして、やはり我々は全世界の国民を武力を用いず平和にしていくこと、そしてまた、専守防衛である我々の、国防軍に変えるんではなく、我々は専守防衛の自衛隊であることを逆に宣言して知らしめることが重要だと思いますが、総理、いかがでございましょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 世界中、ほぼ世界中の国々が言わば軍隊を有するのは、それは自国の防衛のためであろうと思います。侵略のために軍隊を持つということではなくて防衛のためなんだろうと、このように思います。一方、残念ながら北朝鮮はミサイル、国連決議に反してミサイルの開発を行い、そして核実験まで行ったわけであります。そして、例えば、かつてというかずっと拉致作戦を実行して多くの、十三歳の少女を含む多くの日本人を拉致をした、国家としての意思として拉致をした国があるわけでありまして、そういう中において我々は国民を守るという義務を負っているということも忘れてはならないと思います。
藤末健三君 それを伺いますと、やはり国防軍にすればその北朝鮮の問題は解決するのかという話にもなりますし、また、総理に伺いたいのは、海外の日本人を救出することをやるようにしていかなきゃいけない、だから国防軍が必要だということも書いておられますけど、その点、いかがでございますか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 私は国防軍についてそういう解説をしたことはございませんが。つまり、国防軍というのは、先ほどももう既に答弁をさせていただいております。大切なことは、やはり国が国民の命を守るというこれは責務を負っているということをしっかりとこれは明記すべきではないかということではないかと思います。
藤末健三君 私はやはり防衛、国防というか、軍による武力による平和だけのみならず、やはり途上国の援助などを用いた総合的な、あと経済の交流といった総合的なやっぱり自国を守る安全保障を私はやるべきだと思います。それをどんどんどんどん削って、じゃ、防衛だけでやっちゃいましょうという考え方には全く賛同できません。ちなみに民主党は、先ほど申し上げましたように、二日前の党大会で綱領を改めました。その中に、日本国憲法が掲げる国民主権、基本的人権の尊重、そして平和主義の基本精神を具現化すると決めておりますが、その点について総理の御意見をいただきたいと思います。
内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、我々は、別に自衛隊を国防軍にするだけというようなことを全く言ってはいないわけでありまして、今までと同じように、国民の税金による言わば多くの国々に対する支援は今後とも重要な言わばこれは政策的な手段であるというふうに考えておりますし、そうした多くの国々が発展途上からだんだんこれは進んでいくことによって、我が国の平和と安定にもこれは寄与すると、こういう考えも持っております。御党の政策については、今私はここで論評する立場にはないと思います。
藤末健三君 私は、日本の安全保障を考えた場合に、やはり防衛のみならず、先ほど申し上げましたように、近隣諸国に対する支援も必要だと思いますし、もう一つございますのは、経済の交流を活性化し、そして総合的に経済的な安全保障をつくることだと思います。ただ、安倍総理の今までの議論を聞いていますと、それらを非常に否定しているような印象を受けます。安倍総理、いかがですか、それについて。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 今の議事録を見ていただいても、私の書いたものを見ていただいても、否定したことは全くございません。(引用ここまで)
内閣総理大臣(安倍晋三君) 自由民主党の憲法改正草案、これは昨年の四月二十八日に決定をしたものでありますが、その中において、自衛隊を国防軍として位置付けることにしております。自衛隊は、国内では軍隊とは呼ばれていない、軍隊ではないという位置付けでありますが、国際法上は軍隊として扱われているわけであります。私たちは、このような矛盾を実態に合わせて解消することが必要であると、こう考えております。もとより、シビリアンコントロールの鉄則を変えるつもりはもちろんございませんし、憲法の平和主義や戦争の放棄を変えるつもりも全くないわけであります。他方、憲法の改正については党派ごとに異なる意見がございますので、まずは、多くの党派が主張している憲法九十六条の改正から取り組んでいきたいと、こう考えております。
藤末健三君 二つの点を御指摘申し上げたいと思います。一つは、国際基準と合わないから直すということなんですが、我々は、やはり自衛隊、憲法に基づく自衛隊というものを説明する方が先じゃないでしょうか。まず一つございます。あともう一つございますのは、ここで国防軍という軍に名前を変えるということは余分な摩擦を起こすだけであって、何のプラスもないと考えますが、その点はいかがでしょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、この説明をするという今委員のお話でございますが、国内において自衛隊であって軍でないと、こう言っているわけでありますが、一方、海外における自衛隊の存在は軍隊として取り扱われる必要があるわけであります。また、場合によって、もし他国から侵略を受けた際に交戦したときに軍隊でなければ軍隊として取り扱われない、つまり捕虜として扱われるかどうかという、そうした問題も出てくるわけでございます。何よりも、自衛隊の諸君のこれは誇りの問題でもあると私は考えるわけであります。むしろ、国際社会においてはそれが常識でありますから、そこに合わせることによって逆にこれは矛盾が出てくるものではないと、このように思うわけであります。
藤末健三君 総理に申し上げますが、私は一義的に、私は防衛力は必要だと思っています。ただ、一義的に、国防軍になりますよということをもっていろんなものが解決するということは私はないと思います。具体的に我が国に必要な防衛はどうあるべきか、何が問題か、何が足りないかということを議論した上で、最後の答えとして国防軍というのが常識だと思いますけれども、いかがですか、その点について。
内閣総理大臣(安倍晋三君) もちろん、今、藤末議員が言われたように、安全保障については冷静な議論が必要でしょうし、何が必要かということも大切なんだろうと、このように思います。我が党での議論においては、これは実際に、今自衛隊はセルフディフェンスフォースと、こう言われているわけでありますが、実際に自衛隊の方々は海外で活動していく上において、これセルフディフェンス、つまり自分自身を守るんではないかというやゆがあるのも事実なんですね。自衛隊の諸君の誇りは、自分の命を懸けて国を守る、あるいは平和を維持する、それが彼らの誇りであります。まさに、国民のために命を懸ける彼らに必要なものは、何といっても私は誇りではないのかと思うわけでありまして、憲法を改正する際には、これは他国と同じように国防軍という記述が正しいのではないかと、私はこのように思うところでございます。
藤末健三君 その自衛隊の方々の意思を高めることだけをもって国防軍にするような話ではないと思います。私は、もし海外に行かれた自衛隊の方々が、セルフディフェンスフォースという名前に問題があるならば、法律で、例えばピースキーピングユニットとかと言うことできると思います。いかがですか、その点。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 世界中どこの自国を守る言わば実力組織も、基本的には大体どこも国防軍という、そういう名称を持っているわけでありまして、だからといってそれが侵略的なことではないわけでありまして、むしろこれが世界のグローバルスタンダードであろうと、このように思うわけでありまして、そこでやはり、彼らは、これは自衛隊の諸君、東日本大震災におきましても本当に大変な活躍をしてくれました。彼らが、まさに危険を顧みず、事に当たって危険を顧みず任務を遂行すると、もって国民の負託にこたえてまいりますという宣誓をする、言わば自分は命を懸けますよということを宣誓する唯一の公務員と言ってもいいわけでありまして、その士気を維持する、これはまさに日本の国民の命を守ることに最も大切なことではないのかなと、このように思うわけでございます。
藤末健三君 私は、士気を維持するために国防軍に変えるというのは余りにも短絡な議論だと思います、総理、正直申し上げて。まず必要なことは、例えば防衛予算がどれだけあり、そして防衛の装備はどれだけあり、そしてどれだけの自衛隊の方々の数が必要か、そういう議論をまずすべきではないですか、いかがですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) もちろん我々はそういう議論もしております。と同時に、生身の人間がそこでは働いている、まさに国を守っているわけであります。家族もいる、また愛する人もいるわけであります。その彼らのことも私は十分に考えるべきではないのかなと、こう思うわけでありまして、一方、では、国防軍にするということにどこに問題があるのかということであります。そうすると、ほかの国もみんな国防軍でありますから、あなたのところは問題があるということなのかといえば、それはそんなことはないわけでありまして、殊更日本だけが国防軍にしていけないという理由は見当たらないのではないかと、このように思います。
藤末健三君 二つのことを申し上げたいと思います。一つは、やはり国際標準という話にしてしまえば、全部憲法も国際標準に変えるという話になりかねませんか。全部、じゃ、国際標準に合わせた憲法に変えてしまえばいいという話になりかねないと思いますし、そしてまた、国防軍というそんな非常に重要な議論を士気を高めますというだけの話で進めてよろしいんですか。そこを二点お聞かせください。
内閣総理大臣(安倍晋三君) もちろんこれは簡単な議論ではなくて、今の状況でただ国防軍に名前を変えるのではなくて、これ憲法改正が必要であります。逐条ごとに改正をしなければいけませんから、これは国民投票も必要でしょうし、そして九十六条を変えていないのであれば三分の二の発議が必要であります、衆参それぞれの。ですから、これは相当の議論を経なければ、それは成し遂げない。つまり、相当の議論をしてもそれは成し遂げるべきだと我々は考えているわけでございまして、そういう議論を、これはまずは九十六条を変えていくべきだというのが我々の考えでありますが、それと国際標準との関係ということでおっしゃっておられましたが、もちろんこれは全て国際標準に合わせる必要は全くないわけであります。また、憲法の九条についても、第一項は我々も残していくわけであります。同時に、言わばこの実力組織においては、なぜ、では海外と標準を合わせなければいけないかといえば、PKO活動等においては一緒に活動する部隊があって、我が方だけが別の規定で動いているということになると、果たしてそれはうまくいくのかどうかという議論は根強く残っているわけでありますし、そして我が国を防衛する中においては、これは、我が国の事情だけで完結するのではなくて、相手があることであります。よって、これは国際的な標準ということを考えるべきであろうと。特に軍隊、海外でいえば軍隊、自衛隊が活動する上において、国際法的な観点をこれは当然考慮するのは当たり前のことではないかと、このように思うわけであります。
藤末健三君 安倍総理に二つのことを指摘させていただきたいんですが、一つは、自民党の憲法改正案、九条の一項は書き換えていますので、それは御理解いただきたいということが一つ。そして、もう一つございますのは、基本的な考え方を変えないのであれば、今まで、後で議論しますけれども、様々な議論があって、政府解釈などがあります。六十年間の議論が積み重なっている。そういう議論をないがしろにすることにもつながりかねないんじゃないかということを考えることを申し上げます。私はちょっと、ここで御質問でございますけれど、総理は、国防軍にします、じゃ、防衛費をどれぐらい増やさなきゃいけないとお考えでしょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 防衛力については、これは安全保障環境の状況も考慮しながら、また当然財政状況というのも考慮しながら総合的に判断をしていくべきだろうと、このように思います。
藤末健三君 GDPの一%枠というのがございましたけれど、その点についてはいかがでしょうか。総理にお聞きします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 防衛費は何のために使われるかといえば、国民の生命、財産、領土、領海、領空を断固として守り抜いていくためであります。自衛隊がその持てる現在の能力を最大限に発揮をすることは当然でありますが、その上において、政府としては、我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増していることなどを踏まえて、防衛体制の強化のために平成二十五年度予算案では防衛費の増額を図っているわけであります。今、そこで、委員の御指摘のあったGDP一%枠でありますが、それは既に昭和六十一年に廃止をされて、御承知のとおりでありますが、ただ、防衛費の在り方については、先ほどお話をさせていただきましたように、安全保障環境等の対外的な要因を踏まえる必要があります。防衛費をGDPと機械的に結び付けることは私は適切ではないと考えております。もちろん、厳しい財政事情を踏まえて、効果的、効率的な防衛力整備を行っていくことは不可欠でありますが、そうしたことを総合的に勘案をしていくべきであろうと思います。
藤末健三君 安倍総理のこの二年、三年の、二年ですね、のいろいろな憲法改正、国防軍に関する資料を集めさせていただいたんですが、やはり多くのところで防衛費を増額しなけりゃいけないということをずっとおっしゃっているんですよ。その点はもう変わられたんですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 防衛費は増額しなければならないと考えておりましたから、だからこそ来年度予算については、本予算において十一年ぶりに防衛費を増額することにしたところであります。
藤末健三君 防衛大臣に伺いますが、陸海空の予算の配分のこの三十年間の推移をお教えください。お願いします。
国務大臣(小野寺五典君) 陸海空の各自衛隊の歳出予算の割合ですが、例えば昭和五十九年の時点では、陸が四二・四、海上自衛隊が二七・八、航空自衛隊が二九・八ということですが、平成二十五年は、陸上自衛隊が四四・一、海上自衛隊が二九・二、航空自衛隊が二六・七ということになっています。
藤末健三君 今の説明では非常に分かりにくいんですが、この三十年間ほとんど変わっていません。一、二%です、変動は。ずっと陸海空の防衛予算の配分の割合は変わっていないという状況でございますが、安倍総理はこのような状況をどのようにお考えでしょうか。お願いします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) この十年間、財政状況が非常に厳しい中で、日本の場合は大体各省庁同じように横並びで減らしていくわけでありまして、そういう中において、事実上少しずつ防衛費を減らしてきたという状況があります。ところが、このアジア太平洋地域の安全保障環境は厳しさを増しているわけでありまして、そういう中において、対外的な要因をしっかりとこれは勘案するべきだというのが私の考え方でありまして、その考え方にのっとって来年度予算について我々は予算編成を行ったということであります。
藤末健三君 私が申し上げたいのは、冷戦が終了し、そして北朝鮮の問題が起き、先ほど御指摘いただきましたようにアジア太平洋地域の緊張が高まっているという中、陸海空の予算配分は全然変わらないという状況でございます。それについてどう考えているかということをお聞きしております。
国務大臣(小野寺五典君) 予算につきましては、実はその比率、各年度で若干違います。例えば、航空自衛隊等で新しい装備を買う、あるいは海上自衛隊でイージス艦を建造する、こういう場合には多少比率は違っています。ただ、全体としていえば、実はこの防衛予算の八割が人件費等ということになりますので、残りの二割で実は各種装備の更新等を行ってきている、新しい装備がなかなか充実できない、これがここ二十年ずっと我が国が抱えてきた問題だと思っております。
藤末健三君 総理に申し上げたいのは、そのような問題をまず解決することが先であり、国防軍という名前を変えて士気を上げるということについて先に議論すべきでは私はないと思います。続きまして、九条に関しましてその解釈について議論させていただきたいと思います。資料の二と三というのがございますが、この集団的自衛権の行使を含む九条の解釈について様々な政府の解釈がございますが、その解釈につきまして、法制局長官、御説明をお願いいたします。
政府特別補佐人(山本庸幸君) お答えいたします。憲法九条につきましては、従来から自衛隊に関する様々な法律、条約、そして予算が国会で審議される過程におきまして、いろいろな議論が積み重なってきております。その基本となるものとしては、憲法九条の下においては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、これを排除するための必要最小限度の武力の行使を除いて、武力の行使は一般に禁じられているというものでございます。そこで、御指摘のまず海外派兵でございますが、これは、武力の行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することでありますし、集団的自衛権の行使、これは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、我が国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利を行使することにつきましては、そもそも我が国に対する武力攻撃が発生していない場合でございますので、憲法九条の下においては従来から許されないというふうに解釈されてきたわけであります。最後に、御指摘の攻撃的兵器の保有の禁止につきましては、憲法九条の下においても、個別的自衛権の行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは禁止されておりませんけれども、しかしながら、その性能上、相手国の領土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるそういう兵器の使用は、これは憲法上許されないというふうに解釈されてきたというわけでございます。
藤末健三君 このように、憲法に関する議論はもう長年の積み重ねがあるということは御理解いただけたと思いますが、このように、先人たちの長年の解釈の積み重ねがあった憲法の解釈を変えることについて、法制局長官はいかがお考えでしょうか。お願いします。
政府特別補佐人(山本庸幸君) いろんな観点で憲法について議論されることは結構でございますし、現に、現在、最近の安全保障環境を考慮して安保法制懇というところで議論されているところでございますが、私どもとしてはその結論を待っていろいろと検討させていただきたいと思っております。
藤末健三君 また総理にお聞きしたいんですけど、やはり私が思いますのは、いろんなところが変わりませんということで部分的に変わっているのが自民党憲法の改正案でございまして、変わらぬところは変える必要はないと思いますし、また、変えるところも、長年のいろんな議論があったわけでございますので、そういう議論を踏まえて検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 長年の議論を重視したら何にも変わらないんですね、世の中。つまり、変わるべきものはしっかりと変えていきたいし、言わば、先ほど申し上げましたように、我が国のこの平和主義については、我々それは不動のものであると、このように考えているわけでありますが、同時に、政府また国家は国民の命を守る、生命、財産を守るという大きな義務を負っているわけでありまして、安全保障環境が大きく変わっている中において、それをどう果たしていくかということについて不断の努力、検討していくのは当然の義務ではないかと、このように思っております。 (略)
藤末健三君 安倍総理は、徴兵制度は必要だとお考えでしょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 必要であるとは考えておりません。
藤末健三君 これ、総理としてじゃなくて自民党総裁としてお聞きすることになりますけれど、自民党憲法改正案では十三条、十八条、ここを改正することになっていますが、その意味は何でございましょうか。十三条と十八条です。資料の三ですね。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 自民党が取りまとめた日本国憲法改正草案において十三条及び十八条について改正案を示しておりますが、それは、その条文をより分かりやすくするため文言を改めたものであります。
藤末健三君 より分かりやすくするために文言を改めたとございますが、例えば十三条では「公益及び公の秩序に反しない限り、」とわざわざ書き換えておられますけど、この公の秩序というのはどういう意味ですか。これ、中には、これが徴兵制度につながるんではないかと、わざわざ書き換えているということを言う人もいますので、お願いします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、純粋に、公の秩序に反しないというのは当然のことであろうと、それを書き入れたわけでありまして、それと、先ほど申し上げましたように、徴兵というのは今の世界の趨勢において多くの国はそういう制度を取っておりません。むしろ、現代においてはそれは必ずしもうまく機能するとは限らないわけでありますし、私は全くそれは必要がないと、このように考えております。
藤末健三君 また、自民党の憲法の案の前文の第三パラグラフの方に「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、」とございます。そして、十三条の改正ということで、非常にその徴兵制度は心配じゃないかという方がおられますけれども、その点いかがでしょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) それは杞憂だろうと思います。
藤末健三君 私が申し上げたいのは、例えば先ほどの十三条の改正、公共の福祉という話をわざわざ書き換えておられるじゃないですか。その十三条についても、長年の議論があるわけじゃないですか、総理。そして、解釈されているものをわざわざ書き換えている。それは九条についても同じだと思います。ですから、その長年の議論があるものをきちんとわきまえた上で次のことを考えなきゃいけないと思いますが、いかがですか、総理。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 長年の議論等々というのは私も意味がよく分からないんですが、我々は、憲法についてはもう一度更にして、まあ言わば清らかな水のように、最初から、何が大切か、あらかじめ頭にインプットされたものではなくて、何が我が国のために大切か、日本の伝統と文化の中に根差したものについても思いをはせながら自由民主党の草案を考えたわけであります。
藤末健三君 それは聞き方によっては、今までの議論は全然考えずに、もう更から全部考えようというふうに聞こえますが、それでよろしいんですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 自由民主党は相当の議論を行っているんですね。憲法改正の議論を全く行っていない党もあるかもしれませんが、我が党は違います。相当の議論、真摯な議論を行いました。議論をするというのは、党においては時には相当の意見の対立もありますが、そういう中において取りまとめられたものが今度の自由民主党の憲法改正草案であります。その前に第一回目の改正草案もありました。そして、そういう長年の議論を経て、自由民主党は結党の際に憲法改正ということを掲げておりました。それから延々と五十年以上ずっと議論をしているわけでありますから、突然出てきたものでは全くないということは御理解をいただきたいと思います。 (略)
藤末健三君 総理にお聞きします。総理は九十六条の改正によく言及されておりますが、どのような改正の内容であり、そしてその理由、必要性は何かということを御説明いただけますでしょうか。お願いします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 今の法制局長官の説明にあったように、各国三分の二というのがあるんですが、一方、三分の二プラス国民投票ではないんですね。フランスもそれに代替の方法があるわけでありまして、日本のみが三分の二プラス国民投票なんですね。であるからこそ硬性憲法と言われています。我が党の案においては二分の一、そして更に国民の過半数、これが我が党の案でございます。なぜかといえば、国民の六割が、あるいは七割が改正したいと考えていたとしても、三分の一をちょっと超える国会議員が反対をすれば議論すらできないのはおかしいだろうというのが我々自由民主党の考え方であります。 (略)
藤末健三君 総理、いかがですか。アメリカ、ドイツ、フランス、同じような国会議員の要件が入っています、賛成の要件が。それでも、それぞれ六回、二十七回、五十八回と憲法を改正しているわけでございますけれども、その点についてはいかがですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) それは、各政党が現実的なアプローチをしていたんだろうと思います。日本のように不磨の大典として指一本触れてはならないと思うような政党がなかったからであろうと思いますね。
藤末健三君 あえて申し上げますが、私は憲法改正、指一本触れてはいけないということは申し上げていません。安易な改正がよくないと申し上げているんですよ。ほかの国では、三分の二の議員の賛成によってきちんと改正しているわけじゃないですか。安易に国防軍とか、安易なことをおっしゃれば国民は警戒するだけじゃないですか。きちんとした議論をして、深い議論をする中で初めて憲法を改正する。私は、憲法の改正の要件を変えるのではなく、議論を深めることが必要だと思いますが、いかがですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 議論を深めるのは当然のことだろうと思います。だからこそ、憲法調査会でしっかりと深い議論をお願いをしたいと思います。 (略)
藤末健三君 総理、私、資料五というのを配っておりまして、そこに憲法の前文がございます。そこで、一番初めにございます、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」ということがございますが、この点について総理はいかがお考えでしょうか。お願いいたします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) それはそのとおりなんだろうと思います。 (略)
藤末健三君 総理にお聞きしたいんですが、この条文をいかがお考えでしょうか。「新しい国へ」、読まさせていただきまして、ダッカの事件のことが書かれておりますけど、その見解をお聞かせください。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 私は行政府の長でございますから、当然、憲法遵守義務がございます。それを申し上げた上において、自由民主党においてこの前文はふさわしくないと、こう考えたわけであります。我が国の国民の平和とそして生命を守るためには、これはやはり我が国自身がしっかりと責任を持って守っていくべきだと、こう決意を表すべきだと、こう考えたわけであります。
藤末健三君 後ろの自民党議員の方からも北朝鮮を信用するのかというやじをいただきましたけど、私は、国を信用するんではなく、これは国民では、国、諸国ではなく諸国民と書いてございます。ですから、私は、国を信用するかどうかという議論ではなく、国民一人一人が平和を望んでいる、戦争したくないと望んでいるということは信用できると考えております。これはもう、そこだけは指摘させていただきます。また、この条文、経済的なつながりを、諸国民でございますから、国境を越えて諸国民がつながること、それによって平和を安定するというのは、私は総合安全保障の考え方につながると思います。経済を交流させ、そして平和を安定させるということ、これはまさしくTPPなどの自由貿易協定にもつながる考え方だと思うんですが、その点、いかがですか、総理。
内閣総理大臣(安倍晋三君) TPPについては、これは経済連携協定ですから、言わば自由な貿易を通じてお互いの利益を拡大させていこうという考え方なんだろうと思いますが。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し」というのは、言わば、自由民主党としては、やはり自国の国民の安全そして命を守ることについては、それは、他国に任せる、あるいは他国民、他国の人々に任せるのではなくて、それはやはり私たち自身が守らなければならないということだろうと、こう考えた。そう考えたことによって、我々の……(発言する者あり)少し静かにしていただけますか、我々の憲法を、草案を作ったところであります。
藤末健三君 今の平和憲法も、国防、防衛、自衛ということについては全く否定していないわけじゃないですか。その中において、このように諸国民が信頼するという言葉をわざわざ消すというのは、いろんな考え方を否定しているわけですよ、総理。その点、いかがですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) なかなか難解な質問をされておられるわけでありますが、これは自由民主党、私、今、総理大臣というよりも、自由民主党のかつての、自由民主党の昨年の草案についての解説を今質問されておられるんだろうと、このように思いますが、言わば「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」ということ、この言葉そのものにおいて、それは言わば政府の責任で国民の生命と財産を守る責任がそもそもないのかという考え方自体もこれは発生してくるわけでありまして、そう考えたわけであります。そういう議論を経て自由民主党の案ができたと、このようなことではないかと思います。
藤末健三君 私は、平和を愛する諸国民、それぞれの国民を信頼して平和を築いていくという考え方が必ず必要だと私は考えます。次に御質問したいのは、次の憲法の前文の項目で、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」とございますが、この解釈につきまして、法制局長官、お願いいたします。
○政府特別補佐人(山本庸幸君) その「恐怖と欠乏」という言葉でございますが、これは時代背景などから考えますと、平和のうちに生存する権利の言わば全く対極にある戦争によってもたらされる様々な惨禍のことをいうものと思っております。
藤末健三君 この条文に関します総理のお考えをお聞かせいただいてよろしいでしょうか。お願いします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 私の考え方を聞かれたわけでありますが、この平和のうちに生存する権利、当然その平和のうちに生存する権利というのはあるんだろうと思います。ただ、それは権利を主張するだけではその権利は確保されないわけでありまして、それはそれぞれの努力の結果であろうと思います。
藤末健三君 これは、それぞれの努力というよりも、我々日本国民が、全世界の国民がひとしく紛争や戦争といった恐怖、そして食事ができない、水が飲めない、教育が受けられないという欠乏から逃れるようにしていきますよということを書いてあるわけでございまして、それは私は逆に、日本が世界のための、平和のためにやると、それも武力を使わずに貢献していくことを書いていることだと思うんですが、その点、総理、いかがでございますか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) まさに我々、戦後、海外への援助等を通じてそうした世界をつくるために努力をしてきたところだろうと、このように思います。
藤末健三君 これはソニーの元CEOをされていた出井さんもおっしゃっていたことなんですが、平和国家宣言というのを日本はやるべきではないかということをおっしゃっております。私も同感でございます。例えば、今議論がありました、全世界の国民が平和に生存する権利を有し、それを実現すると、日本は実現していくんだということ、そしてまた、今まで議論がございました、例えば攻撃型兵器を日本は持っていない、専守防衛であるということ、そういうことがほとんどこのアジアの国々の方に知られていないのが私は現状だと思います、いろんな国を回って。その中におきまして、やはり我々は全世界の国民を武力を用いず平和にしていくこと、そしてまた、専守防衛である我々の、国防軍に変えるんではなく、我々は専守防衛の自衛隊であることを逆に宣言して知らしめることが重要だと思いますが、総理、いかがでございましょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 世界中、ほぼ世界中の国々が言わば軍隊を有するのは、それは自国の防衛のためであろうと思います。侵略のために軍隊を持つということではなくて防衛のためなんだろうと、このように思います。一方、残念ながら北朝鮮はミサイル、国連決議に反してミサイルの開発を行い、そして核実験まで行ったわけであります。そして、例えば、かつてというかずっと拉致作戦を実行して多くの、十三歳の少女を含む多くの日本人を拉致をした、国家としての意思として拉致をした国があるわけでありまして、そういう中において我々は国民を守るという義務を負っているということも忘れてはならないと思います。
藤末健三君 それを伺いますと、やはり国防軍にすればその北朝鮮の問題は解決するのかという話にもなりますし、また、総理に伺いたいのは、海外の日本人を救出することをやるようにしていかなきゃいけない、だから国防軍が必要だということも書いておられますけど、その点、いかがでございますか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 私は国防軍についてそういう解説をしたことはございませんが。つまり、国防軍というのは、先ほどももう既に答弁をさせていただいております。大切なことは、やはり国が国民の命を守るというこれは責務を負っているということをしっかりとこれは明記すべきではないかということではないかと思います。
藤末健三君 私はやはり防衛、国防というか、軍による武力による平和だけのみならず、やはり途上国の援助などを用いた総合的な、あと経済の交流といった総合的なやっぱり自国を守る安全保障を私はやるべきだと思います。それをどんどんどんどん削って、じゃ、防衛だけでやっちゃいましょうという考え方には全く賛同できません。ちなみに民主党は、先ほど申し上げましたように、二日前の党大会で綱領を改めました。その中に、日本国憲法が掲げる国民主権、基本的人権の尊重、そして平和主義の基本精神を具現化すると決めておりますが、その点について総理の御意見をいただきたいと思います。
内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、我々は、別に自衛隊を国防軍にするだけというようなことを全く言ってはいないわけでありまして、今までと同じように、国民の税金による言わば多くの国々に対する支援は今後とも重要な言わばこれは政策的な手段であるというふうに考えておりますし、そうした多くの国々が発展途上からだんだんこれは進んでいくことによって、我が国の平和と安定にもこれは寄与すると、こういう考えも持っております。御党の政策については、今私はここで論評する立場にはないと思います。
藤末健三君 私は、日本の安全保障を考えた場合に、やはり防衛のみならず、先ほど申し上げましたように、近隣諸国に対する支援も必要だと思いますし、もう一つございますのは、経済の交流を活性化し、そして総合的に経済的な安全保障をつくることだと思います。ただ、安倍総理の今までの議論を聞いていますと、それらを非常に否定しているような印象を受けます。安倍総理、いかがですか、それについて。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 今の議事録を見ていただいても、私の書いたものを見ていただいても、否定したことは全くございません。(引用ここまで)