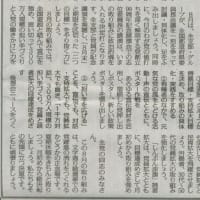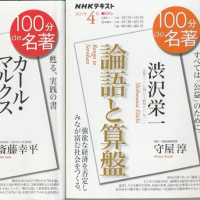集団的自衛権をめぐるマスコミ報道を見ていると、安倍首相たちの集団的自衛権行使論のウソとスリカエ、デタラメとトリックを暴く必要性を感じないわけにはいきません。中心的な視点について、いくつかあげておきます。
1.同盟国が攻撃を受けたら反撃するのは当然というウソとスリカエ
2.国際社会(国際法)で認められている集団的自衛権を行使できないのはおかしいというウソとスリカエ
3.集団的自衛権行使の歴史は、侵略の歴史だったという真実を覆い隠すウソとスリカエ
4.国際環境が変わったというウソとスリカエ
5.国際紛争を非軍事的手段によって解決することを合意した国際社会の到達点である国連憲章をはじめとした諸国際法と日本国憲法第9条の理念の具体化のために非軍事的安全保障論を「脅威」を口実に重視しないウソとスリカエ
まず、内閣法制局のスリカエです。以下の文章をお読みください。憲法第9条が禁止している「戦力」である「軍隊」「軍事力」を正当化したのは、内閣法制局でした。この組織は、この「軍隊」「軍事力」保持を正当化を目的に設置されたと言って過言ではありません。しかし、その内閣法制局の「番人」「番犬」ぶりが、ご主人様である国家、内閣、日米軍事同盟深化派・大東亜戦争正当化派・日米多国籍企業擁護派によって否定されようとしているのです。そこに使われている思想と論理は、ウソとペテン、デタラメ、トリックです。
第3章 第9条をめぐる現実の問題 1、第9条と自衛隊 清水睦『概説 憲法』(南雲堂深山社1971年4月28日刊)
自衛隊は、自衛隊法(1954年)により設置され、その目的は、「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする」(同法第3条第1項)にあるから、その目的に限定してみると、憲法第9条2項の禁止する「戦力」に該当するとみられる。すなわち、その編成、装備、訓練からすれば、まぎれもない「戦力」である。しかし、政府は、自衛隊は「戦力」であると明言しない。政府は、第9条について、当初、自衛戦力は保持できないとの解釈を行ない、その立場にその後拘束されながら、自衛隊を戦力にあたらぬものゆえ、憲法上適法な存在であるといわざるをえないため、戦力について、常識をこえる限定解釈をほどこしている。
この現実は、1950年、朝鮮戦争の勃発を契機とする警察予備隊の設置(マッカーサーの吉田書簡に基づく、ポツダム政令である「警察予備隊令」(1950年8月10日)による)から導かれてきたものである。警察予備隊の目的は、「わが国の平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障するのに必要な限度内で、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補うため」(同令第1条)とされたので、装備、人員が拡大されていったにもかかわらず(1952年には、11万、対戦車砲、迫撃砲をもち、訓練もほぼ軍隊となった)政府は、予備隊はもっぱら治安維持を目的とするから軍隊ではない(1950年吉田首相)、「戦力」は、戦争を遂行しうるに有効適切な兵力をいい、軍隊としての十分なる装備をもっているものを指すが、予備隊はこれにあたらぬ(1952年木村法務総裁)として、目的、装備などの点から、予備隊を合憲なものと主張した。
1952年10月(サンフランシスコ平和条約と、日本の自国防衛能力の漸増が期待された旧日米安保条約が4月に発効している)、予備隊は保安隊として発足し、海上警備隊(1952年4月海上保安庁法の改定で発足)とともに、新たに設置された保安庁の管轄下に置かれることになった。保安隊(陸)と警備隊(海)は、「わが国の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、特別の必要がある場合に行動する部隊」(1952年7月保安法第4条)となり、保安官11万、警備官7万5千、大砲、戦車、航空機(翌年戦闘機を持つ)を装備し、まぎれもない軍隊の相貌を整えるにいたった。かくて、保安隊が第9条に違反するという声の高まりに応じ、政府は「戦力」についておおむね次のような統一見解を表明した(1952年11月25日)。
憲法第9条2項は、自衛の目的でも戦力」の保持を禁止している。「戦力」とは、近代戦争遂行に役立つ程度の装備、編成を具えるものをいう。[戦力]の基準は、その国の置かれた時間的、空間的環境で具体的に判断せねばならない。「陸海空軍」とは、戦争目的のために装備編成された組織体をいい、「その他の戦力」とは、本来は戦争目的を有せずとも実質的にこれに役立ちうる実力を備えたものをいう。「戦力」とは、人的、物的に組織された総合力である。したがって単なる兵器、製造工場そのものは戦力の構成要素ではあるが「戦力」そのものでない。「戦力」に至らざる程度の実力を保持し、これを直接侵略防衛の用に供することは違憲ではない。このことは有事の際、国警の部隊が防衛にあたるのと理論上同一である。保安隊、警備隊は、保安庁法第四条に明らかなごとく、その本質は警察上の組織であって、戦争を目的として組織されたものではないから、軍隊ではない。また、客観的にみても、保安隊等の装備編成は、近代戦を有効に遂行しうる程度のものではないから、「戦力」に該当しない。(引用ここまで)
愛国者の邪論
一つは、ウソと詭弁とトリック、デタラメの事例をあげておきます。それは「特車」でした。こんなことが、マジに主張され、国民も認めた?のですから、大爆笑もんでしょう!
保安隊保安隊及び陸上自衛隊では「戦車」という区分の装備について、「保安隊(自衛隊)は“軍隊”ではない」という建前から、国民感情に配慮して「戦」の語の使用を避けて「特車」の名称を用いていた。陸上自衛隊発足後、警視庁警備部が「特型警備車(略称:特車)」の名称で装甲車を装備するようになったため、「警察用語との混同を避ける為」との理由で「戦車」に改称された。(引用ここまで)
二つは、内閣法制局が設置されたのはいつか、ということです。以下を見れば、内閣法制局の最初の仕事?は、上記清水睦氏の「保安隊が第9条に違反するという声の高まりに応じ、政府は「戦力」についておおむね次のような統一見解を表明した」との指摘が当てはまるのではないでしょうか。ここに内閣法制局の役割が如実になっているのではないでしょうか。以下の「法」「施行令」については、中身をご覧ください、山本庸幸前法制局長官発言や菅官房長官発言が、下記の「法」「施行令」の範囲内の発言であることが判ります。
内閣法制局設置法施行令(昭和27年7月31日政令第290号)
三つは、以下に指摘されている法制局の問題点、到達点について、です。
とりわけ、アメリカの戦争に詭弁を弄して参加する際に、重要な役割を果たしたのが、法制局であったことです。
同時に、ある種の「頑迷」さが、憲法解釈を政治主導によって実現しようとする勢力によって、法制局自身が「お荷物」的存在に転化し、形骸化させられるなかで、今回の長官の首挿げ替え事件、共産党風に言えば、「クーデター」が実行され、集団的自衛権行使論に対する「歯止め」としての法制局の存在が浮き上がってしまったということです。
そこで出てきたのがネガティブキャンペーンということです。以上のような背景を踏まえつつ、血を流させられる若者、自衛官、或いは国防軍の軍人として存在するであろう若者とその家族と関係者に対して、どのように訴えていくか、です。
無責任な脅威扇動者とまじめに「国のために」と考えている若者とその家族は分けて考えていかなければならないと思います。
以下ご覧ください。
集団的自衛権の行使はなぜ許されないのか 前内閣法制局長官 阪田雅裕
元内閣法制局長官·阪田雅裕さん「海外で武力、認める余地ない 解釈 ...
以上ご覧いただくと、憲法の平和主義を国際社会に生かしていくためには、何が必要か、です。軍事・暴力的安全保障論から、非軍事・非暴力的安全保障論への転換です。石破幹事長が述べたように、非軍事的手段を訴え、命令を拒否すれば、「処罰」=「死刑」を覚悟しなければならないことになりかねません。そういう意味では、現在のような軍事的集団的自衛権行使論が席巻していけば、人権と民主主義が「公」「公益」に反するということになりかねません。ナチスの手口を生かそうとする麻生氏など、強固な復古主義者たちが、自民党を牛耳っていることを踏まえるならば、危険水域に近づきつつあるということです。勿論、国民の運動がそうさせないように動くことは当然で、そのベクトルの合力として、歴史が刻まれていくのだと思いますが。