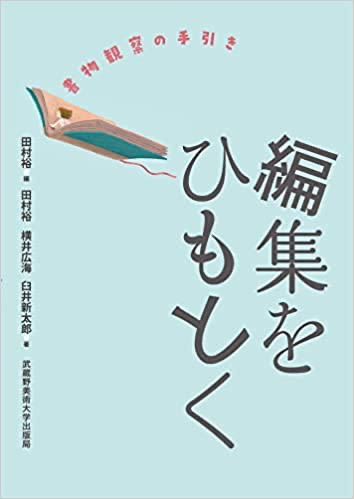一昨日の 小絲源太郎「随筆集 冬の虹」朝日新聞社 (1948/12) の内容から拾ってみる.
著者はこの本の刊行時 すでに還暦で,功なり名を遂げていたらしい.
16 トンの祖父母の世代より少し下かな,という感じ.自分が幼少時に聞かされたことと重なる部分もある.
数え年6歳で入った小学校はまぁ寺子屋で,ばあやがついてきてふたり並びの席のとなりに座った,とか.慶応の寄宿舎に入れられたところが一晩泣き明かして帰されてしまったとか...
美大の修学旅行の乱痴気騒ぎのときの上級生には,藤田嗣治,岡本一平,池部鈞 (良の父) などがいたとある.著者は藤田のように戦争画にはまることはなく,戦時中は俳句を捻っていたらしい.
「揚出しの話」というタイトルの一章があり,グルメ噺と思ったら,江戸時代から続く生家の料理屋「揚出し」の話だった.これは当時の東京人には知られたことだったらしく,新聞の川柳欄に
揚げ出しの帳場に小絲源太郎
というのが載ったこともあるという.
朝5時には店をあけ.朝湯も立て,吉原からの朝帰りの客に風呂つきの朝食を提供した,ある朝,最も苦手な数学の教師がいい気持ちそうに朝湯に入っているのを発見.それ以来先生は顔を見ればにたりと笑うようになりこちらもにこりと笑ってあげる.この「粘華微笑」は「しゃべるなよ」「かしこまりました」という意味だそうで,数学の点数も急上昇...
この料理屋の跡を継ぐのが嫌で嫌でたまらなかったが,幸い空襲で焼けてしまった,アメリカさんのおかげだそうだ.
ネットには著者が文展 (1918年 第12回) 初日に自作を破壊する事件を起こし,その後しばらく出品しなかったという記事があったが,そういう気性はこの本からは感じられない.
トップ画像左は本書の図版.その右の3枚はネットより.三色すみれがお好きらしく,同じ花瓶 (ヤフオクのはちょっと柄が違うようだ) で何枚も描いている.
著者はこの本の刊行時 すでに還暦で,功なり名を遂げていたらしい.
16 トンの祖父母の世代より少し下かな,という感じ.自分が幼少時に聞かされたことと重なる部分もある.
数え年6歳で入った小学校はまぁ寺子屋で,ばあやがついてきてふたり並びの席のとなりに座った,とか.慶応の寄宿舎に入れられたところが一晩泣き明かして帰されてしまったとか...
美大の修学旅行の乱痴気騒ぎのときの上級生には,藤田嗣治,岡本一平,池部鈞 (良の父) などがいたとある.著者は藤田のように戦争画にはまることはなく,戦時中は俳句を捻っていたらしい.
「揚出しの話」というタイトルの一章があり,グルメ噺と思ったら,江戸時代から続く生家の料理屋「揚出し」の話だった.これは当時の東京人には知られたことだったらしく,新聞の川柳欄に
揚げ出しの帳場に小絲源太郎
というのが載ったこともあるという.
朝5時には店をあけ.朝湯も立て,吉原からの朝帰りの客に風呂つきの朝食を提供した,ある朝,最も苦手な数学の教師がいい気持ちそうに朝湯に入っているのを発見.それ以来先生は顔を見ればにたりと笑うようになりこちらもにこりと笑ってあげる.この「粘華微笑」は「しゃべるなよ」「かしこまりました」という意味だそうで,数学の点数も急上昇...
この料理屋の跡を継ぐのが嫌で嫌でたまらなかったが,幸い空襲で焼けてしまった,アメリカさんのおかげだそうだ.
ネットには著者が文展 (1918年 第12回) 初日に自作を破壊する事件を起こし,その後しばらく出品しなかったという記事があったが,そういう気性はこの本からは感じられない.
トップ画像左は本書の図版.その右の3枚はネットより.三色すみれがお好きらしく,同じ花瓶 (ヤフオクのはちょっと柄が違うようだ) で何枚も描いている.