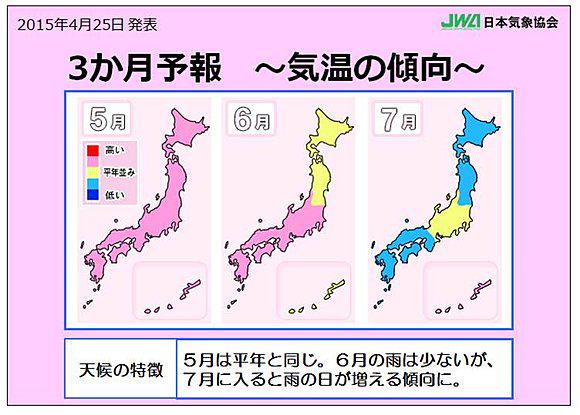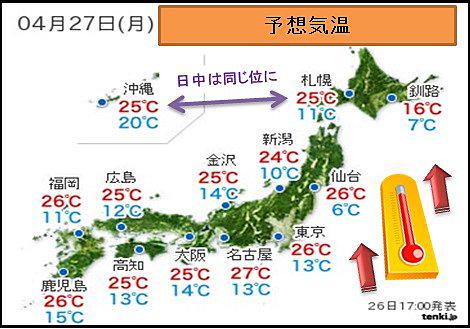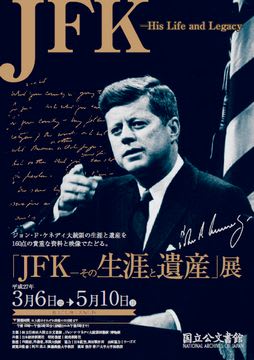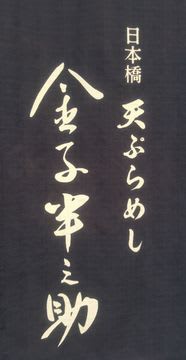巷では、ゴールデンウィーク開始となるのでしょうか?
そんなゴールデンウィーク初日の今日は、
京成電鉄にのって、国立歴史民俗博物館に行こうと
思っていたんですが、何と人身事故で運転取りやめ中。
駅で待っていると、そのうちに運転再開したのですが、
ダイヤが乱れまくっていて、何が何やら判らなかったので、
今日の国立歴史民俗博物館訪問は取りやめ。
コンティンジェンシープラン発動ということで、
地理的には東京湾を挟んで全く反対側の横浜方面にGO!
目的地は、三渓園。
以前も行ったことが有るんですが、今日は二回目の訪問。
今回の目的は、ゴールデンウィーク限定の企画、
臨春閣、蓮華院の公開があるから。
前回行った時は、外から眺めるだけでしたからねぇ。
これは行かねば!
最初から予定していたわけではないので、
三渓園に到着したのは、ちょうど昼頃。
ランチも摂らずに、早速園内徘徊開始です。
正門近くには、藤棚。

丁度いい位に藤が咲いています。
そしてこちらは、三渓園のシンボルとも言える大池。

遠景には、旧燈明寺三重塔が見えます。
こちらは鶴翔閣。

この日は、お茶会のために貸し出されていました。
なので、中には入れませんでしたorz
今回公開される建物は、内苑にあるので、そちらの方に向かいます。

御門を通り、内苑へ。
御門直ぐ脇には、白雲閣があるんですが、
こちらは今日は公開されず。
入口は開いていたんですけどね:-p
「関係者以外立入禁止」との旨の表示がありました。
そして臨春閣。

入口で靴を持ち歩く袋をもらい、靴を脱いで上にあがります。
入口直ぐの部屋が、鶴の間。

襖絵は狩野周信筆《鶴図》。
ここにあるのは複製で、実物は三渓記念館で
保存・公開されているそうです。
蕭湘の間。

襖絵は狩野常信筆《蕭湘八景図》。
ふすまの上の欄間は、『波紋様欄間』と言われ、
下絵は、狩野探幽の弟子、桃田柳栄と言われています。
当初は、銀箔で彩られていて、輝いていたそうです。
花鳥の間。

襖絵は狩野探幽筆《四季花鳥図》
住之江の間。

伝狩野山楽筆・川面義雄補筆《浜松図》
住之江って、大阪の住之江らしいです。
古来松の名所だとか。
そして、写真右下の、戸棚の扉がこれ。

見事な螺鈿細工でした。
廊下の壁に飾られていたのが、十二支板絵額。
伝狩野山楽筆。
十二支が衣をまとった姿で描かれています。






一枚の板絵に、二つづつ描かれているので、
六枚の板で、十二支になっています。
(たぶん)十二支の順番で並んでいますね。
次の間。

襖絵は雲澤等悦筆の《山水図》
この部屋には二階に上る階段があって、
写真右手の、禅宗様建築に見られる窓の形と取り入れた
火灯口が二階への入口になっています。

奥に、階段が見えます。
次の間の隣にある、天楽の間。

狩野安信筆《四季山水図》
臨春閣はここまで。
ここから入り口に戻るのではなく、
この先から外に出ます。
臨春閣から、内苑の奥に向かいます。
月華殿。

ちょっとした高台にあるので、階段をあがると見えてきます。
こちらは違う角度の月華殿。

こちらは、聴秋閣。

そして、こちらがもう一つの公開建築の蓮華院。
蓮華院の土間

土間の隣の広間

そして、こちらが小間の茶室

広間は六畳ありますが、小間は二畳中板で、
左下に小さく、小さい四角の炉をが見えます。
こちらの蓮華院は、“公開”と言っても、
建物に上がることが出来るわけではなく、
外から眺めるだけでした。

こちらは前回来た時も上がった旧矢箆原家住宅

茅葺屋根を保護するために、囲炉裏が焚かれていました。

こちらは大広間(?)

同じような写真ですが、違う部屋です。
こちらの囲炉裏は、焚かれてなかった気がします。
最初に藤棚を見ましたが、ツツジも見頃でした。


いやぁ、行って良かったです。
って言うか、最初からこちらを目的地にしていれば・・・(苦笑)。
-----
三渓園
http://www.sankeien.or.jp/










 a_log @a_log
a_log @a_log
































 tenki.jp @tenkijp
tenki.jp @tenkijp