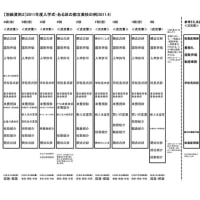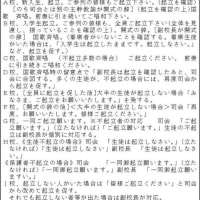◎佐藤春夫・高村光太郎・江口渙、そして江南文三・大江秋子夫妻
江南文三という名前は、どこかで聞いたことがあると思っていたが、昨日ようやく思いだした。江口渙〈エグチ・カン〉の『わが文学半生記』(青木文庫、一九五三)に何度も出てきた名前であった。
同書で、江南文三について書かれていることは、あるいは不正確な部分、記憶違いなどがあるかもしれないが、とにかくかなりの筆が費やされている。何よりも、この江南という詩人が、一時期は(つまり中学校教員になる前は)、文壇においてかなり注目されていた人物だったということがよくわかる。
まず、一九一二年(大正元)に、江南文三夫妻の家で、詩人の佐藤春夫に会うことになったところを引用してみよう。
あったのは本郷千駄木〈センダギ〉の森鴎外の家にそう遠くない、せまい露地〈ロジ〉を入ったおくの二階家だった。そこには「スバル」の編集をしていた江南文三夫婦が二階の六畳に間借をしていた。江南文三を私はずっと前に、金沢の四高でしっていた。私が一九〇五年に四高を退学して、また五高に入りなおしたりしたので、三年おくれて大学にきて見ると、江南はまだ卒業しないでぶらぶらしていた。そして、和辻哲郎との恋愛合戦で見事にたたかいとった恋人、大江秋子(今の詩人大江満雄のおばさんである)と同棲しながら石川啄木がやめたあとをうけて「スバル」の編集をして学資をかせいでいた。「スバル」には幸徳事件の弁護人をつとめた平出修〈ヒライデ・シュウ〉が金を出していた。石川啄木が、その頃、世間には極秘にされていた幸徳事件の真相を、はっきりしっていたのも「スバル」のかんけいで平出修としたしかったためである。私が当時すでに幸徳事件の真相を多少ともしっていたのもそのためだった。――江南文三は四高いらい新詩社の同人で与謝野鉄幹、与謝野晶子夫妻に愛され、「明星」にも「スバル」にもよく詩や歌をのせていた。「スバル」には自叙伝体のきわめてシニカルな小説を連さいしていた。詩も歌も当時の明星派の象徴主義の性格をもったものであったが、彼独自のきわめてシニカルな人生批判がつよく出ている点で特徴のあるものだった。文壇の一部からは鬼才文三〈ブンザ〉とまでいわれていた。おしいことに大学を出ると生活のために田舎の中学の先生になり、文学をやめて長年田舎まわりをしたあげく、最後は東京一中の先生になった。小田切秀雄なども江南に一中で英語をおそわったということだが、こんどの戦争の直後、一九四六年の二月に栄養失調で死んだ。年は私より一つ上だった。
一九一二年(大正元年)の秋の末ごろだった。私が江南の二階でおしゃベりをしていると、下から大江秋子の声で「佐藤春夫さんが見えましたよ」というのがきこえた。やがてあやしげな梯子段〈ハシゴダン〉をみしみしいわせながら上がってきた男を見ると、せいがひょろ長く、大きなまがった鼻と、大きな口と、大きな歯、長い顔、そして鼻めがねをかけた眼を神経質そうにしぱしぱさせている。新しい黒ビロードの服をきて、山高帽をかぶっていたのが、まず眼にとまった。
ここで、江口渙は、「年は私より一つ上だった」と書いているが、おそらく記憶違いであろう。江南文三は、一八八七年(明治二〇)生まれで、一九四六年(昭和二一)没、江口渙は、一八八七年(明治二〇)生まれで、一九七五年(昭和五〇)没、つまり、同年生まれである。
次に、一九一三年(大正二)に、江南文三夫妻の案内で、高村光太郎のアトリエを訪ねた一幕。
これはだれにもあることと思うが、私にもつぎのような経験がある。たとえば有名な作家芸術家を訪問した場合、それが前にもあとにもたった一回しか訪問しなかったために、その一回の訪問でうけた印象がかえってつよく残ることである。大学生時代に江南文三夫婦につれられて高村光太郎をたずねたときと、文壇に出てからあと、芥川龍之介、久米正雄の三人で谷崎潤一郎をたずねたときとの二つの場合がそれである。
高村光太郎を本郷駒込林町のアトリエにたずねたのは、私が「スバル」(一九二一年一二月号)に処女作「かかり船」をかいた、つぎの年、つまり一三年(大正二年)の春もおわりの頃だった。それは、アトリエの窓ぎわにおかれたテーブルの上に、牡丹桜の花がコップにさしてあったことを、いまだにおぼえているからである。
ことに、生まれてはじめてアトリエというものを見たことも、そのときの印象を一ときわつよいものにした。
高村光太郎はその頃、のちの「千恵子抄」の女主人公長沼千恵子と結婚したばかりだった。そのことは、彼が「スバル」に、
「男も多淫
女も多淫」
というような言葉の見える詩をかいていたことでも私はしっていた。私たち三人が、ぞろぞろアトリエに入っていったとき、長沼千恵子からあたえられた第一印象ははなはだ特異なものだった。
高村光太郎は「スバル」の同人であるかんけいで、きげんよく江南夫婦を迎えた。ところが長沼千恵子のほうは全然反対だった。北向きに高い窓のならんでいるそのアトリエの一とう東の端し〈ハシ〉の窓ぎわにある机に向かって本をよんでいた。そして私たちの存在に気がつきながら、全然ふりかえろうともしたかった。
「千恵子さん。この方が江南文三君ご夫妻ですよ。」
高村光太郎が特徴のある金属性のほそい声で丁重によびかけても、ただ一ど、ちらりとふり向いただけだった。そして、そのまま本によみふけった。それが帰るときまで、およそ一時間もつづいた。
一昨日のコラムで紹介したように、江南文三の『日本語の法華経』(大成出版、一九四四)の「序」は、高村光太郎が書いている。江南にとって高村は、三〇年以上前からの友人であり、なおかつ、「序」を頼めるような友人でもあったということになろう。
今日の名言 2012・12・3
◎江南文三氏はふるいわたしの知友である
高村光太郎の言葉。江南文三『日本語の法華経』(大成出版、1944)の「序」は、この言葉から始まる。「江南文三氏はふるいわたしの知友である。そのくせ此の十数年間に幾度といへる程度にしか実際は会つてゐない。会ふに及ばないほどの知友なのである」。上記コラム参照。