先に、野毛山公園に行った際に中村汀女先生の碑がありましたが、別途投稿すると約束しました。今回、横浜図書に行って調べたことを投稿いたします、
中村汀女先生(以下「汀女という。」)は、熊本市に生まれで東京世田谷区下北沢に住まわれていたとなっているのに、何故この横浜野毛山公園に汀女の碑があるのか、その関係を調べてみると次のようなことが分かりました。
概要「鑑賞現代俳句全集」第8巻著者代表中村汀女によれば、熊本市画図町(明治33年4月11日)に生まれ、旧姓齋藤、本名破魔子。熊本県立高女卒業し、大正9年中村重喜と結婚、大蔵省官吏の夫に従い、東京、仙台、名古屋、大阪、横浜、東京・仙台と任地を転々転居して、その間、二男一女を得て、昭和17年にようやく一家は東京世田谷区下北沢に落ち着いた。
俳句は、大正7年初めて「九州日日新聞」に投句、「ホトトギス」には翌年から投句。同9年、九州小倉在住の杉田久女を知る。昭和22年に「風花」を創刊、今日に至る。(昭和63年9月20日逝去)
昭和31年に中国の招きで文化訪問の副団長として、中国を訪問、昭和40年欧州からアメリカへ、同44年再び欧州へ旅。昭和47年勲4等宝冠章を受章、昭和55年「文化功労者」となった。
著書は、句集「汀女句抄」(昭和19年) 「花影」(昭和23年) 「都鳥」(昭和26年) 「紅白梅」(昭和43年) 「薔薇粧ふ」(昭和54年) 、随筆集は、「おんなの四季」(昭和31年) 「母のこころ」(昭和33年) 「風と花の記」(昭和48年)そのほか「婦人俳句のつくり方」(昭和43年)「俳句をたのしく」 (昭和43年)など多数となっていました。
また、汀女は、「熊本市画図町上江津」当時は、江津村の村長齋藤平四郎を父に持ち、母は、亭、当時の父は江津村の村長をつとめる名望家であったが、汀女は、幼い小学校の頃から、日曜日には、母からのいいつけで縁側の拭き掃除をしていた。これが続くある日雑巾を持ちながら,ふと前庭に咲いている寒菊を見て「われに返り見直す隅に寒菊赤し」となんだか「俳句」ともおもいたい言葉が浮んだのに、おどろき、また、たのしくて、次々に見ゆるものを17文字にし始めたのが、私の俳句の始まりで18歳であった。
短く言い得た幸福感、見たもの、感じたものを言葉に託した満足感、そうしたものが私を引っ張ってきたと思っている。ともありました。一日一句を詠い1年通したこともあり、多くは、日常の家庭内からの句が多く詠まれていた。また、故郷に帰るときには、車窓からの景色、欧州等の旅など同様に詠み収めるなど、すべてが俳句であった。
汀女は、子育ての繁忙期から暫く脱しかけているのに加え、肋膜炎に罹って病臥の生活が続いていた汀女に俳句によびもどしたのは、当時横浜に住んでいたことや詩心を甦らせる上で役に立ったのは、江津湖畔に育った彼女が横浜の海を見て、そぞろ胸中に湧きおこるものを覚え、友人の娘から、星野立子を紹介され立子の主宰する「玉藻」句会に毎月参加することで決定的に彼女は、「ホトトギス」俳句に立もどることが出来たのであった。
横浜での作「梨食(た)うふ雨後の港のあきらかや」
この句は、彼女のよく散歩した外人墓地のある山下公園や洋式庭園のある野毛山公園などでもそうした風景はよく見られたことであったろう。「印象派画家」のモネやブーダンのセーヌ河口の画家達の表現した素材のように、格好の素材となって「梨食(た)うふ」の梨の色、形が、雨あがりのさわやかな港の風景とマッチして、口中に噛む梨の歯ごたえ、そのすみずみしい味の広がりという。触覚味覚の世界を加えて、この句を一層爽やかなものに仕上げている。 洋画の世界に日本的なしめりを加えたといえる。この句の空気にはどこか雨後のしめりもひそむもようである。とも評価されている。
こうした句をみると中村汀女の確かな生を見る思いがするのだ。それは、自然薯の「おのれ信じて」生きてゆく姿勢に通うものである。また、幼時を過ごした農村江津湖周辺への愛着につながるものであり、其の処にこそ、汀女は俳人としての長い根っ子をおろしている人だと今更のように思わせる。と結んであった。
このように、中村汀女は、横浜にゆかりのある表現豊かな俳人であるとこをしみじみと知らされました。また、野毛山公園に碑があることの歓びさえ感じました。

(野毛山公園の散策路)

(中村汀女先生の碑)

(「鑑賞現代俳句全集」第8巻著者代表中村汀女からの写真)
中村汀女先生(以下「汀女という。」)は、熊本市に生まれで東京世田谷区下北沢に住まわれていたとなっているのに、何故この横浜野毛山公園に汀女の碑があるのか、その関係を調べてみると次のようなことが分かりました。
概要「鑑賞現代俳句全集」第8巻著者代表中村汀女によれば、熊本市画図町(明治33年4月11日)に生まれ、旧姓齋藤、本名破魔子。熊本県立高女卒業し、大正9年中村重喜と結婚、大蔵省官吏の夫に従い、東京、仙台、名古屋、大阪、横浜、東京・仙台と任地を転々転居して、その間、二男一女を得て、昭和17年にようやく一家は東京世田谷区下北沢に落ち着いた。
俳句は、大正7年初めて「九州日日新聞」に投句、「ホトトギス」には翌年から投句。同9年、九州小倉在住の杉田久女を知る。昭和22年に「風花」を創刊、今日に至る。(昭和63年9月20日逝去)
昭和31年に中国の招きで文化訪問の副団長として、中国を訪問、昭和40年欧州からアメリカへ、同44年再び欧州へ旅。昭和47年勲4等宝冠章を受章、昭和55年「文化功労者」となった。
著書は、句集「汀女句抄」(昭和19年) 「花影」(昭和23年) 「都鳥」(昭和26年) 「紅白梅」(昭和43年) 「薔薇粧ふ」(昭和54年) 、随筆集は、「おんなの四季」(昭和31年) 「母のこころ」(昭和33年) 「風と花の記」(昭和48年)そのほか「婦人俳句のつくり方」(昭和43年)「俳句をたのしく」 (昭和43年)など多数となっていました。
また、汀女は、「熊本市画図町上江津」当時は、江津村の村長齋藤平四郎を父に持ち、母は、亭、当時の父は江津村の村長をつとめる名望家であったが、汀女は、幼い小学校の頃から、日曜日には、母からのいいつけで縁側の拭き掃除をしていた。これが続くある日雑巾を持ちながら,ふと前庭に咲いている寒菊を見て「われに返り見直す隅に寒菊赤し」となんだか「俳句」ともおもいたい言葉が浮んだのに、おどろき、また、たのしくて、次々に見ゆるものを17文字にし始めたのが、私の俳句の始まりで18歳であった。
短く言い得た幸福感、見たもの、感じたものを言葉に託した満足感、そうしたものが私を引っ張ってきたと思っている。ともありました。一日一句を詠い1年通したこともあり、多くは、日常の家庭内からの句が多く詠まれていた。また、故郷に帰るときには、車窓からの景色、欧州等の旅など同様に詠み収めるなど、すべてが俳句であった。
汀女は、子育ての繁忙期から暫く脱しかけているのに加え、肋膜炎に罹って病臥の生活が続いていた汀女に俳句によびもどしたのは、当時横浜に住んでいたことや詩心を甦らせる上で役に立ったのは、江津湖畔に育った彼女が横浜の海を見て、そぞろ胸中に湧きおこるものを覚え、友人の娘から、星野立子を紹介され立子の主宰する「玉藻」句会に毎月参加することで決定的に彼女は、「ホトトギス」俳句に立もどることが出来たのであった。
横浜での作「梨食(た)うふ雨後の港のあきらかや」
この句は、彼女のよく散歩した外人墓地のある山下公園や洋式庭園のある野毛山公園などでもそうした風景はよく見られたことであったろう。「印象派画家」のモネやブーダンのセーヌ河口の画家達の表現した素材のように、格好の素材となって「梨食(た)うふ」の梨の色、形が、雨あがりのさわやかな港の風景とマッチして、口中に噛む梨の歯ごたえ、そのすみずみしい味の広がりという。触覚味覚の世界を加えて、この句を一層爽やかなものに仕上げている。 洋画の世界に日本的なしめりを加えたといえる。この句の空気にはどこか雨後のしめりもひそむもようである。とも評価されている。
こうした句をみると中村汀女の確かな生を見る思いがするのだ。それは、自然薯の「おのれ信じて」生きてゆく姿勢に通うものである。また、幼時を過ごした農村江津湖周辺への愛着につながるものであり、其の処にこそ、汀女は俳人としての長い根っ子をおろしている人だと今更のように思わせる。と結んであった。
このように、中村汀女は、横浜にゆかりのある表現豊かな俳人であるとこをしみじみと知らされました。また、野毛山公園に碑があることの歓びさえ感じました。

(野毛山公園の散策路)

(中村汀女先生の碑)

(「鑑賞現代俳句全集」第8巻著者代表中村汀女からの写真)













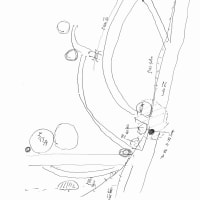






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます