昨日、発表された1月の家計調査の結果は、勤労者世帯の実質消費支出が100.2で前月比+2.2と極めて好調なものだった。さっそく、消費増税前の駆け込みという見方で賑わっていたが、それだけかね。紋切り型がはびこる時にこそ、何かないかと探すべきだろう。発見は、新たに現れたものより、探していなかったところにあるものだ。
消費の分析の基本は、まず収入を見ること。これに強く規定されるのが特徴だからだ。ここで「アベノミクスで気分が明るくなったから」と心理のせいにしてしまうと、見えるものも見えなくなる。教科書では効用最大化を教え込まれるから、満足度のような心理的なものをイメージしがちだが、実態は違う。悲しいかな、ヒトはカネがあれば使ってしまう存在なのだ。
そこで、勤労者世帯の季節調整済指数を見ると、実質実収入は100.2と前月比+1.4も増えている。駆け込み需要より、収入増が大きな要因になっていることが分かるだろう。実収入の増というと、アベノミクスでボーナス増かと早合点してしまうが、名目実収入を見ると、+1.1である。つまり、このところ収入増が物価高で相殺されていたものが、今回は一服しているということだ。
これが、円安波及の一巡だとうれしいのだが、消費者物価の東京都区部(2月)を見ると、そうでもないらしい。しかし、緩やかに実収入が増す中で、いずれは一巡するのだから、景気には明るい展望を抱くことができるだろう。むろん、4月に消費増税がなければだが。増税で物価が上がれば、消費が減るというのは、経済学の基本原理である。もっとも、価格メカニズムより、それを補うとされる金利メカニズムの信奉者ばかりだけどね。
こうしてみると、消費増税で景気が落ち込んだときに、更なる金融緩和で円安にしたら、かえって消費の足を引っ張りかねないことが分かる。米国の景気が不調で輸出数量が振るわないのが明らかなら、円安を避ける方が賢明かもしれない。家計調査を仔細に眺めると、裨益する発見は、いろいろあるわけだ。
………
ついでに、もう一つ。家計消費は、2013年1-3月期に異常に盛り上り、その余韻が2013年の景気の好調さを支えたのだが、景気が底入れしただけの局面で、そうしたことが起こり、景気を一気に持ち上げたというのは、なかなか珍しく、興味深い現象だった。そのメカニズムを家計調査で少し探ってみよう。
結論から言うと、2012年の不況期に、収入を補おうと、配偶者が働きに出ていたところに、景気が底入れして、すぐにパート収入が増し、消費を押し上げたようだ。そういう雇用状況の転換が収入の見通しを明るくし、消費性向を高めたこともある。これが2013年の後半になると、収入増の主役は世帯主にバトンタッチし、むしろ、配偶者の収入は減り気味になった。使う側が労働時間をパートから正社員に再配分したのかもしれないし、働く側も家計を補う必要性が薄れたのかもしれない。
配偶者の収入の影響の大きさを踏まえると、4月の消費増税後、消費の落ち込みと、収入の落ち込みが同時発生することも想定しておく必要がある。駆け込みの反動があっても、雇用が維持されれば、消費が戻ることも期待できるが、反動減で直ちにパートが整理され、収入が減ってしまうと、消費は戻りようがなくなる。つまり、増税後、消費は底をはうということである。その意味で、家計調査の配偶者の収入は、7-9月期の景気を占う注目点だろう。
消費の分析の基本は、まず収入を見ること。これに強く規定されるのが特徴だからだ。ここで「アベノミクスで気分が明るくなったから」と心理のせいにしてしまうと、見えるものも見えなくなる。教科書では効用最大化を教え込まれるから、満足度のような心理的なものをイメージしがちだが、実態は違う。悲しいかな、ヒトはカネがあれば使ってしまう存在なのだ。
そこで、勤労者世帯の季節調整済指数を見ると、実質実収入は100.2と前月比+1.4も増えている。駆け込み需要より、収入増が大きな要因になっていることが分かるだろう。実収入の増というと、アベノミクスでボーナス増かと早合点してしまうが、名目実収入を見ると、+1.1である。つまり、このところ収入増が物価高で相殺されていたものが、今回は一服しているということだ。
これが、円安波及の一巡だとうれしいのだが、消費者物価の東京都区部(2月)を見ると、そうでもないらしい。しかし、緩やかに実収入が増す中で、いずれは一巡するのだから、景気には明るい展望を抱くことができるだろう。むろん、4月に消費増税がなければだが。増税で物価が上がれば、消費が減るというのは、経済学の基本原理である。もっとも、価格メカニズムより、それを補うとされる金利メカニズムの信奉者ばかりだけどね。
こうしてみると、消費増税で景気が落ち込んだときに、更なる金融緩和で円安にしたら、かえって消費の足を引っ張りかねないことが分かる。米国の景気が不調で輸出数量が振るわないのが明らかなら、円安を避ける方が賢明かもしれない。家計調査を仔細に眺めると、裨益する発見は、いろいろあるわけだ。
………
ついでに、もう一つ。家計消費は、2013年1-3月期に異常に盛り上り、その余韻が2013年の景気の好調さを支えたのだが、景気が底入れしただけの局面で、そうしたことが起こり、景気を一気に持ち上げたというのは、なかなか珍しく、興味深い現象だった。そのメカニズムを家計調査で少し探ってみよう。
結論から言うと、2012年の不況期に、収入を補おうと、配偶者が働きに出ていたところに、景気が底入れして、すぐにパート収入が増し、消費を押し上げたようだ。そういう雇用状況の転換が収入の見通しを明るくし、消費性向を高めたこともある。これが2013年の後半になると、収入増の主役は世帯主にバトンタッチし、むしろ、配偶者の収入は減り気味になった。使う側が労働時間をパートから正社員に再配分したのかもしれないし、働く側も家計を補う必要性が薄れたのかもしれない。
配偶者の収入の影響の大きさを踏まえると、4月の消費増税後、消費の落ち込みと、収入の落ち込みが同時発生することも想定しておく必要がある。駆け込みの反動があっても、雇用が維持されれば、消費が戻ることも期待できるが、反動減で直ちにパートが整理され、収入が減ってしまうと、消費は戻りようがなくなる。つまり、増税後、消費は底をはうということである。その意味で、家計調査の配偶者の収入は、7-9月期の景気を占う注目点だろう。


















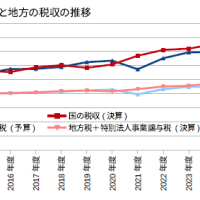





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます