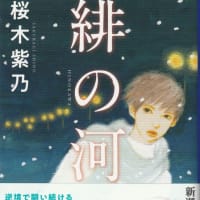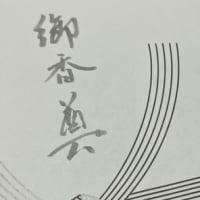東北新幹線には、各座席の背の網ポケットに
「トランヴェール」という月刊のフリーペーパーが置いてある。
JR東日本管内の様々な土地を紹介し、旅心をそそる内容。
季節によりテーマは風景だったり、文化だったりだが、
写真も記事もなかなかいい。
ワタシは毎月2回東京と岩手を往復するので、
自然に毎月読み、仕事の参考に持ち帰っている。
4月号の特集は「岩手の伝統技術」。
お馴染みの南部鉄器や南部煎餅焼き、南部型染めに混じり
全国的には意外に知られていない技術(というか文化)があった。

「南部絵暦」
むかし、文字が読めない農民達のために
季節の変わり目や農作業のタイミングを絵で表現したものだ。
例えば「荷物を背負って走る男」の絵がある。
荷を奪う泥棒を表現したものらしい。
「荷奪い」→「にうばい」→「にゅうばい」→「入梅」
と頓知が利いている。
表現方法も昔から決められ、
かつては木版を使って大量に作られていたとのこと。
とても微笑ましい、そして貴重な技術であり文化だと思う。

「刺し子・裂き織」
刺し子はご存知の通り昔の外套代わりにする半纏などを
寒さを防ぐよう厚くするため
極太の糸や時には布で編み込むように織ったもの。
裂き織とは古い着物を細かく細く裂き
改めてそれを織り込んで新たな布をリメイクするもの。
どちらも寒さの厳しい岩手の地ならではの工夫でもあり、
またそれが素朴な味わいのデザインになっている。
特に裂き織は元の布の色を様々組み合わせ、
カラフルにもなり、渋くもなり、
自由自在にデザインすることができる。
元来エコなものでありながら見た目もとてもオシャレだ。
これら伝統技術(文化)は
ワタシぐらいの歳の岩手人には馴染みもあるが
若い人たちには知られていないことが多い。
観光客のための記事でもあるが
岩手人にもぜひ目を通してもらいたい号だった。

この他、石川啄木の故郷である
旧玉山村(現盛岡市玉山区)の紹介記事が。
最近岩手というと何でもかんでも宮沢賢治さんだが
啄木の故郷である渋民も
岩手山と姫神山に挟まれた本当にいいところ。
北上川越しに岩手山を眺めたであろう歌もたくさん残っている。
「ふるさとの山に向ひて言ふことなし
ふるさとの山はありがたきかな」
「やはらかに柳あをめる 北上の
岸辺目に見ゆ 泣けとごとくに」
「かにかくに渋民村は恋しかり
おもいでの山 おもいでの川」
ちなみに今月号、
角田光代さんの巻頭エッセイもなかなかいい。
「トランヴェール」という月刊のフリーペーパーが置いてある。
JR東日本管内の様々な土地を紹介し、旅心をそそる内容。
季節によりテーマは風景だったり、文化だったりだが、
写真も記事もなかなかいい。
ワタシは毎月2回東京と岩手を往復するので、
自然に毎月読み、仕事の参考に持ち帰っている。
4月号の特集は「岩手の伝統技術」。
お馴染みの南部鉄器や南部煎餅焼き、南部型染めに混じり
全国的には意外に知られていない技術(というか文化)があった。

「南部絵暦」
むかし、文字が読めない農民達のために
季節の変わり目や農作業のタイミングを絵で表現したものだ。
例えば「荷物を背負って走る男」の絵がある。
荷を奪う泥棒を表現したものらしい。
「荷奪い」→「にうばい」→「にゅうばい」→「入梅」
と頓知が利いている。
表現方法も昔から決められ、
かつては木版を使って大量に作られていたとのこと。
とても微笑ましい、そして貴重な技術であり文化だと思う。

「刺し子・裂き織」
刺し子はご存知の通り昔の外套代わりにする半纏などを
寒さを防ぐよう厚くするため
極太の糸や時には布で編み込むように織ったもの。
裂き織とは古い着物を細かく細く裂き
改めてそれを織り込んで新たな布をリメイクするもの。
どちらも寒さの厳しい岩手の地ならではの工夫でもあり、
またそれが素朴な味わいのデザインになっている。
特に裂き織は元の布の色を様々組み合わせ、
カラフルにもなり、渋くもなり、
自由自在にデザインすることができる。
元来エコなものでありながら見た目もとてもオシャレだ。
これら伝統技術(文化)は
ワタシぐらいの歳の岩手人には馴染みもあるが
若い人たちには知られていないことが多い。
観光客のための記事でもあるが
岩手人にもぜひ目を通してもらいたい号だった。

この他、石川啄木の故郷である
旧玉山村(現盛岡市玉山区)の紹介記事が。
最近岩手というと何でもかんでも宮沢賢治さんだが
啄木の故郷である渋民も
岩手山と姫神山に挟まれた本当にいいところ。
北上川越しに岩手山を眺めたであろう歌もたくさん残っている。
「ふるさとの山に向ひて言ふことなし
ふるさとの山はありがたきかな」
「やはらかに柳あをめる 北上の
岸辺目に見ゆ 泣けとごとくに」
「かにかくに渋民村は恋しかり
おもいでの山 おもいでの川」
ちなみに今月号、
角田光代さんの巻頭エッセイもなかなかいい。