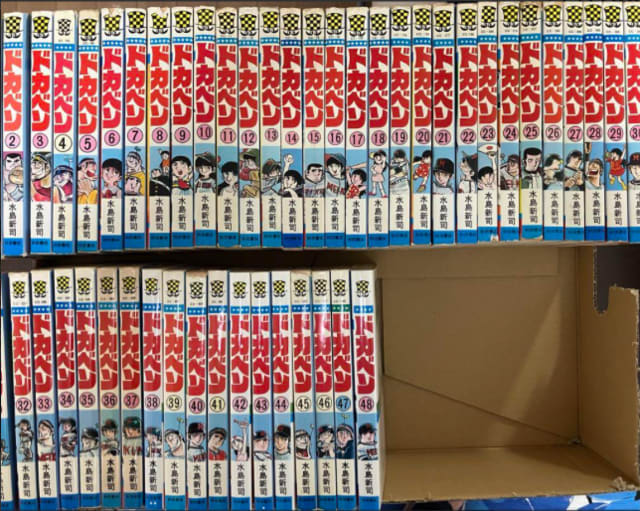話題のこのCDを買った。
それもサザンが「参加は最後」と言っている
夏フェス出演時のDVDがセットになった限定版。
相変わらずのサザンワールドが繰り広げられているが
夏フェス最後ということでより一層の感慨が込められている。
水戸黄門のような偉大なるマンネリではあるけれど
それがこのバンドの最大の魅力だろう。
ファンの期待を裏切らない。
ところで、サザン、ユーミン、中島みゆきの3人は
それぞれ約半世紀も人気を保っている稀代のアーティストたち。
たくさんの人たちが浮かんでは消える音楽業界の中にあって
なぜそんなことができているのだろうか。
まずはサザン。
このバンドの1番の特徴は、
いくつになっても大学のサークルのノリを失わないことだ。
メンバーを惹きつける桑田さんの強烈なカリスマ性はあるが
一方でみんな仲良く実に楽しそうだ。
イタズラっぽさも若い頃と変わっていない。
その時々の時代に共感を呼ぶ楽曲の良さもある。
そんなサザンも20代、30代の頃とは違った印象がある。
少々荒っぽいながら楽しそうに演奏するバンドサウンドの頃から
ブラスやストリングスまで使ってまとまった演奏の今。
恋愛などの切ない気持ちを歌った若い頃から
社会性を帯びてきている現在の楽曲。
彼らとともに年齢を重ねるファンもそれに追随していく。
一方で若い頃の曲も、ファンのノスタルジーを掻き立てるために
何年経っても古びることはない。
コンサートなどではそのバランスが絶妙だと感じる。
中島みゆきさんにも同じことを感じる。
個人的な内面を歌い上げて強烈な共感を得た若い頃から
今では社会を支える年代に響く楽興を提供。
(その歌詞表現がまた秀逸)
一方で昔の曲もファンのノスタルジーを掻き立てる。
サザンの場合は新しい曲でもあくまでサザンサウンドなのだが
みゆきさんの場合は「そうきたか」と思える引き出しの多さ。
ある意味詩人だし、優れたコンポーザーでもある。
ユーミンや達郎さんの場合はちょっと違う。
デビュー当時から30代ぐらいまでに発表した曲が
今も全く古びることなく受け入れられているという楽曲の魅力。
私的には、最近のお2人の曲を知らないけれど
それでも今でも昔の曲を好んで聴いている。
ユーミン独特の世界を描く歌詞といつまでもおしゃれなサウンド。
ファンクやドゥワップ、サーフロックなど
アメリカンポップスのいくつかの潮流を取り入れて
シティポップというひとつの音楽ジャンルを作り上げ
ひたすら音楽性を高めてきた達郎さん。
このお2人は時代とともに変遷してきたというよりも
自分の音楽のストックを徹底して増やしてきた感じ。
その土台にははっぴいえんどやティンパンアレーサウンドがある。
もはやユーミンというジャンル、山下達郎というジャンル。
少しづつ変革していった者たちと、変わらない者たち。
それぞれが時代は流れても広く受け入れられ続けている偉大さ。
とはいえ彼らも総じて70代になっている。
サザンが夏フェスからの引退を宣言したように
徐々に、あるいは突然姿を消す日もやがてやってくるだろう。
(まぁ80代になっても元気な海外アーテイストもいるが)
それでも恐らく彼らの楽曲は消えてなくなることはない。
全く個人的な好みだけど
最近の、角が丸くなった口当たりの良いサザンではなくて
初期のブルージーなバンドサウンドのサザンが
結構好きなんだなぁ😅