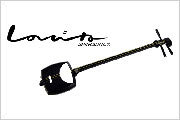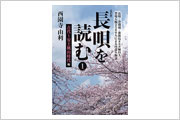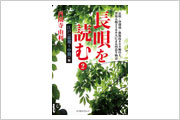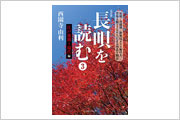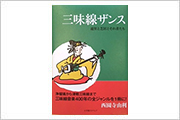「越後獅子」で歌右衛門が白星をつけた翌年(1812)、
森田座に、松風村雨物の「調松風」が出た。
六三郎の作曲で、狂乱した小藤に船頭が絡むという趣向。
恐らくは昨年の三津五郎の「汐汲」が好評だったにつき、
熱のさめやらぬうにち二匹目のどじょうを狙ってのことだろう。
こういう事だから、どんどんバリエーションが増えていくのだ。
歌右衛門は9月の中村座、お名残狂言で「舌出し三番叟」を踊って、
ひとまず大阪に引きあげた。
この頃市川団十郎(7代目)は22才になった。
六三郎は団十郎のための曲を次々と書くことになる。
例えば「晒女」(さらしめ)。
これは大力女”近江のお兼”を題材にしたもので、
高下駄をはいて登場したお兼のことを
「色気白歯の団十郎娘」と唄い、
お兼の履いている下駄の歯が白い、といいながら、
実はお兼は色気のないおぼこ娘なのだと、暗に説明している。
また、「まだ男には近江路や」と唄うことで、
お兼が男を知らない生娘で、ここが近江、琵琶湖の畔である、と暗に分かる。
このように一つの言葉にいくつもの意味を持たせるというのが、
日本語の心意気なのだ。
森田座に、松風村雨物の「調松風」が出た。
六三郎の作曲で、狂乱した小藤に船頭が絡むという趣向。
恐らくは昨年の三津五郎の「汐汲」が好評だったにつき、
熱のさめやらぬうにち二匹目のどじょうを狙ってのことだろう。
こういう事だから、どんどんバリエーションが増えていくのだ。
歌右衛門は9月の中村座、お名残狂言で「舌出し三番叟」を踊って、
ひとまず大阪に引きあげた。
この頃市川団十郎(7代目)は22才になった。
六三郎は団十郎のための曲を次々と書くことになる。
例えば「晒女」(さらしめ)。
これは大力女”近江のお兼”を題材にしたもので、
高下駄をはいて登場したお兼のことを
「色気白歯の団十郎娘」と唄い、
お兼の履いている下駄の歯が白い、といいながら、
実はお兼は色気のないおぼこ娘なのだと、暗に説明している。
また、「まだ男には近江路や」と唄うことで、
お兼が男を知らない生娘で、ここが近江、琵琶湖の畔である、と暗に分かる。
このように一つの言葉にいくつもの意味を持たせるというのが、
日本語の心意気なのだ。