マリ帝国の衰退にかわって登場したのが、ソンガイ帝国である。この帝国は、ガーナ王国やマリ帝国に比べると、やや東方つまりニジェール川の中流に、その起源を発する。現在のマリとニジェール国境近くに、ガオという都市がある。ガオは古くから東西の交易路の結節点として重要であり、ソンガイ王国は、このガオを首都とする一王国として、はじめはマリ帝国の支配に従っていた。
15世紀の後半になり、ソンニ・アリ王(Sonni Ali、在位1464年-1493年)は、ニジェール川の流れを利する水軍を組織、マリ帝国の支配地の征服を始め、トンブクトゥを占領した(1468年)。ソンニ・アリ王は、征服者としては秀でていたけれど、治世は残虐であった。それで、家臣のアスキア・ムハンマドがクーデタをおこし、王位を簒奪、ムハンマド王(Sarakollé Mohammed Touré、1493年-1528年)として新しい王朝を開いた。ムハンマド王の時代に、ソンガイ帝国の版図は大きく拡大した。
ムハンマド王も、2年におよぶメッカ巡礼を行うなど、イスラム教の王朝を志向した。とりわけ、トンブクトゥはその都市としての発展を、ムハンマド王の時代に謳歌する。当時の知的先進国であるアラブ世界から、宗教指導者や学者を招聘し、トンブクトゥは150余りのイスラム神学校が立ち並ぶ、イスラム学術の都市としても栄えた。
その後ソンガイ帝国は、北アフリカのモロッコ王による侵攻を受けて、分裂・滅亡する。ソンガイ帝国とモロッコの間のサハラ砂漠中央部に、テガザという岩塩鉱山があり、ながくソンガイ帝国がここを支配していた。この岩塩鉱山の略取を、モロッコ(サード朝)のマンスール王が試み、1585年にこの地を制した。さらに、1590年にはソンガイ帝国まで攻め入り、ここにソンガイ帝国は滅亡した(1591年)。以降、モロッコがこの地域にスルタンを派遣して支配し、とくに西アフリカ産の金は、モロッコの繁栄を潤した。
さて、このように今のコートジボワールのさらに北の地域で繰り広げられた、帝国の興亡史をおさらいしたのは、第一に西アフリカの内陸部に、これだけの歴史物語があることをご理解いだたきたかったからである。私も、ずいぶん世界史を勉強したけれど、ここに来るまでアフリカの内陸において、このような歴史の展開があることを知らなかった。世界史として世に教えられている歴史は、あまりに欧州に偏重があると思う。欧州の歴史の上では、アフリカは植民地支配の対象としてしか現れない。しかし、アフリカの人々の視点からは、きちんと固有の歴史があり、固有の社会の変動がある。
第二に、この北方帝国の興亡や、サハラ南縁の経済・交易活動が、コートジボワールの形成の歴史に、大きな影響を与えてきたということを述べたいからである。この北方帝国の興亡の時代を通じて、コートジボワールなどの密林地域は後背地でしかなかった。しかし、北における経済の拡大は、民族の大移動というかたちで、コートジボワールに影響を及ぼした。
繰り返しになるが、昔のコートジボワールでは、人口の多くは北半分のサバンナ地域に住んでいた。このサバンナ地域には、ニジェール川のデルタ地帯から広がる、セヌフォ(Sénoufo)族という農耕民族が生活していた。一方、南半分に広がる密林は、疎らであったとはいえ、森の中に点在するように生活している民族がいた。彼らはクル(Krous)族といい、今のギニアやリベリアあたりの密林の住人であった。
やがて、北方のサハラ南縁地域のマンデ(Mandé)系の部族は、経済・交易活動が活発になるにしたがって、南方への拡大を始めた。さらに、マリ帝国やソンガイ帝国の興亡により、圧迫を受けて移動する部族も出てきた。これらの部族のうち、コートジボワール北部に進出してきたのが、マリンケ(Malinké)族であり、さらにマリンケ族に押し出されるようにして南に移動してきた、同じマンデ系のバンバラ(Bambara)族である。さらに、西方ギニア方面から、別のマンデ系部族が、森林地域に進出してきた。これはダン族(Dan、ヤクバ族とも呼ぶ)とグロ(Gouro)族であり、コートジボワール中西部にほぼ落ち着いた。
この民族移動は、だいたい11世紀から16世紀まで、漸次続いてきたようである。その結果、コートジボワールの南半分にクル族、西部から中部にかけてダン族とグロ族、北半分のサバンナ地帯をセヌフォ族、マリンケ族、バンバラ族で分け合う、というような民族分布を、おおかたのところで形作った。
これとは別に、商業活動を通じて、コートジボワールに浸透していった人々がいる。中世以来長きにわたって、サハラ砂漠に向けての交易は、西アフリカにとって大きな富の源泉であった。そして、西アフリカにおいて、商品の流通を請け負う、商業が発達していた。1353年にマリ帝国を訪れた、アラブの大旅行家イブン・バトゥータは、この地域に「ワンガラ」というアフリカ人商人が活動していることを報告している。
この「ワンガラ」というのは、西アフリカの商人集団であり、イブン・バトゥータが見た商人たちの子孫は、その後西アフリカ各地に広がって商業ネットワークを築いた。彼らを総称して、「ジュラ(Dioula)」と言う。「ジュラ」とは、マンデ語で商人を意味している。ジュラ商人は、金の取引に従事するとともに、コラの実を交易した。コラの実は、イスラム世界の嗜好品としてたいへん好まれ、需要が大きかった。コラの実は、南部の密林の中で採集され、輸出するために北部に運ばれた。コラの実を求めて、人々は次第に密林の中に人々が入り込むようになった。
こうしたジュラ商人たちが、コートジボワールの各地に、商業ネットワークを張り巡らしたことは、注目しておいてよい。今でも、ジュラと呼ばれる北方起源でイスラム教を信仰する人々が、コートジボワールの都市という都市に住んで、商業・工業に従事している。庶民の市場で雑貨を売っている人々は、まず全員がジュラ商人である。だから、ジュラ語は市場における標準語となっており、たいがいのコートジボワール人は、自分の部族の言語とともに、ジュラ語を自由に話す。
さて、この民族分布図は、16世紀以降にはじまった全く別の要因によって、新たに大きな変動を来すことになる。西アフリカの海岸に、ヨーロッパ人の貿易商人たちがやってきたのである。ヨーロッパ人による海上交易の開拓、そして奴隷貿易の開始は、西アフリカの産する富をアラブやヨーロッパに運ぶ交易路の重心を、サハラ砂漠からギニア湾(大西洋)に移すことになった。これについては、また稿を改めるとしよう。
15世紀の後半になり、ソンニ・アリ王(Sonni Ali、在位1464年-1493年)は、ニジェール川の流れを利する水軍を組織、マリ帝国の支配地の征服を始め、トンブクトゥを占領した(1468年)。ソンニ・アリ王は、征服者としては秀でていたけれど、治世は残虐であった。それで、家臣のアスキア・ムハンマドがクーデタをおこし、王位を簒奪、ムハンマド王(Sarakollé Mohammed Touré、1493年-1528年)として新しい王朝を開いた。ムハンマド王の時代に、ソンガイ帝国の版図は大きく拡大した。
ムハンマド王も、2年におよぶメッカ巡礼を行うなど、イスラム教の王朝を志向した。とりわけ、トンブクトゥはその都市としての発展を、ムハンマド王の時代に謳歌する。当時の知的先進国であるアラブ世界から、宗教指導者や学者を招聘し、トンブクトゥは150余りのイスラム神学校が立ち並ぶ、イスラム学術の都市としても栄えた。
その後ソンガイ帝国は、北アフリカのモロッコ王による侵攻を受けて、分裂・滅亡する。ソンガイ帝国とモロッコの間のサハラ砂漠中央部に、テガザという岩塩鉱山があり、ながくソンガイ帝国がここを支配していた。この岩塩鉱山の略取を、モロッコ(サード朝)のマンスール王が試み、1585年にこの地を制した。さらに、1590年にはソンガイ帝国まで攻め入り、ここにソンガイ帝国は滅亡した(1591年)。以降、モロッコがこの地域にスルタンを派遣して支配し、とくに西アフリカ産の金は、モロッコの繁栄を潤した。
さて、このように今のコートジボワールのさらに北の地域で繰り広げられた、帝国の興亡史をおさらいしたのは、第一に西アフリカの内陸部に、これだけの歴史物語があることをご理解いだたきたかったからである。私も、ずいぶん世界史を勉強したけれど、ここに来るまでアフリカの内陸において、このような歴史の展開があることを知らなかった。世界史として世に教えられている歴史は、あまりに欧州に偏重があると思う。欧州の歴史の上では、アフリカは植民地支配の対象としてしか現れない。しかし、アフリカの人々の視点からは、きちんと固有の歴史があり、固有の社会の変動がある。
第二に、この北方帝国の興亡や、サハラ南縁の経済・交易活動が、コートジボワールの形成の歴史に、大きな影響を与えてきたということを述べたいからである。この北方帝国の興亡の時代を通じて、コートジボワールなどの密林地域は後背地でしかなかった。しかし、北における経済の拡大は、民族の大移動というかたちで、コートジボワールに影響を及ぼした。
繰り返しになるが、昔のコートジボワールでは、人口の多くは北半分のサバンナ地域に住んでいた。このサバンナ地域には、ニジェール川のデルタ地帯から広がる、セヌフォ(Sénoufo)族という農耕民族が生活していた。一方、南半分に広がる密林は、疎らであったとはいえ、森の中に点在するように生活している民族がいた。彼らはクル(Krous)族といい、今のギニアやリベリアあたりの密林の住人であった。
やがて、北方のサハラ南縁地域のマンデ(Mandé)系の部族は、経済・交易活動が活発になるにしたがって、南方への拡大を始めた。さらに、マリ帝国やソンガイ帝国の興亡により、圧迫を受けて移動する部族も出てきた。これらの部族のうち、コートジボワール北部に進出してきたのが、マリンケ(Malinké)族であり、さらにマリンケ族に押し出されるようにして南に移動してきた、同じマンデ系のバンバラ(Bambara)族である。さらに、西方ギニア方面から、別のマンデ系部族が、森林地域に進出してきた。これはダン族(Dan、ヤクバ族とも呼ぶ)とグロ(Gouro)族であり、コートジボワール中西部にほぼ落ち着いた。
この民族移動は、だいたい11世紀から16世紀まで、漸次続いてきたようである。その結果、コートジボワールの南半分にクル族、西部から中部にかけてダン族とグロ族、北半分のサバンナ地帯をセヌフォ族、マリンケ族、バンバラ族で分け合う、というような民族分布を、おおかたのところで形作った。
これとは別に、商業活動を通じて、コートジボワールに浸透していった人々がいる。中世以来長きにわたって、サハラ砂漠に向けての交易は、西アフリカにとって大きな富の源泉であった。そして、西アフリカにおいて、商品の流通を請け負う、商業が発達していた。1353年にマリ帝国を訪れた、アラブの大旅行家イブン・バトゥータは、この地域に「ワンガラ」というアフリカ人商人が活動していることを報告している。
この「ワンガラ」というのは、西アフリカの商人集団であり、イブン・バトゥータが見た商人たちの子孫は、その後西アフリカ各地に広がって商業ネットワークを築いた。彼らを総称して、「ジュラ(Dioula)」と言う。「ジュラ」とは、マンデ語で商人を意味している。ジュラ商人は、金の取引に従事するとともに、コラの実を交易した。コラの実は、イスラム世界の嗜好品としてたいへん好まれ、需要が大きかった。コラの実は、南部の密林の中で採集され、輸出するために北部に運ばれた。コラの実を求めて、人々は次第に密林の中に人々が入り込むようになった。
こうしたジュラ商人たちが、コートジボワールの各地に、商業ネットワークを張り巡らしたことは、注目しておいてよい。今でも、ジュラと呼ばれる北方起源でイスラム教を信仰する人々が、コートジボワールの都市という都市に住んで、商業・工業に従事している。庶民の市場で雑貨を売っている人々は、まず全員がジュラ商人である。だから、ジュラ語は市場における標準語となっており、たいがいのコートジボワール人は、自分の部族の言語とともに、ジュラ語を自由に話す。
さて、この民族分布図は、16世紀以降にはじまった全く別の要因によって、新たに大きな変動を来すことになる。西アフリカの海岸に、ヨーロッパ人の貿易商人たちがやってきたのである。ヨーロッパ人による海上交易の開拓、そして奴隷貿易の開始は、西アフリカの産する富をアラブやヨーロッパに運ぶ交易路の重心を、サハラ砂漠からギニア湾(大西洋)に移すことになった。これについては、また稿を改めるとしよう。



















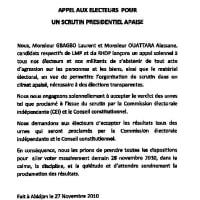
コートジボワール在住のメンバーから、「良いところだから、ぜひいらっしゃい」と誘われ、行ってみたいと思い始めた昨年の10月から、このブログを愛読しています。
8月23日の夜関空を飛び立ち、1ヶ月間滞在する予定ですが、コートジボワールの歴史や文化について、とても楽しく学ばせていただきました。
ありがとうございました。