日本大使の公邸に、武装勢力が乱入してきたというニュースは、映像とともにCNNやBBCなどの報道で流れ、多くの人々の耳目を驚かせた。日本の報道にも大きく取り上げられ、たくさんの方々に心配をかけてしまった。私たちの救出に向けて、フランス軍・政府、日本の外務本省、在仏大使館、国連代表部ほかの、全力をあげた努力をいただいた。多くの方々のおかげで、私は生き延びることができた。
一時は殺されることを覚悟したし、緊張と重圧のあの時間は、今でも思い出すと顔がひきつる思いになる。その15時間の間には、報道で伝えられた襲撃と救出という事実だけではなく、かなり込み入った展開と駆け引きがあったのだけれど、それを語るにはまだ、私の中で整理が必要だろう。
ここでは、その後多くの人々から問われた疑問にだけ触れておきたいと思う。それは、なぜそんなに危険な場面になるまで留まっていたのか、という問いである。私が十分に危険を認識し、早期に国外に脱出するなどしておけば、あのような事態を避けることができたし、これほど大勢の人々に迷惑をかけることはなかったはずだ。危険をきちんと予測し、適切な対応をとっていたのか。大使館をあずかる職務にある者として、私には説明責任があるだろう。
2011年3月の中旬に、度重なる調停努力にもかかわらず、政治的な解決の見通しは殆ど立たなくなった。北部の軍事勢力が集結を始め、やはり軍事的な衝突が避けられないのか、という情勢になりつつあった。東京の外務本省からは、大使館の待避を含めた対応を考えるように、指示が来ていた。私は現地を離れることは考えない、と答えた。
一つの理由は情勢の解釈にあった。「バグボ大統領」の指揮下にあるはずの国軍には、ほとんど戦う意欲がないことを、私たちは知っていた。国軍の兵士たちが意気地なしだったからではない。大統領選挙の後、バグボ側が勝利の根拠にした理屈が、まったくのでっち上げであることを、国軍の兵士たちは一番よく知っていた。「多くの地域で暴力があったので、13%の投票を無効にし、その結果得票51%でバグボが勝ち」とか、「選挙管理委員会がどう票を数えようと、憲法上は憲法院が宣言した側が勝利者」と言われても、まったく納得できなかった。それでも「バグボ大統領」が、政治をするのだと言っている間は、仕方なく忠誠を誓う。しかし、戦争をするのだと言い出したなら、それは話が違う。でっち上げの大統領のために命を落とすわけにはいかない。
実際のところ、ウワタラ大統領を支援するために、北部の軍がアビジャンに向けて進軍し始めた3月中旬、国軍や憲兵隊の兵士たちは、ただちに制服を脱ぎ捨て、武器を捨て、家に帰って一般市民になった。だから、わずか1ー2日の間に、北部軍は全く抵抗を受けずに、アビジャン近郊まで南下できた。私たちは、予想通りに戦況が進んでいることに、ある種の安心をした。もしアビジャンでの市街戦が始まったとしても、バグボ側にはもはや抵抗の力はなく、数日のうちに戦闘は終了するだろう、と。
それに、私たち外交団は攻撃の対象や巻き添えにはならないという、思いこみのようなものがあった。1月以来、バグボ側は、外国籍の市民に危害が及ばないよう、細心の注意を払っていた。国際社会による軍事介入を、とりわけフランス軍が動き出すことを、もっとも恐れていたからだ。アビジャン市内には、1万人以上におよぶフランス人がいた。彼らが悲鳴を上げれば、フランス軍に介入の口実を与えることになる。だから、フランス人や欧米諸国を刺激しないように、厳格な指示を出していた。その結果、あるフランス系ホテルのフランス人支配人が拉致された事件と、北欧の女性が流れ弾に当たって死亡した事件を除いては、欧米人の犠牲者は皆無であった。
だから私は、この2つの理由から、たとえ戦争になったとしても短期間で終わる、そして戦闘状態の中でも、外国人まして外交団に被害が及ぶことなはいだろう、と考えた。ところが2つの理由のそれぞれに、落とし穴があった。まず、たしかにバグボ側の正規軍が、戦闘を放棄するだろうという予想は、その通りであった。ところが、実際に市街戦が始まってみれば、バグボ側は国軍や憲兵隊ではなく、アフリカ中から雇い集めた傭兵を使って抵抗した。彼ら傭兵は、戦闘のプロであり、北部軍はたいそう手こずったのである。そして、傭兵の戦いに仁義はなかった。彼らにとって、公邸に掲げた日本国旗は、何の意味も持たなかった。
もちろんながら、武力衝突は避けられないという危険を、私は事前に十分認識していた。だから、日本人への退避勧告を出し、大使館員の数を最低限まで縮小し、在留邦人ほか各方面との通信・連絡体制を整え、生活維持のための備蓄を行うなどの準備をしていた。しかし、市街戦が長引き、私の公邸を巻き込むところまで発展するとは予測していなかった、というのが正直なところである。
ただ、たとえ相当の危険があるということを、正確に見通していたとしても、私はアビジャンを離れただろうか。北部の軍がアビジャンに集結し始めた時点で、市内にまだ在留邦人が残っていた。家族との関係、そのほかの事情で残留していた人々である。この方々をおいたまま、大使館の事務所を閉めるわけにはいかなかった。そして、私には大使として、この地において日本を代表するという役割があった。多少の危険があるからといって、日本国旗を畳んで逃げるなどということはできなかった。
何より私には、この大統領選挙にまで持っていく過程において、日本が中核の役割を果たしたという、誇りがあった。国連のチョイ代表や、フランス大使や、米国大使や、その他の大使たちとも、この誇りと連帯感を分かちあっていた。そして、大統領選挙の後の混乱の中で、私は引き続き、スイス大使などとともに、バグボ・ウワタラ両方の間を取り持ち、密かに武力衝突を避けるための調停工作に、中心になって関わってきていた。コートジボワールの危機を解決しようと、いっしょに取り組んできた同僚たちが、みんな危険を冒してでも頑張っているのに、どうして私だけが待避できようか。
欧州諸国のほぼ全て、中国、インドなども、大使が自ら残っていた。日本が臆病風を吹かせたなどという評価を、後世には微塵も残したくはなかった。私はこのことを、いっしょに残ってくれていた大使館員にも相談した。もし危険が迫っている、身の安全のため待避したいと考えるなら、アビジャンを離れてもいい、と。たった6名になっていた大使館員たちは、誰もが、職務だから、と言った。彼らは全員、激しい市街戦の中を、それぞれの自宅に閉じこめられながら砲撃に堪え、最後まで頑張り抜いてくれた。
危険な場面になるまで、どうして残っていたのか。危険に際して外交官はどう対応するべきなのかについて、さまざまな考え方があろう。不首尾な結末を迎えたことで、厳しくお叱りも受けた。私は、それらに耳を傾ける。私の事件以降も、世界の様々な場所で、外交官たちは危険に晒されながらも、それぞれの職務を守ってきた。私は一人の外交官として、あのときに私の選択をした。その結果、あのような事態に至ったことについては、まことに面目がない。しかし、私は大使として、日本国旗を最後まで掲げ続けたことを誇りに思っている。
一時は殺されることを覚悟したし、緊張と重圧のあの時間は、今でも思い出すと顔がひきつる思いになる。その15時間の間には、報道で伝えられた襲撃と救出という事実だけではなく、かなり込み入った展開と駆け引きがあったのだけれど、それを語るにはまだ、私の中で整理が必要だろう。
ここでは、その後多くの人々から問われた疑問にだけ触れておきたいと思う。それは、なぜそんなに危険な場面になるまで留まっていたのか、という問いである。私が十分に危険を認識し、早期に国外に脱出するなどしておけば、あのような事態を避けることができたし、これほど大勢の人々に迷惑をかけることはなかったはずだ。危険をきちんと予測し、適切な対応をとっていたのか。大使館をあずかる職務にある者として、私には説明責任があるだろう。
2011年3月の中旬に、度重なる調停努力にもかかわらず、政治的な解決の見通しは殆ど立たなくなった。北部の軍事勢力が集結を始め、やはり軍事的な衝突が避けられないのか、という情勢になりつつあった。東京の外務本省からは、大使館の待避を含めた対応を考えるように、指示が来ていた。私は現地を離れることは考えない、と答えた。
一つの理由は情勢の解釈にあった。「バグボ大統領」の指揮下にあるはずの国軍には、ほとんど戦う意欲がないことを、私たちは知っていた。国軍の兵士たちが意気地なしだったからではない。大統領選挙の後、バグボ側が勝利の根拠にした理屈が、まったくのでっち上げであることを、国軍の兵士たちは一番よく知っていた。「多くの地域で暴力があったので、13%の投票を無効にし、その結果得票51%でバグボが勝ち」とか、「選挙管理委員会がどう票を数えようと、憲法上は憲法院が宣言した側が勝利者」と言われても、まったく納得できなかった。それでも「バグボ大統領」が、政治をするのだと言っている間は、仕方なく忠誠を誓う。しかし、戦争をするのだと言い出したなら、それは話が違う。でっち上げの大統領のために命を落とすわけにはいかない。
実際のところ、ウワタラ大統領を支援するために、北部の軍がアビジャンに向けて進軍し始めた3月中旬、国軍や憲兵隊の兵士たちは、ただちに制服を脱ぎ捨て、武器を捨て、家に帰って一般市民になった。だから、わずか1ー2日の間に、北部軍は全く抵抗を受けずに、アビジャン近郊まで南下できた。私たちは、予想通りに戦況が進んでいることに、ある種の安心をした。もしアビジャンでの市街戦が始まったとしても、バグボ側にはもはや抵抗の力はなく、数日のうちに戦闘は終了するだろう、と。
それに、私たち外交団は攻撃の対象や巻き添えにはならないという、思いこみのようなものがあった。1月以来、バグボ側は、外国籍の市民に危害が及ばないよう、細心の注意を払っていた。国際社会による軍事介入を、とりわけフランス軍が動き出すことを、もっとも恐れていたからだ。アビジャン市内には、1万人以上におよぶフランス人がいた。彼らが悲鳴を上げれば、フランス軍に介入の口実を与えることになる。だから、フランス人や欧米諸国を刺激しないように、厳格な指示を出していた。その結果、あるフランス系ホテルのフランス人支配人が拉致された事件と、北欧の女性が流れ弾に当たって死亡した事件を除いては、欧米人の犠牲者は皆無であった。
だから私は、この2つの理由から、たとえ戦争になったとしても短期間で終わる、そして戦闘状態の中でも、外国人まして外交団に被害が及ぶことなはいだろう、と考えた。ところが2つの理由のそれぞれに、落とし穴があった。まず、たしかにバグボ側の正規軍が、戦闘を放棄するだろうという予想は、その通りであった。ところが、実際に市街戦が始まってみれば、バグボ側は国軍や憲兵隊ではなく、アフリカ中から雇い集めた傭兵を使って抵抗した。彼ら傭兵は、戦闘のプロであり、北部軍はたいそう手こずったのである。そして、傭兵の戦いに仁義はなかった。彼らにとって、公邸に掲げた日本国旗は、何の意味も持たなかった。
もちろんながら、武力衝突は避けられないという危険を、私は事前に十分認識していた。だから、日本人への退避勧告を出し、大使館員の数を最低限まで縮小し、在留邦人ほか各方面との通信・連絡体制を整え、生活維持のための備蓄を行うなどの準備をしていた。しかし、市街戦が長引き、私の公邸を巻き込むところまで発展するとは予測していなかった、というのが正直なところである。
ただ、たとえ相当の危険があるということを、正確に見通していたとしても、私はアビジャンを離れただろうか。北部の軍がアビジャンに集結し始めた時点で、市内にまだ在留邦人が残っていた。家族との関係、そのほかの事情で残留していた人々である。この方々をおいたまま、大使館の事務所を閉めるわけにはいかなかった。そして、私には大使として、この地において日本を代表するという役割があった。多少の危険があるからといって、日本国旗を畳んで逃げるなどということはできなかった。
何より私には、この大統領選挙にまで持っていく過程において、日本が中核の役割を果たしたという、誇りがあった。国連のチョイ代表や、フランス大使や、米国大使や、その他の大使たちとも、この誇りと連帯感を分かちあっていた。そして、大統領選挙の後の混乱の中で、私は引き続き、スイス大使などとともに、バグボ・ウワタラ両方の間を取り持ち、密かに武力衝突を避けるための調停工作に、中心になって関わってきていた。コートジボワールの危機を解決しようと、いっしょに取り組んできた同僚たちが、みんな危険を冒してでも頑張っているのに、どうして私だけが待避できようか。
欧州諸国のほぼ全て、中国、インドなども、大使が自ら残っていた。日本が臆病風を吹かせたなどという評価を、後世には微塵も残したくはなかった。私はこのことを、いっしょに残ってくれていた大使館員にも相談した。もし危険が迫っている、身の安全のため待避したいと考えるなら、アビジャンを離れてもいい、と。たった6名になっていた大使館員たちは、誰もが、職務だから、と言った。彼らは全員、激しい市街戦の中を、それぞれの自宅に閉じこめられながら砲撃に堪え、最後まで頑張り抜いてくれた。
危険な場面になるまで、どうして残っていたのか。危険に際して外交官はどう対応するべきなのかについて、さまざまな考え方があろう。不首尾な結末を迎えたことで、厳しくお叱りも受けた。私は、それらに耳を傾ける。私の事件以降も、世界の様々な場所で、外交官たちは危険に晒されながらも、それぞれの職務を守ってきた。私は一人の外交官として、あのときに私の選択をした。その結果、あのような事態に至ったことについては、まことに面目がない。しかし、私は大使として、日本国旗を最後まで掲げ続けたことを誇りに思っている。



















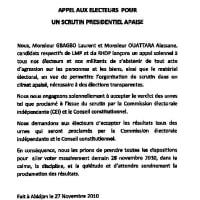
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます