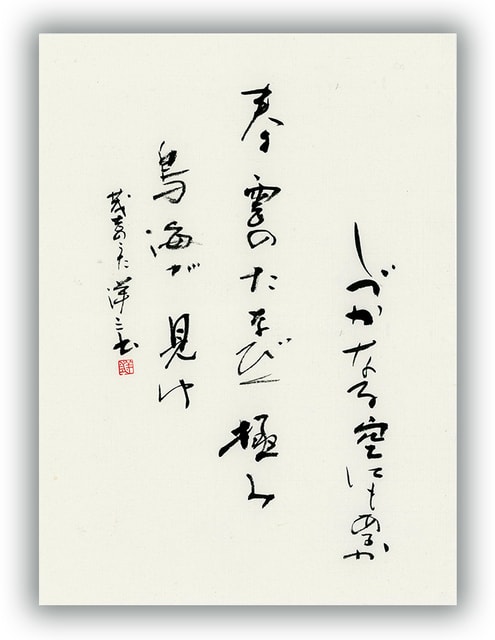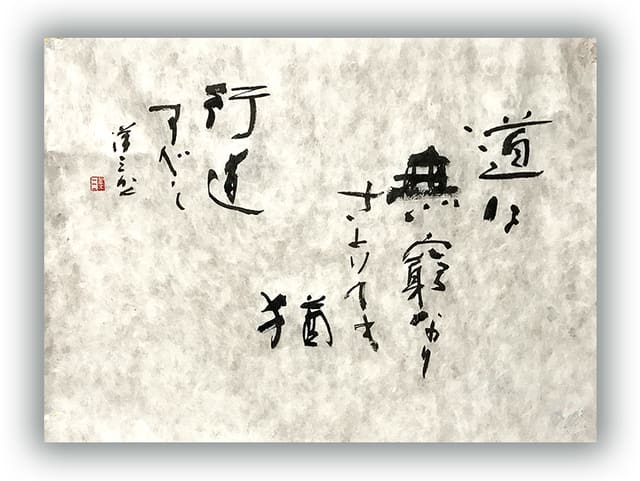日本近代文学の森へ (105) 徳田秋声『新所帯』 25 新吉の「苦悩」

2019.4.27
話はここで急展開する。お作の流産である。なんとなく予感はあったが、陰惨なことである。
二月の末──お作が流産をしたという報知(しらせ)があってからしばらく経って、新吉が見舞いに行った時には、お作はまだ蒼い顔をしていた。小鼻も目肉(めじし)も落ちて、髪もいくらか抜けていた。腰蒲団など当てて、足がまだよろつくようであった。
胎児は綺麗な男の子であったとかいうことである。少し重い物──行李を棚から卸(おろ)した時、手を伸ばしたのが悪かったか知らぬが、その中には別に重いというほどの物もなければ、棚がさほど高いというほどでもない。が何しろ身体がひ弱いところへ、今年は別して寒(かん)じが強いのと、今一つはお作が苦労性で、いろいろの取越し苦労をしたり、今の身の上を心細がったり、表町の宅(うち)のことが気にかかったり、それやこれやで、あまりに神経を使い過ぎたせいだろう……というのがいいわけのような愚痴のような母親の言い分であった。
お作は流産してから、じきに気が遠くなり、そこらが暗くなって、このまま死ぬのじゃないかと思った、その前後の心持を、母親の説明の間々へ、喙(くち)を容(い)れて話した。そうしてもう暗いところへやってしまったその子が不憫でならぬと言って泣き出した。いくら何でも自分の血を分けた子だのに、顔を見に来てくれなかったのは、私はとにかく、死んだ子が可哀そうだと怨んだ。
新吉も詳しい話を訊いてみると、何だか自分ながらおそろしいような気もした。そういう薄情なつもりではなかったが、言われて見ると自分の心はいかにも冷たかったと、つくづくそう思った。
「私(あっし)はまた、どうせ死んでるんだから、なまじい顔でも見ちゃ、かえっていい心持がしねえだろうから、見ない方が優(まし)だという考えで……それにあのころは、小野の公判があるんで、東京から是非もう一人弁護士を差し向けてほしいという、当人の希望(のぞみ)だったもんだから、お国と二人で、そっちこっち奔走していたんで……友達の義理でどうもしかたがなかったんだ。」といいわけをした。
「それならせめて初七日にでもいらして下されば……。」とお作は目に涙を一杯溜めて怨んだ。「それにあなたは、お国さんのことと言うと、家のことはうっちゃっても……。」と口の中でブツブツ言った。
新吉は、改めて自分の「冷たい心」に驚いている。自分ではそんなに薄情なつもりはなかったが、お作の詳しい事情を聞いてみると、なるほどこれはやっぱり薄情というしかないか、という新吉の「気づき」は、それでもどこか他人事だ。自分が「薄情である」ことを認識はするが、それについての「道義的」な判断がない。「薄情な自分」が「おそろしい」ような気もするが、それはそういう自分を否定する契機にはならない。新吉は何があっても「変わらない」のだ。
この氷の塊のように新吉という人間の中でどっかと腰を据えている「心」の正体はいったい何なのだろうか。それはいったいどこから来るのだろうか。「どうせ死んでるんだから、なまじい顔でも見ちゃ、かえっていい心持がしねえだろうから、見ない方が優(まし)だ」という考えは、新吉によって「薄情」だと認識されているが、そのこと自体を新吉は否定していないのが不気味だ。
これを酷薄なエゴイズムといってしまえばそれまでだけど、どこかに「時代」の空気を反映しているような気もするのだ。というのも、これとまったく同じようなセリフを、岩野泡鳴の小説の中で読んだことがあるからだ。泡鳴の場合は、流産ではなくて、幼子の死だが、やはり死んだ子どもへの哀惜の念が皆無なのだ。どうせ死んだんだ、そんなものを見てどうする、という冷たさは、この新吉や、泡鳴だけのものではなかったのではなかろうか。
当時は乳幼児死亡率が非常に高く、子どもをたくさん産んでも全部が生き延びるわけではなかった。そういう環境の中で、子どもの死は、とくに父親にとってはいちいち悲しむべきものとは思われていなかったのかもしれない。
けれども、母親にとっては大事な子どもだ。新吉の薄情さは許せるものではない。思わず新吉をなじる言葉が口をついて出る。お国のことだ。
これが新吉の耳には際立って鋭く響く。むろんお国は今でも宅へ入り浸っている。一度二度喧嘩して逐(お)い出したこともあるが、初めの時はこっちが宥(なだ)めて連れて帰り、二度目の時は、女の方から黙って帰って来た。連れて来たその晩には、京橋で一緒に天麩羅屋へ入って、飯を食って、電車で帰った。表町の角まで来ると、自分は一町ほど先へ歩いて、明るい自分の店へ別々に入った。何の意味もなかったが、ただそうしなければ気が済まぬように思った。それからのお国は、以前よりは素直であった。自分も初めて女というものの、暖かいある物につつまれているように感じた。
それから二、三日は、また仲をよく暮らすのであるが、後からじきに些細な葛藤が起きる。それでお国が出てゆくと、新吉は妙にその行く先などが気に引っかかって、一日腹立たしいような、胸苦しいような思いでいなければならぬのが、いかにも苦しかった。
ここで初めて、お国はまだ新吉の家に入り浸っていることが明らかになる。新吉は愛想をつかしたのだが、なんだかんだいって、新吉もお国を諦め切れていないのだ。そこをお作につかれて、新吉は腹を立てる。
「莫迦を言っちゃいけねえ。」新吉はわざと笑いつけた。「お国と己(おれ)とが、どうかしてるとでも思ってるんだろう。」
「いいえ、そういうわけじゃありませんけれどね、子供が死んでも来て下さらないところを見れば、あなたは私のことなんぞ、もう何とも思っていらっしゃらないんだわ。」
新吉は横を向いて黙っていた。むろんお作の流産のことを想い出すと、病気に取り着かれるようであった。彼奴(やつ)も可哀そうだ、一度は行って見てやらなければ……という気はあっても、さて踏み出して行く決心が出来なかった。明日(あす)は明日はと思いながら、つい延引(のびのび)になってしまった。頭脳(あたま)が三方四方へ褫(と)られているようで、この一月ばかりの新吉の胸の悩ましさというものは、口にも辞(ことば)にも出せぬほどであった。その苦しい思いが、何でお作に解ろう。お作はとてもそういうことを打ち明ける相手ではないと、そう決めていた。
「それで、私が帰れば、お国さんは出てしまうんですの。」お作はおずおず訊いた。
新吉は、口のうちで何やら曖昧なことを言っていた。
「義理だから、己から出て行けと言うわけにも行かないが、いずれお国にも考えがあるだろう……。それでお前はいつごろ帰って来られるね。」
「もう一週間も経てば、大概いいだろうと思うですがね……でも、お国さんがいては、私何だかいやだわ。阿母(おっか)さんもそう言うんですわ。小石川の叔母さんだけは、それならばなおのこと、速く癒(なお)って帰らなければいけないと言うんですけれど……。」
新吉は、二人の間(なか)が、もうそういう危機に迫っているのかと、胸がはらはらするようであった。
「どちらにしても、お前が速く癒ってくれなければ……。」と気休めを言っていたが、そうテキパキ事情の決まるのが、何だかいやなような気がした。
いくら冷たい心の新吉とはいえ、やはり流産のことはこたえていたのだ。並々ならぬ苦悩を味わったけれど、その苦悩をお作に話す気にはなれなかった。「お作はとてもそういうことを打ち明ける相手ではないと、そう決めていた。」とあるわけだが、なぜ「そう決めていた」ということになるのだろうか。流産をしたお作を哀れにも思い、見舞いに行こうと思いつつ、それでも足を運べなかったのはなぜなのか。ああでもないこうでもないと新吉はなにを一月も苦しい思いをしたのか。その辺がどうも判然としない。
お作は自分の苦悩を打ち明ける相手ではない、と決めたというのは、お作を妻として扱っていないということになる。苦しみを分かち合う相手でないとしたら、それは妻とはいえないだろう。結局のところ、新吉は、お作との結婚に満足していないばかりか、後悔しているのだ。流産のことを考えると、病気になりそうなくらい苦しいけれど、お作は自分の何倍も苦しいだろうということに思い至らない。苦しんでいるのは自分ばかりではなくて、お作こそ苦悩の真ん中にいて、その苦悩をこそ二人は分かち合わなければならないはずなのに、新吉の思いは「自分の苦悩」にだけ向いている。そして、お作は、そんな苦悩を理解できる人間ではないと、新吉は見くびっているのだ。
お作は苦しんでいる。だから可愛そうだ。だが、オレはお作より、もっと高度な苦悩を抱えている、そう思っているのかもしれない。そしてその「苦悩」を理解してくれるのは、もっと頭のいい別の女だと考えているのかもしれない。それがお国かどうかは別にしてもだ。
お作が元気を取り戻して家に戻ってくることを、新吉は恐れている。それはお国との別れを決定的なものにするだろうからだ。かといって、お作と離縁して、お国と一緒になる決心もついていない。「テキパキ事情の決まるのが、何だかいやなような気がした。」という表現は、そんな中途半端な新吉の気分をよく表している。