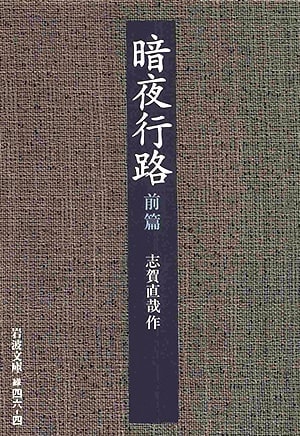日本近代文学の森へ (145) 志賀直哉『暗夜行路』 32 リアルな現実 「前篇第一 八」 その1
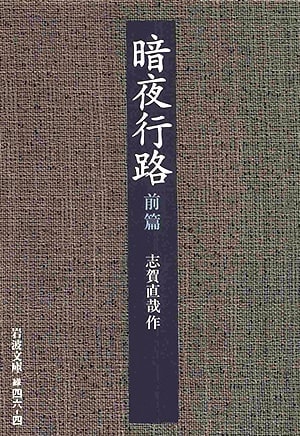
2020.2.23
暫く上方の旅をしていた宮本という謙作よりは年下の友達が、松茸の籠を下げて訪ねて来た。
謙作が家でこの宮本と話をしているとき、清賓亭から電話がきて、お加代がこっちへこないかと誘ってきた。聞けば、緒方もいるらしい。謙作は、緒方と一緒に家にこないか、こっちには松茸があるからというのだが、加代子はめんどくさがって承知しない。それで、謙作は、宮本と一緒に清賓亭に出かけていく。
清賓亭では、緒方がお鈴とお加代相手にウイスキーを飲んでいた。
急に緒方が言った。
「オイ、君々」と緒方はお鈴の膝を叩いて、「橋善の天ぷらで日本酒を飲もう」といった。
「天ぶらは見るのも苦労らしいな」と内気らしく宮本がいった。
「いやかい? そんならよそう」
「本統にそうですよ。陽気の変り目ですから、もしもの事があるといけませんからね」
「この人のいう事は何だか、お婆さん染みてるよ」そうお加代は傍白のようにいった。
宮本の「天ぶらは見るのも苦労らしいな」というセリフの意味が分からないが、緒方が「いやかい?」って即座に聞き返すので、どうも、「見るのも嫌だ」ぐらいの意味なのだろう。それに対してお鈴が、陽気の変わり目だからもしものことがあるといけないと言うのをみると、天ぷらで食中毒を起こすことが結構あったようだ。今ではあまり聞かないが、それでもそれなりにあるようだ。
お鈴が、そういう心配をするのを、お加代は「お婆さん染みてる」と評するところがおもしろい。
ここに出て来る「橋善」は、新橋にあった天ぷら屋で、創業1831(天保2)年の老舗だったが、2002年に休業しているとのこと。ちょっと残念。行ってみたかったのに。
若い頃はちっともそんなことはなかったのだが、最近は、小説に出て来る場所に行ってみたいと思うようになった。なぜだか分からない。田山花袋の「田舎教師」を読んでいたころには、舞台になっている羽生あたりを小旅行する計画まで立てた。いまだ実現していないけれど、いつか、行こうと思っている。
小説に、地名やら、店名やらが出て来ると、そこに行ってみたいと思うのは、やはり、それらの土地や建物の実在性が、小説にとって非常に大事だと思うようになったからだろう。土地や建物がそこにかつてあって、そこに登場人物が行った、つまりは、作者がそういうふうに創作したということが、その必然性が、果たしてあるのかということ。単に思いついたとか、本で読んだとかいうことではなくて、作者の実際の経験があって、そうした土地や建物を描いたということが大事だと思える。
最近ではすぐにAIのことが頭に浮かぶが、例えば、AIが書いた小説には、果たしてその土地や建物(お店、そこで食べた食事なども含むわけだが)にまつわるリアルな記憶がある種の必然性をもって描き込まれる、ということが可能だろうか。
さて、緒方は例によってベロベロだが、連れてきた宮本も酒が強い。
宮本も酒は強かった。そしてペッパーミントのような甘い酒を一緒に飲みながら少しも酔わなかった。そして変に沈んだ顔をしていた。前夜の夜汽車でよく眠れず、宮本は元気がなかった。
「どうしたのよ」謙作と並んでいたお加代は、向い合った宮本の俯向き顔を覗込み、
「いやあね。さっきから一人で悲観ばかりして……」そしてお加代は謙作を顧みた。「全体どうしたの?」
そういってお加代が身を起した時、何気なくお加代の椅子に手をかけていた謙作の指が背中で挟まれた。
「寝不足なんだ」こう答えながら、謙作は指を静かにぬこうとした。
「イキな寝不足じゃ、ないの?」お加代はかえって謙作に誘惑的な眼つきを向けながら、心持、背中に力を入れた。
「イキなもんか。夜汽車の寝不足だ」謙作は不愛想にいって、ぐいと指を抜いてしまった。その時彼はお加代が不快な顔をするかと思った。が、お加代は如何にも無関心らしくしていた。
謙作には女からそういう遣方(やりかた)で交渉される事は余り気持よくなかった。それで不愛想に指を引き抜いてしまったが、やはり一方ではそれを後悔していた。こんな事に変な潔癖を見せつけたような自分も気に食わなかったし、―つの機会を見す見すに逃した事も惜しかった。皆が酔っている中で自分だけが酔わずにいるからだと思った。そして気まぐれな心持で、
「その酒をくれないか」と一度断ったペッパーミントを注がして、それを一卜息に飲んだ。
もともとお加代に惹かれていた謙作は、ズルズルとお加代と親密になっていく。指が挟まれたとか、抜いたとか、細かい動作が精密に描かれ、その都度の自分の心境も書かれている。どうでもよい情事の断片だが、これだけ精密だと、心を惹かれる。
「隅に置けないわ」
酔うに従ってお加代の眼はまた美しくなった。脣(くちびる)も美しい色になった。そして動作が段々に荒っぽくなって行った。
のりの利いた厚いテーブル・クロースに緑色の酒がこぼれたのが白熱瓦斯の下で一層美しく見えた。
「まあ綺麗だこと、──」こういってお鈴がそれへ顔を寄せると、
「もっと作って上げよう。ねえ?」お加代はぞんざいにこういいながら、小さい塩の匙を取って、やたらにその酒を撒散(まきちら)した。
「またそんな乱暴をする」
「綺麗だって讃めたからさあ」とお加代はお鈴をにらみ返した。
「全く綺麗だ」と謙作がいった。
お加代は直ぐ謙作の方を振り向いた。そして、
「ねぇ──」と顔と顔をつける位までに近づけて首肯(うなず)くような事をした。謙作は今度は故意に、それに応じて、同じように首肯いて見せたが、それが自分ながらちょっと調子がはずれていた。気が差していると、今まで黙っていた宮本が、
「仲のええ事」と京都訛りを真似て冷やかした。識作には妙に皮肉に響いた。彼はそれに抵抗しようとした。するとなお調子がはずれて来た。彼は 椅子をずらし、お加代の方へ身を寄せながら、
「僕は君が好きなんだ」といってしまった。
酒の酔いの中で、謙作の自制心はとうとう崩れる。崩れるのだが、どこか醒めている部分もあって、描写自体の崩れはない。あくまで、精密に行動と心理を追っている。
他愛ない情事のただ中に、「のりの利いた厚いテーブル・クロースに緑色の酒がこぼれたのが白熱瓦斯の下で一層美しく見えた。」の一文が、どこか硬質の輝きをたたえているようで、美しい。
「ありがとう」お加代は謙作の不意な変りようにちょっとまごつきながら、それでも今の荒々しい様子とは、全く思いがけない可愛らしい顔つきをした。
「どうしよう?」謙作の方は大胆になって、肩でお加代の肩を押した。
「どうかしましょうよう」とお加代は甘ったれた声をした。その時は何時かお加代も自身を取返していた。そして、首を傾け、謙作の胸へ顔をつけてそのまま、凝っとしてしまった。髪の毛が謙作の頬に触れていた。
「こりゃあ、たまらない」お鈴は大きな声で笑い出した。
謙作はお加代の首へ腕を巻いて、顔を寄せて接吻する真似をした。二人は蟀谷(こめかみ)と額とを合していた。しかし脣と脣とは三、四寸離れていた。そしてただ凝っとしていると、酔った皮膚からの温かみが顔と顔の間に立迷っているのが感じられた。謙作は意識の鈍るような快感を感じた。
ふと、その辺が急に静かになったので、彼は顔を挙げた。皆は何時か入口の厚いカーテンを下ろして何処かへ行ってしまった。お加代も少し汗ばんだ顔を挙げた。二人は不意に変に覚めた気持に突きもどされた。笑談(じょうだん)一ついえない気持だった。
「きっと隣りよ」
「行って見よう」
二人は直ぐその部屋を出た。隣りへ入って見たが、誰もいなかった。
自制心は崩れたとはいうものの、ここまでだ。「三、四寸離れていた」脣は、触れ合うことがない。そして、「酔った皮膚からの温かみが顔と顔の間に立迷っているのが感じられた」というのだから驚くほかはない。
考えようによっては、何をばかなことをだらだたやってるんだ。さっさと脣を重ねればいいじゃないか、ということにもなるのだろうが、そんなことを言ってもしょうがない。謙作はこういう男だったし、お加代もまたこういう女だった。回りでとやかくいってもはじまらない。
そういうそれぞれに、独特な感性と生き方みたいなのがあって、それがこうしたいわば「商売女」と「客」の間にも厳然としてあって、それが接触するとき、こういう事態にたまたまなった。たまたまだけれど、それはそれで、真実である。
真実というよりは、「リアルな現実」である、といったほうがいいだろうか。「リアルな現実」というのは、実に多様で、それこそ人の数だけある。その「リアルな現実」が小説に描かれるとき、やっぱり、小説はおもしろい、と思えるのだ。