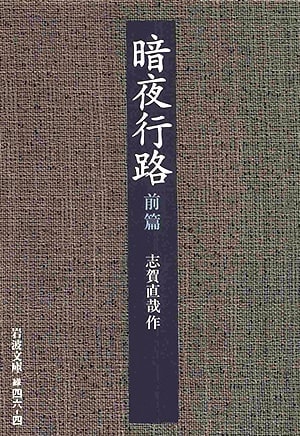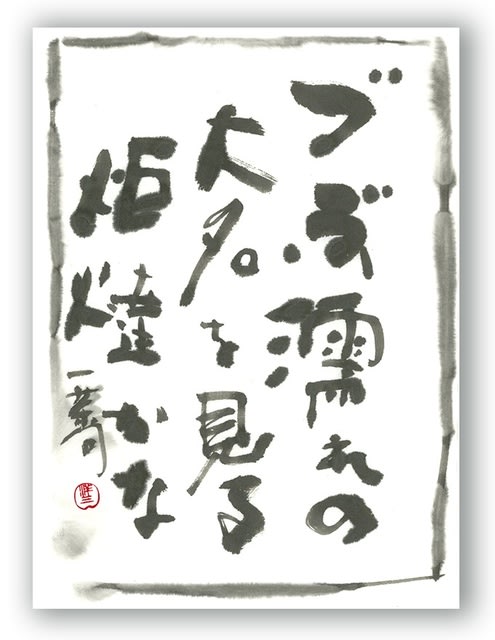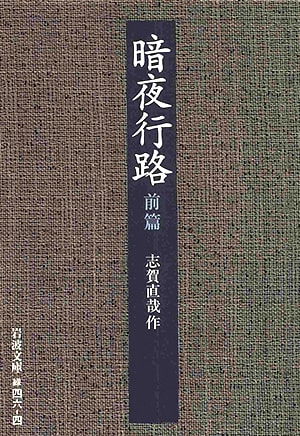日本近代文学の森へ (138) 志賀直哉『暗夜行路』 25 放蕩と自然 「前篇第一 六」
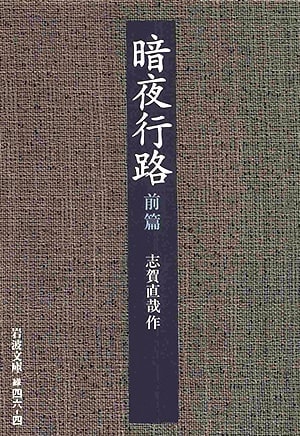
2019.12.15
「前篇第一の六」は、「謙作が二度目に登喜子と会ってから二、三日しての事」として、夜遊びの様が描かれる。これが、時間と場所を明示しながら、実に簡潔に、しかもリアルに書かれていて、読んでいて気持ちがいい。
結局二晩家を空けることになるのだが、その三日間の「足取り」をまとめてみたい。
「その日」は、一四、五年前に死んだ親しい友の命日で、謙作はそのころ親しかった友人たちと染井に墓参に出かけた。
墓参を済ませて、巣鴨の停車場へ来たのは日暮れどきだった。この巣鴨の停車場というのは、今でいう山手線の停車場だろう。
墓参を済まして巣鴨の停車場へ帰って来たのはもう日暮れだった。彼らはそれから賑かな処へ出て、一緒に食事をするはずだったが、この電車で上野の方へ廻るか、市内電車で直ぐ銀座の方へ出てしまうかで、説が二つに分れた。謙作は何という事なしに、上野の方へ出たい気がしていた。上野から登喜子のいる方へ行くというほどの気はなかったが、ただ何となく、その方へ心が惹かれるのだ。
登喜子のいるのは吉原だから、上野から近いわけだ。この当時は、巣鴨から「山手線」で上野に行くか、「市内電車」つまりは都電で、銀座へ出るかの選択肢があったわけだ。今だとバスか地下鉄だろうか。
結局、銀座に出ることになったのだが、「近頃フラン人が開いた西洋料理屋」に行くか、「うまい肉屋」に行くかで意見が分かれ、お互いにワガママ言って譲り合わなかった。金持ちの坊ちゃんたちのワガママなのである。
西洋料理屋は分かるが、「肉屋」って何だろう。すき焼き専門店だろうか。
で、結局別々に行くことになって、食事の後のお茶だけを、肉屋に行った連中が西洋料理屋に来て一緒にすることになった。どうも、悠長な話である。時間も金も余裕があるということかしら。今なら絶対にどこかで妥協するし、妥協しなかったら、お茶だけ後で一緒になんてこともしないだろう。
その西洋料理屋を出たのが、午後の九時頃。謙作は、一緒に西洋料理屋に行った緒方という男を誘って登喜子の所に行こうとするが、緒方は、今夜は兄や姉が来ているので家を空けるのはまずいと言う。しかし、どうしても登喜子に会いに行きたい謙作は、例によって一人では行けなくて、緒方を誘う。緒方は酒の誘惑にまけて、謙作についてくる。
途中の「カッフェ」から電話をすると、登喜子はまだ帰っていないという。その辺のやりとり。
とにかく、電話をかける事にして、二人は或るカッフェに入った。
電話に出たのはお蔦だった。
「登喜ちゃんは今日は市村座で、小稲さんは昨日から遠出で、まだ帰って来ないんです」と気の毒そうにいった。
「しかし《はね》たら帰って来るだろう」
「さあ、帰るだろうとは思いますが、今訊いて見ましょう。そちらは何番ですか? 伺っておいて、直ぐ御返事致します」
そして暫く待っていると電話が掛って来た。
「芝居を見残して、お客様と蔵多屋へ行ってるんですって。今御飯を頂いているから、もう直きお暇が出そうだというんですけど……」
「それなら行こう」そう謙作はいった。
芸者をつれて、芝居を見て、それから食事をする男が、当時もゴロゴロいたわけで、なんだか羨ましい。
行くと決まったらもっと飲むと緒方は言って、そのカッフェで酒をがぶがぶ飲む。
それから一時間ほどして、二人は「西緑」(登喜子のいる待合)に行った。しばらくして登喜子も来たけれど、登喜子も疲れているとみえて、「その夜も子供らしい遊びでとうとう夜明しになった」。このまま泊めてくれというのもどうなんだろうなんて思っているうちに、二人はうとうとしてしまい、結局目が覚めたのは翌朝十時ごろ。
戸外(そと)には秋らしい静かな雨が降っていた。その音を聴きながら二人がうとうとしている間に女たちは帰って行った。
十時頃眼を覚まして、二人は湯に入ると、いくらか気分がはっきりした。また前夜の二人をいったが、小稲だけ来て、登喜子は同じ家の表二階の客の方へ行く事になっていた。
緒方は少し醒めかけると飲んだ。もう遊び事も話もなかった。小稲はそのだらけて行く座をもち兼ねて、ただぼんやりと淋しい眼つきをして、其処に仰向けに、長くなっている緒方の顔を凝っと眺めていた。
やっぱりこの連中は、金も時間も持て余すほどあるんだよなあ。こんなにダラダラした時間の使い方、しかも金のかかる使い方は、そうそうできるもんじゃない。
この後、緒方は「何か面白い話はないか」と小稲にいい、小稲も「下谷の芸者衆が白狐に自動車の後押をされた」とかいう嘘かほんとか分からない話をしたりするが、どうにも盛り上がらないで時間が過ぎていく。そのうち、緒方はイビキをかいて寝てしまう。謙作は所在なさに、小稲と五目並べなんかしていると、むこう座敷から登喜子の声が聞こえてくる。
時々彼方(むこう)の座敷から登喜子の声が聴こえて来た。謙作は今はもう登喜子との関係に何のイリュージョンも作ってはいなかった。しかしそれでも此処に登喜子がいない事、そして彼方の部屋で誰れかと話しているという事は変に淋しく感ぜられた。いないならばまだいい。彼方にいるという事、それはどうしても彼の意識を離れなかった。で、実際にも登喜子は謙作らの座敷の前を通る時には必ず何か声をかけた。中へ入って来る事もあった。すると謙作の気分は、自分でも不思議な位に生々した。
登喜子の客はなかなか帰らず、謙作と緒方は、吉原をあとにして、またまた西洋料理屋に入って緒方はウイスキーを飲む。謙作はもう飲めない。二人は三の輪まで歩いて、其処から人形町行の電車に乗った。
その電車の中で、赤ん坊を連れた女に出会う。この描写がとても生き生きとしていて見事だ。長いが引いておこう。
車坂の乗換に来た。乗る人も降りる人も多かった。眉毛を落した若い美しい女の人が、当歳位の赤児を抱いて入って来た。その後ろから十六、七のおとなしそうな女中が風呂敷包を抱えてついて来た。二人は謙作の前の丁度空いた処へ腰かけた。
よく肥った元気な赤児だった。綺麗な友禅の着物にやはり美しいチャンチャン児(こ)を着ていた。しかし身体が小さいので着物がよく着(つ)かぬかして、だらしなくそれがぬき衣紋になって、其処から丸々と盛り上った柔らかそうな背中の肉が白く見えていた。赤児は頭(かぶり)を振り、手足を頻(しき)りに動かして、一人元気に騒いでいた。女の人は二十二、三だったかも知れない。しかし細君になった人を見ると誰でも自分より年上のような気のする謙作には《はっきり》した見当はつかなかった。その人は友達と話すような気軽さと親しさで女中と何か話していた。
すると、女中の向こうに、女におぶさった四歳ぐらいの女の子が、赤ん坊をじっと見ている。赤ん坊はその女の子の方に手を伸ばして、からだをもがいている。
余り赤児が《もがく》ので、話に気を奪られていた女の人も、漸く気がついた。そして至極軽快な首の動作で、女の児の方を振向いた。それは生々とした視線だった。
「おや、この人はお嬢さんのとこへ行って話し込みたいんだネ」といって女の人は笑った。女の児は平気で《むっつり》としていた。おぶっている女中が何か鈍い調子でお愛想をいった。
女の人は連れの女中との話をそのまま、打切って、今度は急に──むしろ発作的に赤児の頬だの、首筋だのへ、ぶぶぶと口でお灸(とも少し異うが)日本流の接吻を無闇にした。赤児はくすぐったそうに身もだえをして笑った。女の人は美しい襟足を見せ、丸髷を傾けて、なおしつっこく咽(のど)の辺りにもそれをした。見ていた謙作は甘ったるいような変な気がして、今は真正面(まとも)にそれを見ていられなくなった。彼は何気なく首を廻らして窓外を眺めた。そしてこの女の人はまだ甘ったれ方を知らぬ赤児よりも遥かに上手に甘ったれていると思った。
若い父と、母との甘ったるい関係が、無意識に赤児対手に再現されているのだと思うと、謙作は妙に羞かしくもなり、同時に余りいい気持もしなかった。しかし、精神にも筋肉にも《たるみ》のない、そして、何となく軽快な感じのするこの女の人を謙作は美しく感じた。彼は恐る恐る自分の細君としてこういう人の来る場合を想像して見た。それは非常な幸福に違いなかった。一時は他(た)に何物も欲求しないほどの幸福を感じそうな気さえした。
「さあ、今度おんりするのよ。君やにおんぶしてエッチャエッチャって行くのよ」美しい細君は赤児を女中におぶせながらこんな事をいった。そして電車の停るのを待って降りて行った。
謙作は何という事なし、幸福を感じていた。この幸福感はその人の印象と共に後まで、彼の心で尾をひいていた。
二人は小伝馬町で降りると、人道を日本橋の方へ歩いて行った。雨に濡れた往来が街の灯りを美しく照りかえしていた。日本橋の仮橋を渡って暫くいった横丁の或る小綺麗な料理屋へ二人は行った。
放蕩の合間に、まるで晴れ間のように描かれるこの「幸福」の何としみじみと身にしみてくることか。
芸者たちのもつ「けだるさ」とは対照的に、この母親は、「生き生きとした視線」、「筋肉にも精神にもたるみのない軽快さ」で、印象的だ。
この後、二人は、電車を小伝馬町で降りて、日本橋の「小綺麗な料理屋」で9時ごろまで酒を飲み、銀座をぶらつき、緒方の馴染みの「清賓亭」へ行って、そこの女たちを相手にまたさんざん酒を飲み、夜中の十二時ごろに「西緑」に行く。
その夜十二時近くなって、二人はまた西緑へ行った。惰性的になかなか別れられなかった。夜が更けるとかえって一時の疲れた気分もはっきりして来たが、それも長もちはしなかった。三時頃いよいよ参ると、謙作はもう自分の寝床が無闇と恋しくなった。それで思う様の眠りに落ち込みたかった。彼は緒方に翌日帰途に必ず来てもらう約束をして、一人褞袍(どてら)を借りて俥で帰って来た。
途中で夜が明けて来た。雨後の美しい曙光が東から段々に湧き上がって来るのを見ると、十年ほど前の秋、一人旅で日本海を船で通った時、もう薄く雪の降りている剣山の後ろから非常な美しい曙光の昇るのを見た、その時の事を彼は憶い出した。
この最後の段落の自然描写も美しい。放蕩の果ての自然の美。それがなんども繰り返されている。
電車の中の女の美しさも、また自然の美なのではなかろうか。