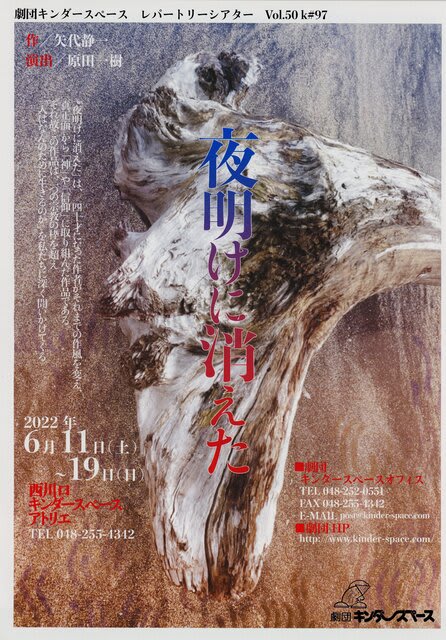木洩れ日抄 88 写真とは何か? ──「東慶寺境内における撮影禁止」を巡って

2022.6.27
北鎌倉にある東慶寺が、数年前に、「一眼レフカメラ」での撮影を禁止するとのお触れをだした。いつものように、重いカメラを抱えて嬉々として東慶寺門前に着いたとたん、その御触書を見て、愕然とした。そして、悄然として門前を去った。
そこには、「当分の間」とはあったので、いずれ事態が改善したら、禁止も解けるかなあと思っていたのだが、今年になって、それが更に「悪化」して、全面的に撮影禁止となったことが、ホームページに掲載された。
そのお触れをいちおうここに掲載しておきたい。
境内における撮影禁止について 2022年06月07日
カメラ、スマートフォンを問わず、境内における、一般参拝者の撮影行為はご遠慮ください。
携帯電話とスマートフォンが普及して以降、写真や動画の撮影がとても身近なものになり、我々の生活は大変便利になりました。
一眼レフカメラも求めやすくなり、本格的な撮影に臨まれる参拝者も増えました。
そんな中には、お寺であることを忘れ、本堂をお参りしない方も多く、足元に咲いている花や苔を踏みつけ、進入禁止の場所に入り込んだり、勝手に物を動かしたり、見境がない人も出始めました。
なにより残念なことは、特に考えもなく、とりあえず撮影してしまう癖がつき、目の前のことに対して、「心」で感じるのを忘れてしまったことです。
東慶寺では2年前より、境内環境の向上を目指し、水脈などの改善活動「大地の再生」に取り組み始めました。その成果は如実に表れており、植物の表情はもちろんのこと、境内の空気が明らかに変わり、参拝者や寺に住む我々の心までも穏やかにさせてくれます。
神社仏閣の境内が美しく、豊かであるべきなのはこの為なのだとはっきり分かったのでした。
参拝者の皆様にも、この空気の変化を肌で感じ、ご自身の心のあり方を大切にしていただきたいのです。
心を育むのも寺の重要な役目と思い、決断いたしました。
何卒ご理解いただきたく、お願い申し上げます。
東慶寺住職
最初のお触れでは、「一眼レフカメラ」での撮影禁止だったので、じゃあ、ミラーレスならいいのか、じゃあ、スマホならいいのか、というような問い合わせが「殺到」したのではなかろうか。ぼくだって、そのくらいのイチャモンはつけたくなったから。それで、いろいろ検討した結果、今回のような決定に至ったということのようだ。
境内での撮影禁止ということ自体は、ぼくが何か文句をいう筋合いのことではない。たしか、極楽寺などはずっと前からそうだし、寿福寺などは境内にすら入れてくれない。だから、それはどうでもいいのだ。
どうでもいいとはいっても、東慶寺は、もう十数年も前から、ぼくの大事な撮影スポットだったから、残念でしょうがないということはある。あるけれども、だから、どうしろというわけでもない。
このお知らせを読んで、ずっと心の中にわだかまっていた思いは、「ああ、またか。」という一種の嘆きだった。それは、「なにより残念なことは、特に考えもなく、とりあえず撮影してしまう癖がつき、目の前のことに対して、「心」で感じるのを忘れてしまったことです。」という一節にある。
これはいったい誰に向けて発せられた言葉なのだろうか。「特に考えもなく、とりあえず撮影してしまう癖」がついたのは誰なのか? 「目の前のことに対して、『心』で感じるのを忘れてしまった」のは誰だというのだろうか?
文脈からいえば、東慶寺にやってきて、写真を撮る人すべて、がその「主語」ととれる。べつの言い方をすれば、「あなたたちは」ということになるだろう。そしてその後の文面を総合すれば、
あなたたちは、特に考えもなく、とりあえず撮影してしまう癖がつき、目の前のことに対して、「心」で感じるのを忘れてしまったのです。どうぞ、ご自身の心のあり方を大切にしていただきたい。私どもは、あなたたちの心を育むのも寺の重要な役目と考えております。
ということになる。
お寺というものが、人々を教え導く使命を持っていることを疑うものではない。その使命感が強いからこそ、こうしたものいいとなるのもうなずける。
しかしだ。写真を撮っている者が、「目の前のことに対して、『心』で感じるのを忘れてしまっている」と、どうして断定できるのだろうか。あまりに勝手な断定ではないのか。その勝手な断定のうえに、「あなたたちの心を育んでやりたい」と言う。「お寺だから」といって済ますには、あまりに尊大な態度ではあるまいか。
そもそも「目の前のことに対して『心』で感じる」とは、いったいどういうことなのだろうか。それは、今自分が生きているこの時間と場所を、全身で感じ取るということだろう。お寺の境内にいれば、花も木も本堂の屋根も目に入るだろうが、そうした「目にはいる」ものだけではない。小鳥のさえずりや、人々の話し声や足音、さらには鐘の音や、読経の声さえ聞こえてくるかもしれない。音だけじゃない。空気の冷たさとか、風のながれとか、線香の香りとか、そういった触覚、嗅覚にも訴えてくるものも多かろう。それらを、全身で、全感覚で受け止め、今という時間を十分に味わい、生きて欲しい、ということだろうと思う。それにまったく異論はないし、むしろ大賛成だ。
ただ、そのことが、「カメラで写す」と、できなくなってしまったり、忘れたりしてしまったりする、というのは、直接の関係がないことだ。
せっかく東慶寺まで足を運んだのに、その境内にいることを全身で味わおうともせずに、「いちおう撮っておいたから、後で写真を見ればいいや」と考えて、さっさと帰っていく人がそんなにたくさんいるものだろうか。ほとんどの人が、十分に東慶寺の境内に流れる時間を感じ取り、見たいものを見て、あとはその記念にスマホで写真をとっておく、というのが普通ではなかろうか。
だから、問題はやはり、「一眼レフ」なのだ。一眼レフカメラ(含む、ミラーレス一眼カメラ)で写真を撮る人というのは、「写真を撮る」ことが目的で東慶寺に行くわけだから、ごくまれに「肉眼じゃ見ない」という人もいるかもしれない。肉眼で見る人でも、写真に撮るものや場所を探す目的で見るので、「全身で感じ取る」ヒマはないかもしれない。
しかし、「一眼レフ」カメラで撮る人が全員そうだというわけじゃない。写真を撮る人は、「見ない」人じゃない。むしろ、「よりよく見る」あるいは「よりよく見よう」とする人である。「とりあえず撮っておけばいい」という人が、わざわざ重いカメラを担いで東慶寺くんだりまで出向くわけがないではないか。
東慶寺で、1枚の写真を撮るということは、東慶寺という場所のすべてを感じ取って、それを1枚の写真に集約しようとすることだ。その写真に、東慶寺の空気を取り込もうとすることだ。だから、とことん「見る」、そして「感じる」。音も、風のすずしさも、匂いも、なにも写真には写らないと思ったら大間違いだ。写真は「見える」ものだけを写すのではない。「見えない」ものも写すものだ。
だからこそ、しつこくいつまでも撮り続ける。その人の姿が、偏執的に見え、オタクっぽく見えるのも致し方のないことなのだ。そして、時として、そういう意味での「いい写真」を撮ろうと熱中するあまり、「足元に咲いている花や苔を踏みつけ、進入禁止の場所に入り込んだり、勝手に物を動かしたり、見境がない人も出始め」るという言語道断な仕儀に至るわけである。
そういうとんでもないヤツに腹を立てるご住職の気持ちはよく分かる。そんなやつは、ホウキを持って追い出してもいい。
ただ、そのことと、「特に考えもなく、とりあえず撮影してしまう癖がつき、目の前のことに対して、「心」で感じるのを忘れてしまった」こととは、区別して考えてもらわないと困るのだ。
カメラが発明されたときから、おそらく、人々の間に根付いた偏見は、「写真というのは、人間の目で見ないで、機械の目で見た映像にすぎない。」ということだろう。最初のほうに、ぼくが「ああ、またか。」と思ったと書いたのは、その偏見がぜんぜんなくならず、依然としてある種の「説得力」をもってまかり通っているという現実への失望と怒りがあるからだ。
写真に興味のない人は、写真というのは実に「安直」なものである、と思い込んでいる。とにかく、カメラのシャッターを押せば誰でも撮れる、という安直さ。その昔「写るんです」というカメラがあったり、誰でも簡単に撮れるからというので、ヒドイ差別語の名称で呼ばれたカメラもある。そういう人たちは、写真を撮るということがなかなか難しいと思っていたのに、それが簡単に撮れるカメラが出てきたということへの一種の驚きからそういうネーミングをしたり、安直なものだと思い込んだりしたわけだ。そして、そのことで、「写真=安直」という図式がひろく行き渡ったのだ。
しかし、それはもう何十年も前の話だ。それから時代は大きく変わった。写真というものも、その意味とか役割が激変した。「誰でも撮れる」という方向は、スマホのカメラによってそれこそ「写るんです」の比ではなくなった。そしてそれ以上に、写真の概念を根本から変えたのは「共有」という概念である。
写した写真を、瞬時に友達におくり、「共有」する。あるいは、インスタグラムに投稿することで、それこそ世界中の人に瞬時に発信できる。写真は、「とりあえず撮って、後から自分が見る」ものじゃなくなったのだ。
たとえば、寝たきりになって、どこへも出かけられなくなった母親が、東慶寺を懐かしんで、梅を見たいと言う。親孝行な娘が、それならかわりに私が行ってきてあげるわ。梅の写真を送るから、見てね、といって、スマホを持ってでかける、といったシーンはごく当たり前のことになっているだろう。
「インスタ映え」などという言葉が大流行し、それもすでに廃れ、単に「映える」というヘンテコな言葉になっているけど、写真は、今までのカメラではできなかった分野を開拓して、コミュニケーションの大事なツールとなっているのだ。
その一方で、「一眼レフ」のほうはどうかというと、実際には、一部のマニアのものとなっている。もちろん、メーカーとしても、「スマホじゃ撮れない画質」を宣伝して、なんとか、カメラに誘導しようと懸命だが、もはや昔の市場規模を回復することはできないだろう。東慶寺のご住職は、「一眼レフカメラも求めやすくなり、本格的な撮影に臨まれる参拝者も増えました。」と言われるが、「一眼レフ」は決して「求めやすく」なっているわけではない。デジタルになってから、「一眼レフカメラ」や「ミラーレス一眼カメラ」は、むしろ高価なものとなっている。しかも、それらは、カメラを買っておしまいとはならず、多くのレンズを揃えることにこそ意味があるわけだから、ますます一般の人は手がでない。そのうえ、スマホの画質が、ともすれば、半端な一眼レフを超えかねないという昨今では、よほどレンズにこだわる人じゃないと買う気になれない。というか、買えない。
では、なぜ、東慶寺のご住職は「一眼レフカメラを持った人が増えた」と感じるのか。それは、主に、退職して金に余裕ができた高齢者が買うからである。その高齢者の中心にいるのがいわゆる団塊の世代であって、数がやたら多い。そういう層は、退職金もたんまりもらっている人も多いから、何百万という金をカメラやレンズにつぎ込むことができるのだ。そして、そういう人たちというのは、会社でエライ人だったりするから、超我儘で、人の言うことを聞かない。見栄っ張りも多いから、カメラ雑誌に投稿して入賞しようなんて思ったりする。そのためには、先生から教わった「構図」のためなら、どこへでも入ってしまう。苔を踏みつけても、そんなものはいくらでも生えてくるものだと勘違いしたりする。これで、言語道断な連中がメデタク誕生するわけで、そういう連中が、東慶寺のご住職を怒らせるということとなるわけである。
かく言うぼくも、その団塊の世代の一翼を担う者で、薄給の教職に長くあったために、金は湯水のようにはとてもじゃないけど使えないが、それでも、カメラやレンズに、普通の人よりは多額の金を使うマニアの一員でもあることを認めるにやぶさかではない。その証拠に、数年前、海蔵寺で、リンドウの花を撮るのに夢中になって、庭と道との境を示す縄の数センチ内側に靴のつま先を侵入させたところを、ご住職ではない、ジイサンに、「おい、そこ、入っちゃだめだよ!」と冷たく叱責された「実績」がある。そのジイサンは、ずっとぼくの行動を監視し続け、ついに、「違反」を見つけて、ここぞとばかりに注意喚起を決行したのであろう。そこには、「なんだ、こいつ、いい歳しやがって!」という冷たさしか感じなかった。もちろん、ぼくは、丁重に謝ったけれど。
こんなことをずらずら書き連ねていても、だんだん愚痴になっていくので、そろそろやめるが、言いたいことはただ一つ。写真撮るのも楽じゃないということだ。そして、多くの写真を愛する者は、さまざまな思いで、撮影している。決して「とりあえず撮って、後で見ればいいや」と思って、その瞬間を疎かにしている人ばかりではない、いや、むしろそういう人は少ないはずだ、ということだ。
東慶寺のご住職には、できればその辺を分かってほしいものだ。撮影禁止そのものは、異論はないし、そういう連中が跋扈するなら、むしろ当然と受け止めているが、その「理由」に、少々問題を感じたというまでである。