「春は鉄までが匂った。」
英文を読むのに疲れると、近所の図書館で借りた松尾宗次さんの『いろいろな鉄』というエッセイ集を読んでいます。文系理系をまたがって、鉄にまつわる古今東西の話がつづられています。そのなかに「香りと鉄」という章があって、そこに冒頭の言葉が載せられていました。町工場で旋盤工をしながら小説を書き、芥川賞と直木賞に複数回ノミネートされた作家小関智弘さんの小説『錆色の町』の結びの言葉だといいます。「かなけ(金気・鉄気)くさい」と広辞苑にも載っているくらい鉄にも匂いはあるそうですが、当時の文芸評論家は「鉄が匂うはずはない、思い込みの過ぎた表現である」と批評したんだそうです。ここまで読んで、僕はふと、自分が生まれた新潟県与板町のことを思い出しました。戦国時代は上杉家の知将直江兼継の城下町として、江戸時代には鍛治町として栄えたこの町は、僕が小さい頃はまだ、金物屋の作業場から火花が散るのを眺めることができるような町でした。豪雪地帯でもあるため、道路にはくまなく消雪パイプが埋め込まれていて、冬の降雪時にはそこからチロチロと地下水が噴き出します。夜遅くに新幹線で長岡駅に着いて、迎えに来てくれた祖父と一緒にタクシーに乗り、運転手と祖父の会話を聞きながら走るときに、前方の道路に降る雪の向こうにひざ下くらいまで吹き上がる水柱をじっと眺めていたことを思い出したのでした。「こんげな日は道路の上の水も凍るすけ、かえって危ねがて…」(新潟弁、間違ってるかも)

消雪パイプ: photo from wikipedia
与板の道は、そんな消雪パイプから出てきた錆の色でオレンジ色をしています。道路に引かれた白線が追い越し禁止の黄色線に見えてしまうくらいに。だから鉄の匂いではないけれど、錆の匂いは僕の鼻に鮮明に残っている。降り積もった雪が解ける頃、春先の朝早く、空気が湿っているときは特にそんな匂いがしました。
というのは僕の思い込みでしょうか。
英文を読むのに疲れると、近所の図書館で借りた松尾宗次さんの『いろいろな鉄』というエッセイ集を読んでいます。文系理系をまたがって、鉄にまつわる古今東西の話がつづられています。そのなかに「香りと鉄」という章があって、そこに冒頭の言葉が載せられていました。町工場で旋盤工をしながら小説を書き、芥川賞と直木賞に複数回ノミネートされた作家小関智弘さんの小説『錆色の町』の結びの言葉だといいます。「かなけ(金気・鉄気)くさい」と広辞苑にも載っているくらい鉄にも匂いはあるそうですが、当時の文芸評論家は「鉄が匂うはずはない、思い込みの過ぎた表現である」と批評したんだそうです。ここまで読んで、僕はふと、自分が生まれた新潟県与板町のことを思い出しました。戦国時代は上杉家の知将直江兼継の城下町として、江戸時代には鍛治町として栄えたこの町は、僕が小さい頃はまだ、金物屋の作業場から火花が散るのを眺めることができるような町でした。豪雪地帯でもあるため、道路にはくまなく消雪パイプが埋め込まれていて、冬の降雪時にはそこからチロチロと地下水が噴き出します。夜遅くに新幹線で長岡駅に着いて、迎えに来てくれた祖父と一緒にタクシーに乗り、運転手と祖父の会話を聞きながら走るときに、前方の道路に降る雪の向こうにひざ下くらいまで吹き上がる水柱をじっと眺めていたことを思い出したのでした。「こんげな日は道路の上の水も凍るすけ、かえって危ねがて…」(新潟弁、間違ってるかも)

消雪パイプ: photo from wikipedia
与板の道は、そんな消雪パイプから出てきた錆の色でオレンジ色をしています。道路に引かれた白線が追い越し禁止の黄色線に見えてしまうくらいに。だから鉄の匂いではないけれど、錆の匂いは僕の鼻に鮮明に残っている。降り積もった雪が解ける頃、春先の朝早く、空気が湿っているときは特にそんな匂いがしました。
というのは僕の思い込みでしょうか。
















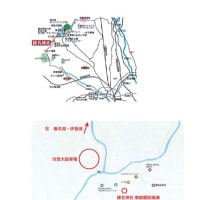
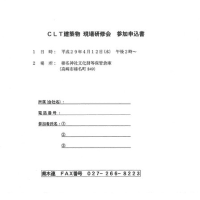
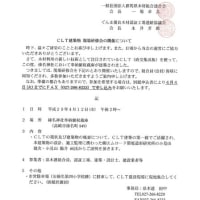









デザイナーズウィークのとき数日間ただひたすら
鉄のフレームを磨きながらの経験上。
でも同じ金属でもアルミって匂わないような気もしないでもない。
酸化鉄が匂うのかなぁ?
人体の感覚器に詳しくないのでなんとも言えないけども。
鉄は他の元素との親和性がとても高いので、金属の中でも比較的匂いやすいのかもしれませんね。