
土曜日の午後にあったTalkと夜のオープニングパーティに行ってきました。

SANAAの2人によるTalkは金沢21世紀美術館以降の近作の紹介。レクチャーの中でパヴィリオンについての説明はなし。質疑応答もそこそこに自由見学となる。



上下両面アルミニウムで合板をはさんだサンドウィッチパネルは上下の曲率差が極力小さくなるように1m×3mほどで割られている。パネルの厚みは一定。パネル自体は曲率の極端に大きい箇所を除き現場で曲げながら柱にボルト止めしたらしい。パネル同士は内部の合板が互いに刺さりあいながらそこでビス止めされている。梁のないフラットスラブを百十数箇所で支える細い柱には60mm径と40mm径があり、いずれも荷重を支えている。60mm径の一部には、地下から電線が通っていて、柱に取り付けられた照明等につながっている。ごみを拾うために管理者が登っていたので想定されているのだとは思うけれど、体重を掛けていたら怒られたので公式には屋根に登ってはいけないようだ。



通常パヴィリオンの設置場所として想定されている敷地以外の場所にも屋根は広がっている。そのためパヴィリオンを道が突き抜けていたり、大きな樹木を囲むように屋根が巡っていたりする。屋根には雨どいがなく、雨水は端っこから垂れてくる。屋根が下りてきていて雨水が流れ込むであろう場所には、砂利が敷かれている。



ウェブサイトでは「煙が漂うような」という説明のされ方をしていて、当初のイメージ画には、コンクリートの床も、アクリルのついたてもない。この日は冷たい雨の降る日だったので、むしろ舗装された床やアクリルの風除けが人の集まり方を強く規定していたけれども、基本的にはどこからでも入れてしまう、タダの屋根。実際、talkのときもパーティのときも、チケットがなくてイベントスペースに入れなかったひとたちもパヴィリオンの周囲に集うことで事実上参加できてしまっていた。見学の順番待ちで並んだり、招待状がないと近づくこともできなかった今までのパヴィリオンとは、そこが根本的に違う。端が見えない建築、です。
















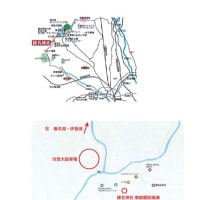
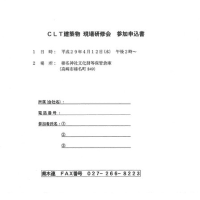
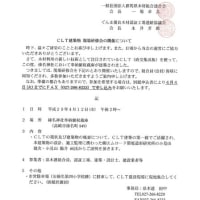







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます