世界最初の鉄橋といわれるアイアンブリッジには、「ありつぎ」「ほぞあなつぎ」「くさび」といったイギリスの伝統的な木組みが参照されているという。これは当時の鋳込み技術の正確さを示しているとともに、鉄という素材がその最初期において独自の構法を有していなかったことを意味している。また、この際に使用された鉄は炭素分の多い鋳鉄というもので、粘り気が少なく、圧縮には強いが引張りには弱い。それは内部構造が石のように粒状だからである。そのため、アイアンブリッジでは石橋のようなアーチ構造が採用されたといわれている。
RIBAの年報を読んでいて、ジェームス・アランソン・ピクトンという人物にたどり着いた。彼は、1880年に「建築における構造材料としての鉄」というレポートを書いている。彼の経歴は「builderの息子」ということになっているのだが、「アングロサクソンの建築は、石造か木造か」という論文も書いていることから、マテリアルに関心のある人物だったのではないかと想像している。その論文の背景には、St.Mary教会という建物をめぐって「11世紀以前にもイギリスに石造文化はあったのか」という論争があったようで、ピクトンは「timber」という単語には語源までたどればもともと「木造」という意味はないのだから、歴史上登場するtimberenという語をもって木造しか知らなかったとは言えない、と述べている。Oxford辞書によれば、timberは古英語ではもともと建築および建築材料一般を指す言葉であり、いつからかそれが木だけのことを指すように変わっていったのである。
そんなことを考えていたら、研究室の先輩の卒業論文がイギリスの木造建築についてだったことを知り、さっそく本文を貸していただくことにした。1666年のロンドン大火以降、都市部での木造建築は排除される方向に法整備が進んでいく。先輩の論文はイギリス木造建築の基本構法が定まった11世紀から、ロンドン大火によって都市部から木造建築が消えていく17世紀末までを扱っている。巻末付録の416人分の大工名鑑(いつどこで、どのような身分賃金で働いていたか)が圧巻。
昨日今日は、今までちょっとずつ書いてきたものを全部つなげて編集してみたりしていた。明日からはまたしばらく資料読みに復帰する予定。
RIBAの年報を読んでいて、ジェームス・アランソン・ピクトンという人物にたどり着いた。彼は、1880年に「建築における構造材料としての鉄」というレポートを書いている。彼の経歴は「builderの息子」ということになっているのだが、「アングロサクソンの建築は、石造か木造か」という論文も書いていることから、マテリアルに関心のある人物だったのではないかと想像している。その論文の背景には、St.Mary教会という建物をめぐって「11世紀以前にもイギリスに石造文化はあったのか」という論争があったようで、ピクトンは「timber」という単語には語源までたどればもともと「木造」という意味はないのだから、歴史上登場するtimberenという語をもって木造しか知らなかったとは言えない、と述べている。Oxford辞書によれば、timberは古英語ではもともと建築および建築材料一般を指す言葉であり、いつからかそれが木だけのことを指すように変わっていったのである。
そんなことを考えていたら、研究室の先輩の卒業論文がイギリスの木造建築についてだったことを知り、さっそく本文を貸していただくことにした。1666年のロンドン大火以降、都市部での木造建築は排除される方向に法整備が進んでいく。先輩の論文はイギリス木造建築の基本構法が定まった11世紀から、ロンドン大火によって都市部から木造建築が消えていく17世紀末までを扱っている。巻末付録の416人分の大工名鑑(いつどこで、どのような身分賃金で働いていたか)が圧巻。
昨日今日は、今までちょっとずつ書いてきたものを全部つなげて編集してみたりしていた。明日からはまたしばらく資料読みに復帰する予定。
















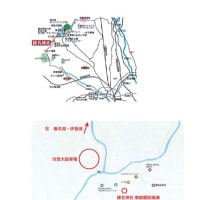
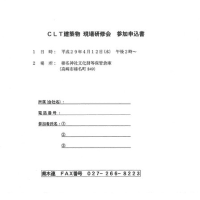
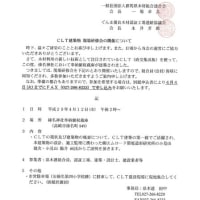







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます