
the Palm House at Kew Gardens/2006年12月9日撮影
鋳鉄梁から錬鉄梁へ、という変遷の具体例として挙げようと考えているのが、キューガーデンの温室である。クリスタルパレスよりも先行する1848年に完成したこの温室は、デシムス・バートンとリチャード・ターナーのコンビで設計がなされた。同じくバートンがパクストンと共同し1840年に完成したチャッチワースの大温室を参照しつつも、こちらは錬鉄造である。当初はチャッチワース同様に鋳鉄造として設計がなされたが、追加予算を捻出して錬鉄造で設計がやり直されたという経緯がある。ここで追求されたのは、より多くの太陽光を取り入れるためのできるだけ細い骨組みであった。鋳鉄を用いた場合、欠点である曲げへの弱さを補うため梁材が太くなってしまう。そこでターナーは、当時特許が取得されたばかりの錬鉄製甲板梁を応用することにしたのである。造船業からの技術移転。これにより、断面でかなりのスリム化が実現され、重量が軽くなったおかげで柱も細くて済んだのだ。

from "Richard Turner and the Palm House at Kew Gardens"
/E. J. Diestelkamp
温室はターナーが自ら持ち込んだ企画にもかかわらず、評議会の方針で実績のあるバートンが主導権を握るかたちで設計が進められた。外観のプロポーションはバートンの意向が優先されターナー不在のまま実施図面まで引かれたが、結局詳細はその後ターナーによって建設途中にほとんど変更されることになる。バートンとターナー、植物園側の責任者との往復書簡からは、ターナーがバートンを立てつつも、肝心なところでは自分の意見を植物園側に主張して認めさせていたことがわかる。ちなみにそうした技術をバートンは逐一特許申請している。
資料を読んでいて思うのは、「実験をして」「試験をして」という表現の多さと、特許申請された造船技術が翌年には建築に移転されているというスピード感。
ちなみにイギリスでは窓に税金をかけていたガラス税が1845年に撤廃される。
















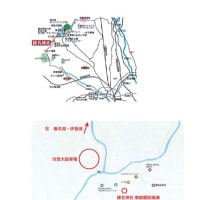
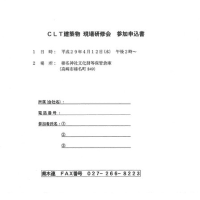
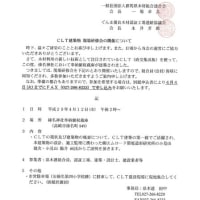








いやほら昔の鉄って黒く塗ってあるのが多いじゃない?
最初のフォード車とかも。
おそらく防錆剤が黒いんじゃないかと睨んでいるのだけれど
具体的な化合物とか知っているわけでもなく、推測の域を出ません。
他力本願でなんですが、なにかそういったことの記述に遭遇したりしてませんかね?
僕が行ったときキューガーデンの錬鉄は白く塗られていました。でも初めからそうだったかはわかりません。ジョン・ナッシュがロンドンに設計したカールトンハウステラスという集合住宅では、鋳鉄柱が壁面の湿式仕上げに合わせてクリーム色に塗られていました。駅舎だったら鉄骨の地の色が剥き出しだったかというとそうでもなくて、リヴァプールストリート駅なんかは鉄骨が赤・青・白・金に塗り分けられています(こちらも最初からそうだったかは不明)。クリスタルパレスは「鉄の枠組はオレンジ色や深紅色、淡青色に塗られ」ていたという記述があります。
当時は防火の観点から鉄骨が石膏版などで包まれてしまうことも多かったのですけどね。そのせいで錆の点検ができないと批判されたりもした。僕は鉄骨造といえば白のイメージがあったけど、それはハイテックの軽い建築による刷り込みだろうな。
水晶宮の色のことは知らなかったよ。
パルテノンと同じくらい驚きの真実って感じ。
モノクロームの画像の刷り込み力はすごいな…。
ま、そんなわけだからカラー写真以前のプロダクトの色の研究してる人はほとんどいないんだろうけど。
>>僕は鉄骨造といえば白のイメージ
それもすごいな。
個人的には鉄骨というよりも住宅周囲の黒い柵の印象。
もしかしたらクリスタルパレスもその影響を受けて、「現代のパルテノン」を意識して彩色されたのかもしれないね。にわか勉強によると、Owen Jonesという建築家、ギリシャに旅行してるね。
当時のインテリは全員知ってただろうから、パルテノンに似せること自体相当政治的なメッセージだったはずだよね。
1840年にパリのサントシャペルの修復が行われて、中世の色彩システムが明らかになったので、教会堂の図式を踏襲していた駅舎などの鉄骨造建築が、中世の教会のポリクロミー(多色彩色)を手本としたことはありうるそうです。ロンドン・ドックは黒だったり、商業建築は原色だったりしたので、用途に応じてある程度塗り分けられていたかもしれないということでした。
というわけで、tomoさんのスキャンダラス(!)な説もありうるかもしれないね。松村昌家さんの『水晶宮物語』という研究本がもうすぐ手元に届くのでまた何かわかったら報告します。
ところでフォード車の黒塗装の件はわかりました。
たしかに車体を錆から防ぐために黒い塗料が塗られていました。その成分は、「天然に産出する黒色のギルソナイトや原油の蒸発残渣ピッチに亜麻仁油などを混合、加熱し、松の樹脂液を蒸留して作ったテレピン油や原油を蒸留して得たミネラルスピリットなどの溶剤に溶かしたもの」だそうです。その黒色が定着し、車は黒いものというのが常識となっていったそうです。
しかしその後、デュポン社が開発した塗料パイロキシンラッカーをゼネラルモーター社が採用し、つやのあるカラフルなラインナップを売り出します。そのシリーズは両社のシェアを逆転してしまうほど売れたそうです。
『これだけは知っておきたい 建築家のための塗料の知識』宇野英隆:監修、伊丹慶輔ほか:著、鹿島出版会、1985
より
うちのボスが散々口にはするんだけど(車の専門家的には常識らしい)
ちゃんとしたことは読んだことがなかったのよ。
まさか「建築家のための」本にあるとは…orz
水晶宮はやはりキューガーデンのイメージだったので
「内装」とか「外装」って単語自体が予想外でした。
こういうことがあるから歴史研究は面白いよね。