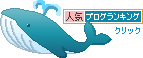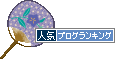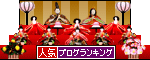|
電子書籍を日本一売ってみたけれど、やっぱり紙の本が好き。 |
| 日垣 隆 | |
| 講談社 |
昨年のiPadの出現により、電子書籍が一気に一般的になり、
紙の本は、近い将来消滅してしまう、電子書籍化に乗り遅れたら未来はないぞ!
という脅迫的な論評を張る人もいるようですが、著者は
私は何も、電子書籍に対して紙の本の優位を説きたいわけではありません。
ただ、電子書籍とそのデバイスの普及は、せいぜいが本のヘビーユーザたちにいきわたればそれだけでおしまい、という市場規模であることはわすれないほうがいい、と言っているだけです。
と言って、電子書籍マーケットの未来は決してバラ色ではないといいます。
今まで本を読まなかった人が、これまでと同じコンテンツであれば、
電子書籍になったからといってそれらを購入してくれるようになるわけではない。
言われてみれば、確かにそうです。
これまで新聞を読んでいた人が、電子版でいいやということにはなっても、
新聞を読まなかった人が、ネットで新聞を読むかというと、それはなさそうですもんね。
「検索」目的の辞書類は電子書籍が圧倒的に優位だし、
そもそも、電子データなら在庫費用が殆どかからないので、「絶版」にする必要がない
という点でも電子書籍のメリットは大きい。
だけど、『カラマーゾフの兄弟』なんかを誰が電子書籍で読みますか!?
と言われても、本格的な電子書籍用デバイスで本を読んだことがないので、
そうそうと納得はできませんが、
散々使ってきたという著者が言うんだから、きっとそう思わせるものがあるんでしょうね。
ま、そういうようなことが、まえがきから、第1章くらいまでは書かれております。
で、2章以降は、新聞など既成メディアの超辛口批判と、自分がいかにスマートで、
先見の明があり、たくさん稼いでいるかという自慢です。
へ~、ふーんと読んではいたのですが突然、TBSの批判になって、目が点。
なんか、ご自身がどうもTBSから嘘つき呼ばわりされたようで、
そのことに対する怒りを、滔々と書かれていて、
そのうち、トヨタのディーラや老舗旅館で自分が受けた酷いサービスなども書き連ねて
生き残れないものの典型と酷評されるのですが、
だんだん、私、何の本読んでいたのかしら・・・とわからなくなりそうでした。
様々な批判は、納得できる部分も多いのですが、
それにしてももう少し、自慢せずに書けないのでしょうか。
図書館で借りて読んだからいいけど、自分で1300円出して買っていたらかな読後感が悪くて、
後悔していただろうなということです。
著者についての、ウィキペディアの記載も結構、辛口・・・。
見た目は、学校の先生っぽいのに、言いたいこといってきて敵が多いみたいですね。