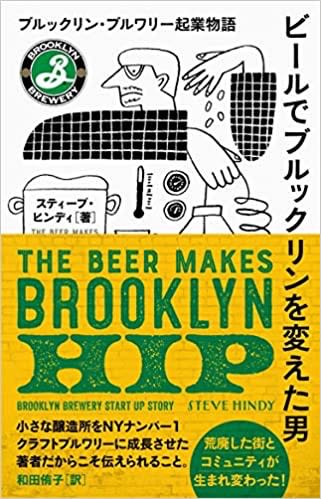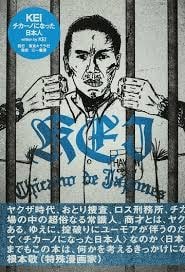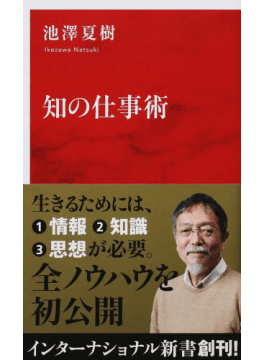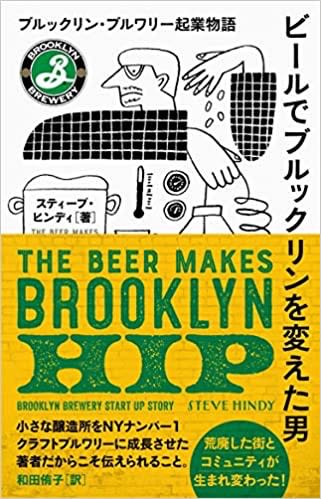
妥協せずにおいしいものを作り、事業として成立させるのはとても難しい。
大きな資本で、品質とコストを落として、大半の人がそこそこ満足するもを作っている会社と競争するのはとても難しいから。
そんな挑戦のビール業界の事例。
そこそこ満足している人に、割高になるものを知ってもらって、指示してもうには、
おいしいだけでは難しい。不満のないところに、新しいものを提示するわけだから。
しかも、液体。運ぶのにもコストがかかるし。そして、味が変わる。
制約がとても多い。
そんな挑戦の話。本の装丁からも伺えるがヒップというか、どこかかっこいい。
ドラマチックなエピソードもあるが、ビジネス上の現実も書いてある。
面白くて、ためになる。良書だと思う。
著者のスティーブ・ヒンディは、中東でのレポーター経験からビールを作り始めた人。
意外な経歴。ビール会社に勤めて不満を感じて独立したのではない。
I LOVE NYのロゴを制作したミルトン・グレイザーが、ブランドのロゴを制作を発注することに成功。
仕事を選ぶ超大御所に仕事を受けてもらうのはとても大変なはず。言われてみれば、とてもキャッチーなロゴ。
アイディアにストーリーがあってこそミルトン・グレイザーを説得できたと思う。
あとは、使い倒された言葉だけど「熱意」。これも必要。もちろん、持ってるだけではなく人に伝えることが必要。
ビジネスでのリアルな制約も具体的に書いてあり参考になる。
目先の成長は遅れても、譲れない線は守る。
雇われ社長ではしずらい判断かも知れない。
しかし、とても大切なこと。この判断がグズグズになると、
自分たちが何者かわからなくなってしまう。
自分や自分の職場と照らし合わせた時の対比が
自分の状況を見つめ直すことに役に立った、とても。