
和製ヘミングウェイ的なイメージが少しある。
文章と釣り、、、あと戦争を取材とかね。マッチョな面。
もちろん、それだけじゃない。同じくらいセンシティブで、内向的でもある。
ヘミングウェイの文章は簡潔として知られる。
開高健もそうなのかな。わからん。でも、ぶ厚い。denseな感じがする。
今、こんな文章を書く人を僕はしらない。描写力もそう。
読んでいて浮かぶのが、情景、平面のイメージでなく、彫刻とかなにかもっと立体的でtangibleな感じ。
筆力。言葉での表現力。the ability to portrait what he saw.
これが尋常じゃない。プロの書き手という感じ。
さらに、マテリアル(書いている対象)が戦争やその周辺で暮らす人だったりすると、書き上がった文章のパンチは重たくなる。
そうゆうことだと思う。
何度も読みたる。読むたびに舌を巻く。

三浦さんの主張には全面的に同意。
だけど、自分の感覚を代弁してくれる人の本を読んでいい気持ちになっているだけではいけないと思う。
で、自分はどうするんだ。
それが問題。
「世界中どこでも、食べる行為が道空間に向かって濃密に行われる街はいい街だ」と槇文彦というお名前の先生が仰ったらしい。
よくわかる。
「文化は真面目な人にはつくれない」この言葉も心に残った。
確かにそう。だから大企業が行う再開発には違和感を感じてしまう。
文化とは直接関係ないかも知れないけどつまらなくなるんだ。

メディアで頻繁に見かける落合陽一さん。
といっても、YouTubeに出てくるNews PicksのWeekly Ochiaiがメインだけど。
どんな人なのかと思って本を手にとってみた。
研究の内容はよくわからないけど、自分を追い込んでいることはよくわかる。
そして追い込み続けている。大したもんだと思う。
わざわざ世の中に向けて発表しなくてもよさそうな内容もあるけど、
実名でさらけ出すことはなかなかできることではない。
「思い込む力」という言葉は良いなと思った。
ちょっとひねくれた味方をすると、
こんな文章を書いている暇があれば、、、と思うこともある。
書くことによって思考が整理されたり、可視化できたりするし、
メリットは確かにあると思うけど。言い訳できないもんね。自分にも他人にも。
その辺りの覚悟は見上げたものだと思う。
本のタイトルと内容は一致しない。
「思い込む力」という表現は覚えておきたい。

心地よい本。
松本隆さんはホンモノというか大物というか、
落ち着いている。年齢もあるが、自分をとりまくモロモロを
ごまかさないで向き合ってきたのではないかと思う。
だからか、言葉に含蓄がある。
最初の「SNSについて」、その次の「天才について」をチラッと読んで買うことにした。
「才能について」、「意志を持つ」も印象に残った。
なかには「詞のつくり方」という実用的?なものもある。
松本隆さんが言っていることだと思うと
スッと心に入ってくる。
ときどき読み返したい本。
それにしても、かっこいい人だ。
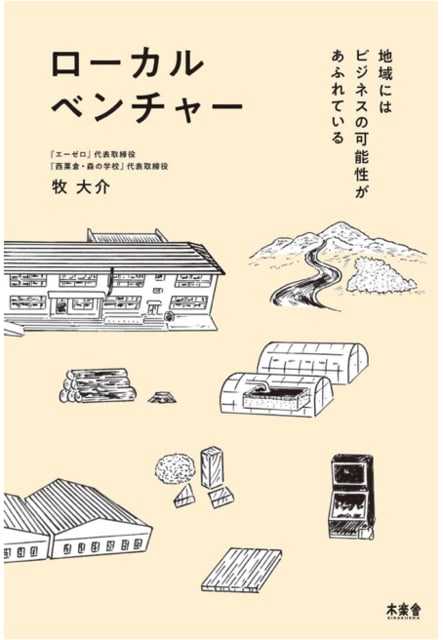
良書。
牧大介さんは、その経歴からもわかるが非常に頭が良い。
知識だけでなく、実社会に積極的働きかけている点が非常に魅力的。
どこかから借りてきたようなことをせず、時間をかけて制度(プログラム)を設計していく。
その根っこには自らイメージした形や景色がある。
そのような印象を受けた。
このアプローチはクリエイティブな仕事に近いと思う。
映像、音楽、グラフィック制作という意味ではなく、
創造していくという意味でのクリエイティブ。
この思考ができ、かつ実行に移し、しかも実績を残す人は非常に大切。
こういう人の周りに人が集まり、行動を起こし、そして少しずつ社会が変わっていく。
そのプロセスの中で個人は幸福を感じ、社会は問題解決に近づく。
関係人口という言葉を初めて聞いた。
特に地方の地域活性化は人口の増加とセットで考えられることが多いが、
住人としてでなくても、その地域と関わっている人の数を地域活性化に於ける
指標として捉えることができる。
そして、ベンチャー企業を支援する際に、
ピュアなモチベーションというか、熱意というか、好きであることを
最重視するやり方にも共感する。それがないと駄目な気がする。
いくら形を美しく設計しても、エンジンがない車は走らない。
牧さんのような生き方は、悩みも多いだろうが、充実していると思う。
そして、その一歩を踏み出すのに必要なのはほんの少しの勇気である気がする。
勇気よりも、ノリとか勢いの方がニュアンスが近いかも知れない。
とにかくやってみればいいんだよ。
そう思った。
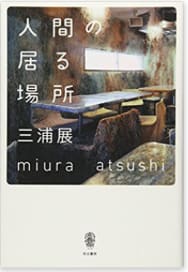
買ったままずっと読んでいなかった。
地域とかコミュニティについて買いてある本。
偉い人たちも、大きな資本を持つ企業のみが参加する再開発の不健全さは感じていることが良くわかる。
その認識の上に立って何ができるのか、ということなんだね。
みんなそれぞれの形で。
MY HOUSEという映画が紹介されている。
これは観てみようと思う。ホームレスに昔から興味がある。
子供のころの僕にはとても恐ろしい存在だった。
公園から帰るときに「あの人たちには帰る家がない」と思っていた。
都市と都会の違いなど、思考を深めるには厳密な言葉の定義が必要であることを再認識した。
どんな分野であれ、プロの世界では当然のことだけど。

休日に移動中電車の中、ホテルのラウンジ、ビジネス街のカフェで読んだ。
大坊さんがお好きな画家や彫刻家について、あと珈琲屋での無言のコミュニケーションのお話がとても素敵。
後者の話は珈琲屋の元店主ならば文字にできてさほど不思議はない。
だけど、前者の方はなかなかできない。
きっと、何事も丁寧に、自分で感じながら、目をそらさずに、自分にも自分の周りとも向き合って生きている、そう思った。
いつでも憧れている、そういう人に。
落ち着いて、しっかりと生きている人。不思議と自信が湧いてきたりもするんだろうと思う。
だから、さらに向き合うことができて、所作や考えが深まっていく。大坊さんの珈琲の味もそうやって深まっていたったのだろうと思う。
大坊珈琲店へは行ったことがある。行ってみてよかったとつくづく思う。
形あるものはいつかなくなっちゃうからね。
大坊さんの本の装丁はいつも洗練されている。無駄なものも少ない。
お店があったのは東京・青山だし、お知り合いのデザイナーに頼んだろうか。
かっこいいんだよな。珈琲も、大坊さんも、本も、文章も。ため息がでるくらい。

苦しみ、悲しみ、不安を乗り越えて笑顔でいる人は聡明だと思う。
不景気な顔をした学者よりも、明るく語れるおっさんの方が人生・社会に有益かつ幸せなんじゃないかと常々思う。
どんな局面でも、どうすれば良いかわかれば、明るくふるまえるのだ。例えそれが完璧な解ではなく、諦めを伴っても。
そのとてもわかりやすい例。
困難なんて笑い飛ばせる知性と強さが欲しい。
文章から受ける感覚に浅田次郎さんと共通する部分がある気がする。
PEN(国際ペンクラブ)の空気感なのかな。
たしか カート・ヴォネガットさんも浅田さんもしていた気がする。
ペン(文字、文章、小説、言論)はいいな。やっぱり好きだな。
音楽も大好きだけど。
カート・ヴォネガットさんも本書の中で音楽は美しいと言っているし。
コミュニティが大切だとも書いてある。
僕の場合は自分を育ててくれたコミュニティに
give backしたいと思ってる。あわよくば、
そこの住んだり、関わっている人たちが楽しくなる形で。
その方がこのクソッタレてて寂しい人生が、
少しはマシになるんじゃないかと思う。

僕にとっては刺激的な内容だった。恥ずかしながらWIREDはほんのたまに買っていただけ。佐久間裕美子さんのヒップな生活革命→だえん問答→こんにちは未来という流れで行き着いた。今さらながら若林さんが編集長がだった頃のWIREDのバックナンバーを買っている。(まだぜんぜん読めてないけど)。
著者の若林恵さん。少年時代の2~4コ上の先輩というか、ファミレスで好きなものを注文させてくれた友達のちょっと悪いお父さん的な感じがする。
他の地元の猛者どもから守ってくれるわけでも、全能の知恵を授けてくれるわけでもない。一生の師にもおそらくならないだろうと思う。それでも大きな影響を受けていると自覚している。
あたかも地元の先輩や身近な大人のような感覚がするのは、職業がそう遠くないからだと思う。僕は編集者ではないが、広い意味でのプロデューサー的な感じ。僕は自分の立場に歯痒さを感じるけど、若林さんの活躍を目にすると少し安心する。同じ道の先を行っている先輩の感じ。若林さんのレベルには到底かなわないけどね。若林さんもいろいろ自分のキャリアなどについて、考えながら(迷いながら?)生きているのではないかと思うが、勝手に親近感と安心感を覚えている。
本書は2回読んだ。WIREDの巻頭用の編集長からのメッセージエッセイ的な文章が多い。そのため、トピックは当時の特集によって異なり、頭の切り替えにエネルギーを使用する。エッセイ集的であり、つまり一冊を通して何が言いたいというわけではないと思う。それだけに、受け取る視点や知識がたくさんある。お金持ちの宝石箱みたいに。その宝石はどれも刺激的。本当の財産は頭の中にあるのだ。
「こんな考え方もできる」、「実はこんなことだったりするのでは」、「この人が過去に言ったことは、今日の課題に於いてはこのような示唆をしていると捉えられないか」とか、少し刺激的、そして少し前を見据える癖を僕にくれた気がする。
たまに少しずつ読み返していきたい。

パウロ・コリーニョの「アルケミスト」を思い出した。
思いが大切なわけだが、その思いを変えるには、
その栄養となる環境や意識的にインプットする情報を変える必要があるよな、、と思う。
ただ、日々の思いの大切さを念頭に置いて生活することはとても大事。

西川美和監督のエッセイが好きで、たしか西川監督は是枝監督の弟子?仲間?だったなと思い読んでみた。
最高。
世の中を丁寧に、しっかりを腰を据えて見ていることがよくわかる。
仕事に追われていると、子供の頃の感覚(プールの後、塩素ですべすべの肌など)の感覚を
思い出すことは過去を振り返る行為で、成長しきれていない証拠で、恥ずべきことに感じることもあるが、
人間として大事ななことで、実はそこにから、自分が漠然と感じている不満の原因や打開の方向を見つけることができるのかも知れない、
なーんてことを思った。
テレビマンユニオンに所蔵していることは知らなかった。













