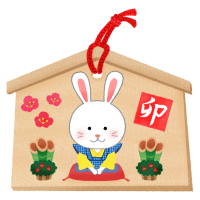| ニュー・アース -意識が変わる 世界が変わる- 価格:¥ 2,310(税込) 発売日:2008-10-17 |
 オリジナル ステンレスラックのユーロカード用フロントプレートが先日完成したので、ラッキングする前に久しぶりにフォーラムを覗いた所、色々新しい方法が論議されていたのでそれらを試してみました。
オリジナル ステンレスラックのユーロカード用フロントプレートが先日完成したので、ラッキングする前に久しぶりにフォーラムを覗いた所、色々新しい方法が論議されていたのでそれらを試してみました。 このアンプはユニバーサルアンプとして『zero-ohm entrances』と言われる方法で適合した抵抗値をモジュールの入り口に配置し希望する用途に合わせて使用します。マイクプリの場合、RE = 40Ωを推奨していますので今まではマニュアル通りそれに従ってRG = 250kΩでゲイン調整をしていましたが、それだと少々ゲインが足りないのでRG = 500kΩにして56dB以上のゲインを稼ぐと高域が少々ドロップしたりでラッキング方法は様々な方法が議論されていました。
このアンプはユニバーサルアンプとして『zero-ohm entrances』と言われる方法で適合した抵抗値をモジュールの入り口に配置し希望する用途に合わせて使用します。マイクプリの場合、RE = 40Ωを推奨していますので今まではマニュアル通りそれに従ってRG = 250kΩでゲイン調整をしていましたが、それだと少々ゲインが足りないのでRG = 500kΩにして56dB以上のゲインを稼ぐと高域が少々ドロップしたりでラッキング方法は様々な方法が議論されていました。最新のトレンドは、いくら『zero-ohm entrances』と言ってもトランス自体に固有のインピーダンスが存在するのでエントランス抵抗は必要無く初段でゲインを稼いだ方がf特 / 歪率共に有利ではないか?と言うものです。実際にこの方法でラッキングして測定上も全く問題がない事が報告されていましたので早速試してみる事にしました。
Telefunkenのマニュアルにあるような結線では、特徴的な中域で輪郭をはっきりさせるようなイメージ通りのTelefunkenサウンドですが、エントランス抵抗を省いた結線はもう少しモダンと言うか高域の特性が伸びやかな感じがします。ビンテージ的な色合いは少々薄れますが12~15kHzあたりに不足を感じていた方にはお勧めです。
 実際に採用したのは、マイク/ラインの切り替えをしたいので初段に-26dBのPadを入れてREはDPDTで0Ω / 6.81kΩを切り替えて、RGは500kΩ / LINのPODがあったのでそれを使用しました。リニアカーブだと少々音量変化が急なのでAカーブを擬似的にシュミレーションするために470kΩ(この値だとカーブは殆ど変わりません 笑)をワイプとボトム間にハンダ付けしましたが、計算値では242kΩにしかならないはずが、実測値では264kΩでしたのでとりあえずはそれで良しとします。RGの理想は350kΩ / Aカーブがあれば良いのですがそんなボリュームは探しても見つかりませんので懸案であるELMAのスイッチでステップゲインを製作したいのですが抵抗値を計算してもその通りにならないので沢山の抵抗を揃える必要があり、未だ実現に至っていません。500kΩ / Aカーブが入手出来ればフルまで回し切らなければ問題無いのでそれでも良いと思います。
実際に採用したのは、マイク/ラインの切り替えをしたいので初段に-26dBのPadを入れてREはDPDTで0Ω / 6.81kΩを切り替えて、RGは500kΩ / LINのPODがあったのでそれを使用しました。リニアカーブだと少々音量変化が急なのでAカーブを擬似的にシュミレーションするために470kΩ(この値だとカーブは殆ど変わりません 笑)をワイプとボトム間にハンダ付けしましたが、計算値では242kΩにしかならないはずが、実測値では264kΩでしたのでとりあえずはそれで良しとします。RGの理想は350kΩ / Aカーブがあれば良いのですがそんなボリュームは探しても見つかりませんので懸案であるELMAのスイッチでステップゲインを製作したいのですが抵抗値を計算してもその通りにならないので沢山の抵抗を揃える必要があり、未だ実現に至っていません。500kΩ / Aカーブが入手出来ればフルまで回し切らなければ問題無いのでそれでも良いと思います。以前の方法でPODの所に入れていた2.2kΩはエントランス抵抗を省いたので使用しません。
ガリや振動で無限大になると凄いゲインになりそうなのでワイプとトップをジャンパーします。
今回のラッキングでは、2系統あるアウトプットを両方使用出来るようにしようと思っていますが、その理由は次回にさせて頂きます。
Telefunkenのマニュアルにある結線はこちらを参考にして下さい。