プロローグ
![]() 室町時代の物語を集めた『御伽草子』などによると、「酒呑童子」の姿は、顔は薄赤く、髪は短くて乱れた赤毛、背丈が6m以上で角が5本、目が15個もあったといわれる。
室町時代の物語を集めた『御伽草子』などによると、「酒呑童子」の姿は、顔は薄赤く、髪は短くて乱れた赤毛、背丈が6m以上で角が5本、目が15個もあったといわれる。
彼が本拠とした大江山(京都府にある山。京都市西京区と亀岡市の境に位置する。標高は480m。)では龍宮のような御殿に棲み、数多くの鬼達を部下にしていたという。
酒呑童子生立ち伝説
その1
伝教法師(最澄:さいちょう)や弘法大師(空海)が活躍した平安初期(8世紀)に越後国で八岐大蛇と人間の娘との間で生まれた彼は、若くして比叡山に稚児(昔貴族や寺院に仕えた少年)として入って修行することとなったが、仏法で禁じられている飲酒をし、しかも大酒呑みであったために皆から嫌われていた。ある日、祭礼の時に被った仮装用の鬼の面を、祭礼の終了後に彼が取り外そうとしたが、顔に吸い付いて取ることができず、やむなく山奥に入って鬼としての生活を始めるようになった。そして茨木同時と出会い、彼と共に京都を目指すようになったといわれている。
その2
酒呑童子は、越後国(現在の新潟県本州部分)の蒲原郡中村で誕生したと伝えられているが、伊吹山の麓で、『日本書紀』などで有名な伝説の大蛇、八岐大蛇が、スサノオとの戦いに敗れ、出雲国(島根県東部)から近江へと逃げ、そこで富豪の娘との間で子を作ったといわれ、その子供が酒呑童子という説もある。その証拠に、父子ともども無類の酒好きであることが挙げられる。
伝教法師(最澄)や弘法大師((空海)が活躍した平安初期(8世紀)に越後国で生まれた彼は、国上寺(新潟県燕市)の稚児となった(国上山麓には彼が通ったと伝えられる「稚児道」が残る)。
その4
越後国の鍛冶屋の息子として産まれ、母の胎内で16ヶ月を過ごしており、産まれながらにして歯と髪が生え揃い、すぐに歩くことができて5~6歳程度の言葉を話し、4歳の頃には16歳程度の知能と体力を身につけ、気性の荒さもさることながら、その異常な才覚により周囲から「鬼っ子」と疎まれていたという。『前太平記(通俗史書。40巻・目録1巻。藤元元作。天和元年(1681)ごろの成立。)』によればその後、6歳にして母親に捨てられ、各地を流浪して鬼への道を歩んでいったという。また、鬼っ子と蔑(さげす)まれたために寺に預けられたが、その寺の住職が外法(妖術)の使い手であり、童子は外法を習ったために鬼と化し、悪の限りを尽くしたとの伝承もある。
その5
12, 3歳でありながら、絶世の美少年であったため、多くの女性に恋されたが全て断り、彼に言い寄った女性は恋煩い(こいわずらい)で皆死んでしまった。そこで女性たちから貰った恋文を焼いてしまったところ、想いを遂げられなかった女性の恨みによって、恋文を燃やしたときに出た煙にまかれ、鬼になったという。そして鬼となった彼は、本州を中心に各地の山々を転々とした後に、大江山に棲みついたという。
酒呑童子退治伝説

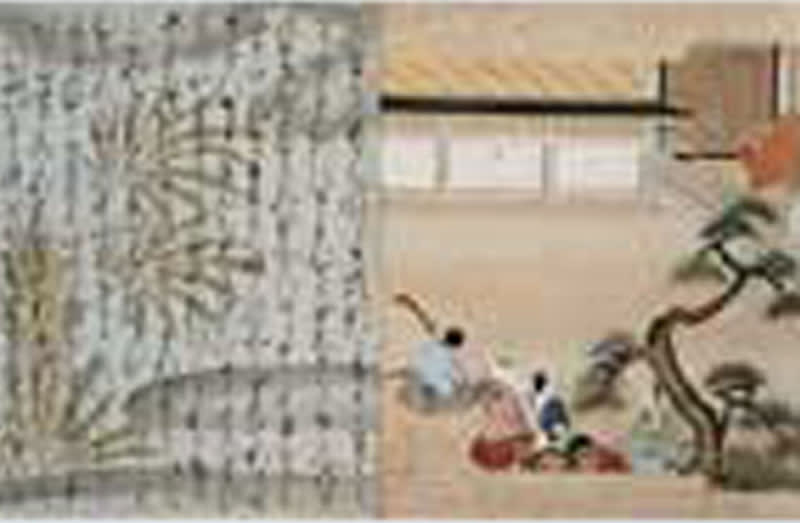
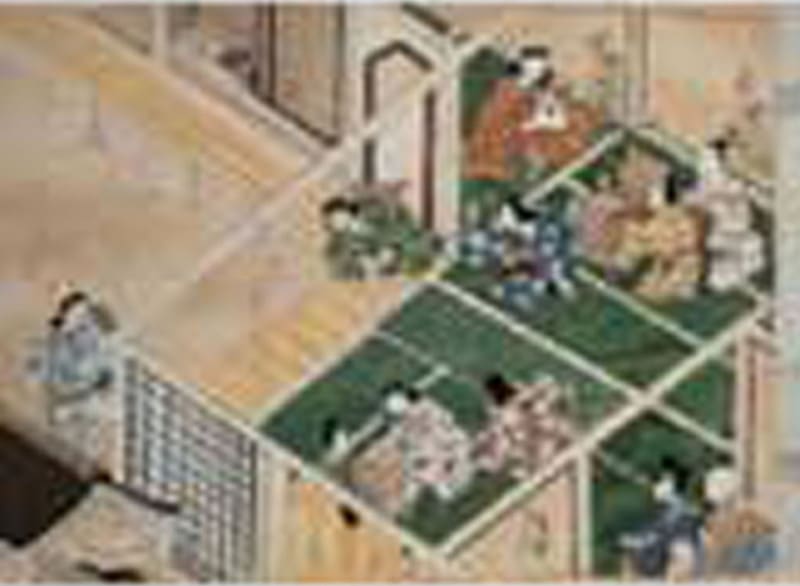



 酒呑童子は大江山の棲む鬼で、都を荒らし回っては数多くの人を殺して食べたり、貴族の姫君をさらったりした鬼です。
酒呑童子は大江山の棲む鬼で、都を荒らし回っては数多くの人を殺して食べたり、貴族の姫君をさらったりした鬼です。
その存在は晴明によって暴かれます。
ある貴族の姫君が突然、行方不明になったのを心配した一条天皇は、晴明を召しだし 占わせ、「これは大江山に棲む鬼の仕業です。このまま捨て置けば、都はおろか諸国にまで仇なすことは間違いありません。」と、陰陽道の力で明らかにしたのです。
占わせ、「これは大江山に棲む鬼の仕業です。このまま捨て置けば、都はおろか諸国にまで仇なすことは間違いありません。」と、陰陽道の力で明らかにしたのです。
 それで、天皇は、源 頼光に酒呑童子の退治を命じ、源 頼光は渡辺 綱ら四天王を連れて、大江山に向かうので。頼光たちは酒呑童子を見つけると、鬼の仲間のふりをし、酒呑童
それで、天皇は、源 頼光に酒呑童子の退治を命じ、源 頼光は渡辺 綱ら四天王を連れて、大江山に向かうので。頼光たちは酒呑童子を見つけると、鬼の仲間のふりをし、酒呑童 子を油断させ、だまして毒酒を飲ませて退治するのです。
子を油断させ、だまして毒酒を飲ませて退治するのです。
酒呑童子が都を襲ったのは、一条天皇の時代の正暦元年(990年)から正暦6年(995年)のあいだと言われています。晴明は69~74歳。陰陽道としては重鎮中の重鎮です。占術にしても呪術にしても神の領域に達するほどだったでしょう。
![]() 確かに酒呑童子を倒したのは武力です。しかし、この陰には晴明の呪力があったことを忘れてはなりません。
確かに酒呑童子を倒したのは武力です。しかし、この陰には晴明の呪力があったことを忘れてはなりません。
![]() 晴明は式神や護法童子を京のあちこちに放ち、酒呑童子が都に入って来られないよう守りを固めたのです。
晴明は式神や護法童子を京のあちこちに放ち、酒呑童子が都に入って来られないよう守りを固めたのです。
そう、晴明はたった一人で、広い京の全てを防衛したのです。
そのおかげで、酒呑童子は京に入ることが叶わず、大江山で歯がみして悔しがりながら酒![]() を呑んでいたのです。
を呑んでいたのです。
源 頼光の活躍の陰には晴明がいたのです。
 そして、晴明が後顧の愁いを絶ったからこそ、頼光らは酒呑童子を倒すことだけを考えることができた。そう、晴明なくして酒呑童子は倒せなかったのです。
そして、晴明が後顧の愁いを絶ったからこそ、頼光らは酒呑童子を倒すことだけを考えることができた。そう、晴明なくして酒呑童子は倒せなかったのです。
その2解説
酒呑童子の物語は仏教文化を背景として宗教説話的な要素を盛り込んだものです。
「今昔物語」をはじめとして、多くの物語で仏教に敵対するものは鬼として描かれており、酒呑童子もそんな鬼の一人なのです。
 ただ、仏教説話が流行したこの時代は、とりもなおさず仏教がそのまま政治に置き換えられる時代である事を、忘れてはならないのです。つまり、政教一致の時代だったのです。
ただ、仏教説話が流行したこの時代は、とりもなおさず仏教がそのまま政治に置き換えられる時代である事を、忘れてはならないのです。つまり、政教一致の時代だったのです。
そのことを考えあわせると、この時代でいう仏教に敵対するものというのは政治に敵対するものだったのです。
そんな反逆者が大江山という古代製鉄技術や出雲神話の痕跡が存在する山に住んでいたのは単なる偶然ではありません。
少なくとも「酒呑童子」という物語の作者は「酒呑童子」の真実を知っていたのだと思います。
酒呑童子が最期に言った「鬼神に横道なきものを(※後期酒呑童子参照)」という言葉には、山中で古くからの文化を守り続けた勇者達の悲痛な叫びが込められている様な気がしてならないのです。
当時、鬼と呼ばれた者達が歴史の闇の中で、妖怪、化け物の類として塗り変えられていった悲劇を垣間見ることができるのではないでしょうか。
丹波各地にある数々の旧跡は「出雲」と「鉄」を媒介として酒呑童子とのつながりを見せてくれています。
大江山のみならず出雲、熊野、越後などなど酒呑童子等、即ち鬼達の歴史の舞台をこれからも機会があれば探ってみたいと思います。
*
以下に掲載する「酒呑童子の物語」は、当時の歴史的背景や混乱の中で、鬼というものがどのように創作され、政治に利用されていったのか・・・。鬼たちの正義、政治を司るものたちの悪意、謀略、陰陽師たちの正体が暴かれていきます。
ですから、前記の良く知られている「あらすじ」とは微妙に異なった展開となり、最後には、私たちの知っている「酒呑童子」とはまったく違う、鬼たちの悲痛な叫び声が聞こえてきます。
*酒呑童子のいく通りもある伝説の一編を掲載します。






























