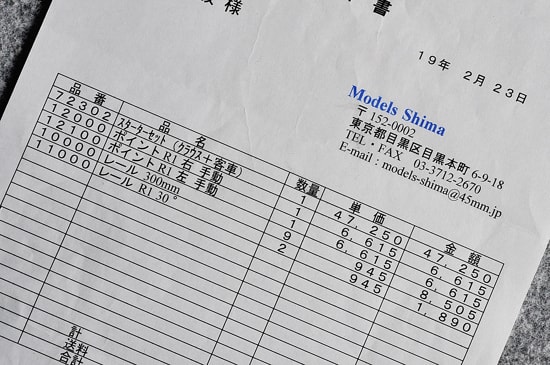小径レイアウトを作る為、レールベンダーを自作し、半周分のレールを曲げ終えた所まではお伝えしていましたが、後の半分を曲げる前にレールベンダーを改造しましたので、その経緯を報告しておきます。花咲爺さんの「形から入る」典型的な悪い例でした。

これは自作したてのレールベンダーです。「戸車」をドリルレースで削ってローラーを作り、ハンドルの握りに「鍋蓋つまみ」を使うなど、それなりの仕上がりでした。
ただハンドルの回転だけではレールは進まず、手で後押しをしてやる必要がありました。
ただ曲げアールの確認には役立ちました。曲率が一定しているとハンドルを回す力が一定ですが、曲げが足らない部分が有ったら、手に余分な力が掛かって感触で判るからです。

今回、あと半周分を加工する前に、ローラーを取り除き、アングルに凹と凸を付けました。
もっと大きなゲージのレールや、パイプなどを曲げる時に、世間でよく使われるベンダー方式です。
このやり方だと万力のレバーを締めたり緩めたり頻繁にやる必要はありますが、万力レバーの締め具合が飲み込めたら、1本のレールが10分足らずで済みました。レールの送りは2~3cm程度が良かったです。

もう1つ経験から得たノウハウ(?)を申し上げておきますと、レールは逆さ向きにセットして、レールのフランジがアングルの上面に、常に接地している事を確認しながら曲げていくとレールに変なネジレが生じないですみます。ネジレが生じたかどうかを知るには、ガラスを定盤代わりにして、置いてみたら良いでしょう。
私が使用したアングルの厚みは3mmでしたが、4㎜だとレールの溝にピッタリなのでもっと良いようです。

これは曲げ終わった半周分4本のレールを、ゲージ代わりに描いていたカーブに沿わせてみた写真です。ほぼドンピシャリに仕上がっています。ここまでの作業は1時間も掛かりませんでした。

次に枕木の加工にはいります。外周の枕木のつなぎはそののままですが、内周のつなぎはレールが短くなった分だけ縮める必要があります。ニッパーやカッターナイフで1箇所について1.3~1.5mm程切り取ります。その場合ジョイント(ジョイナー)の付く側の1箇所だけは切り取らないのがコツです。レールはジョイントを介して枕木に固定されますから、枕木が1本より2本の方がしっかりしています。偉そうな事を言いますが、これも経験で得た教訓です。

あとは組み付けるだけです。分解する時、レールとジョイントのカシメ部をドリルで解除していますので、最終的にはその穴にハンダを流し込んで固定する予定ですが、後で微調整があるのでとりあえずはこれで終わりです。

出来上がったレールを初めて全周つないで「亀の子ケーシー」を走らせて見ました。やはり亀の子には小さなレイアウトがお似合いのようです。
ちなみに、手前に直線レールが置いてあるのが、ちょうどレイアウト盤半分の広さです。

ついでに、「折りたたみレイアウト盤」全体を使ってエンドレスを作ってみました。これが基本形になってどれだけ支線が延ばせるか、ゆっくり考えてみたいと思います。
一応通電もして走らせて見ましたが、いたってスムーズで且つ快調でした。
ここに使ったレールは、全て隣に見えるお座敷レイアウトの、引込み線等から借用しました。よってお座敷レイアウトは、外回り線と内回り線だけが、辛うじて機能している状態です。何時になったら現状復帰するか全くめどは立っていません。