
信濃毎日新聞社が今日の視角で、長谷川眞理子教授(←クリック)の怒りの声を取り上げている。
■■引用開始■■
タウンミーティングでの文科省などによる「やらせ」質問問題が話題となっている。どんなことだったのか、徹底的に調査して、関係者の処分も考えるという政府の方針が報道されていたが、この問題は、もっともっと重大なゆゆしき問題であると思う。
実際、私はこの話を聞いて呆(あき)れるとともに、心底、怒りを感じている。教育基本法改正を国民が望んでいるという雰囲気をつくり出すため、そのような意見や質問をあらかじめ書いて参加者に渡し、あくまでも自分の意見であるかのように、わざとらしくなく言ってくれという指示までつけたということだ。
これは、民主主義の根幹を無視した態度であり、国民をばかにするにもほどがある。呆れるほど稚拙なやり方で行われた、たいへんに汚い、卑怯(ひきょう)で悪質な行為である。
最近、研究費の不正使用、データのねつ造など、科学者の倫理が問われる問題がいくつか発覚し、科学者の信用が大きく傷つけられた。いずれも、科学者としてやってはならない悪事である。科学者個人の問題ばかりでなく、なぜこんなことが発生するのか、科学研究をめぐる今日の状況についても、大いに議論がなされた。
たとえば、現在の研究費の使い方の規則が、研究の実情にあっていない、研究費獲得のための過当競争が、安易な論文多作を促す、などの一般的状況が、指摘されている。そして、科学者の倫理に関する指針が、政府からも、学者の団体である日本学術会議からも出された。それは、科学者の不正の問題の根が、単に特定の個人の悪行のみならず、科学という営み全体のあり方にもあると考えられたからだ。
それと同様に、今回の「やらせ」問題も、文科省の特定の官僚が起こした不祥事というだけでなく、文科省という組織全体に、このような稚拙なやらせを起こさせる何かがあるのではないだろうか。日本の教育、科学、技術、文化すべての政策にかかわる人々がどんな「文化」を持っているのかと考えると、寒々とした思いを禁じ得ない。
■■引用終了■■
(おまけ)
無料パンフレットの紹介
タイトル:弁護士から見た教育基本法「改正」の問題点~自由法曹団著
入手先:こちら(←クリック)
教育基本法の問題点を丁寧に説明したパンフレット。PDFになっており、全て無料で見ることができます。ぜひ、一読を。忙しい方はQ&Aだけでもご覧下さい。
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。
■■引用開始■■
タウンミーティングでの文科省などによる「やらせ」質問問題が話題となっている。どんなことだったのか、徹底的に調査して、関係者の処分も考えるという政府の方針が報道されていたが、この問題は、もっともっと重大なゆゆしき問題であると思う。
実際、私はこの話を聞いて呆(あき)れるとともに、心底、怒りを感じている。教育基本法改正を国民が望んでいるという雰囲気をつくり出すため、そのような意見や質問をあらかじめ書いて参加者に渡し、あくまでも自分の意見であるかのように、わざとらしくなく言ってくれという指示までつけたということだ。
これは、民主主義の根幹を無視した態度であり、国民をばかにするにもほどがある。呆れるほど稚拙なやり方で行われた、たいへんに汚い、卑怯(ひきょう)で悪質な行為である。
最近、研究費の不正使用、データのねつ造など、科学者の倫理が問われる問題がいくつか発覚し、科学者の信用が大きく傷つけられた。いずれも、科学者としてやってはならない悪事である。科学者個人の問題ばかりでなく、なぜこんなことが発生するのか、科学研究をめぐる今日の状況についても、大いに議論がなされた。
たとえば、現在の研究費の使い方の規則が、研究の実情にあっていない、研究費獲得のための過当競争が、安易な論文多作を促す、などの一般的状況が、指摘されている。そして、科学者の倫理に関する指針が、政府からも、学者の団体である日本学術会議からも出された。それは、科学者の不正の問題の根が、単に特定の個人の悪行のみならず、科学という営み全体のあり方にもあると考えられたからだ。
それと同様に、今回の「やらせ」問題も、文科省の特定の官僚が起こした不祥事というだけでなく、文科省という組織全体に、このような稚拙なやらせを起こさせる何かがあるのではないだろうか。日本の教育、科学、技術、文化すべての政策にかかわる人々がどんな「文化」を持っているのかと考えると、寒々とした思いを禁じ得ない。
■■引用終了■■
(おまけ)
無料パンフレットの紹介
タイトル:弁護士から見た教育基本法「改正」の問題点~自由法曹団著
入手先:こちら(←クリック)
教育基本法の問題点を丁寧に説明したパンフレット。PDFになっており、全て無料で見ることができます。ぜひ、一読を。忙しい方はQ&Aだけでもご覧下さい。
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。










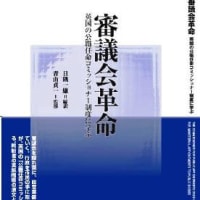
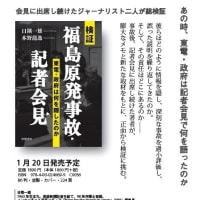
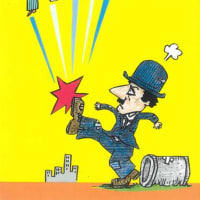
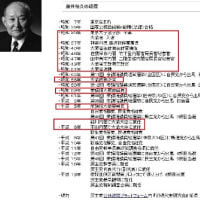
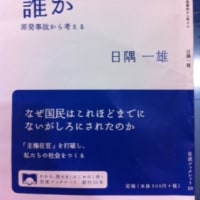
長谷川さんの言われることは女性研究者だけに説得力がありますね。私ら生物・医学分野では数多くの女性研究者がカネのかかる「基礎研究」で頑張っているのに対して,全く評価されていないのが現実です。
まるで日本史を選択する高校生と同じですね(笑) 目先の利益しか考えていない。その結果,国際的に通用しないクズばかり養成していることに全然気付いてないのがこの国の指導者なのです。
↑Kaetzchen様、快調のご様子なによりです。
教育基本法「改正」というのがおかしいのです。
「改悪」です。
笑ってしまうしかない。ははは
子供は飼いならして、
↑最近はペットでも飼いならすって言わないでしょううに、・・・・・
部屋に床の間を作って、
↑なにがしたいねん??????
学校に畳の部屋を、・・・
↑柔道でもしたいんかなぁ??????
こういうことを言うのが国のトップに居るかと思うとナサケナイ、・・・・・・
これからドンドン冬模様。
寒くなります。お体お大事に!
では、また、・・・・・・・
飼い馴らすのはゴキちゃんとか(笑) あれはなかなか可愛いです。←慣れると
# だから最近は「ネットゴキ」と言うことにしています。
ここ2,3日,書いとる記事がどんどん過激になってて,自分でも怖い。要するに次の少女マンガ評論と論文作成が詰まっているストレスのせいなんだけどね。
「改正反対」では意味通じませんよね、やっぱり。
もっと大々的に「教育基本法『改悪』反対!」と、運動すべきでした。
私たちは控え目すぎて、一般大衆へ、アッピールしなかったようです。
仕方がないので,私の詩を。
百時間審議したというが、誰も、なにも知らない。
なにも、報道しないマスコミ。
沈黙の国、日本。
バカばっかり。
個人として、教育基本法改正案に賛成しておりません。
しかし、改正案を総じてすべてダメだと言及するつもりはありません。
ここでもそうですが、多くの反対派ブログでも改悪だとして批判するのですが、みなさんは法案すべてみて全て現行法より劣ると言うのでしょうか?
自分はブログ内でも意見としていますが、改正案は古き教育基本法を部分的に改定し、現代に合致した総合的教育の基本的枠組みの強化を謳っている部分もあります。
そもそも、与党審議の過程にも問題があるし、採決さえも問題であることは否定しえない事実ですが、改正案全てを否定する必要はないと思う。同時にこの批判の中で改正案全て総じて評価して精査しているのか?と疑問に思う。
たとえば、改正案12、13条、6条から11条まで学校教育にかかわる新規条文の大枠などはむしろ現行法では無視されがちだった問題を改めて基本法の形態で法理的に宣言している部分で評価するべきではないだろうか?
個人としてブログ内で記事として取り上げているので宣伝になるかもしれないが、改正案全て悪ではなく、長所をも踏まえて評価してほしいと思うのだが、それほど改正案は全てダメなのだろうか?
現行法がそれほどすばらしいのだろうか?・・・教育現場にいた自分からすれば、現行法の不足を認めない人も理解できないのだが・・・
追記:政権政党の法律案、予算案の中に社会性・人間性が反映しているのは当然です。なぜならば、政権政党は人間の集団だからです。同時に、政権政党を監視、批判していくことが民主主義であり、国民主権ですね。日本国は議会制民主主義ですから、国民政権批判を結集し、監視していく急先鋒が野党となりますし、既存の野党に不満があれば憲法21条によって政治結社に自由が存在し、政治資金規正法上では政党の資格が規定されております。
多くの改正案の評価においてネガティブなものばかりで生涯教育に関する文言(12,13条)などはむしろ、諸種の機関は批判しないだけでなく評価する姿勢を見せていることを認識してほしいのである。
繰り返すが、個人として改正案そのものに反対している。しかし、評価するべき部分を評価しないで一部をとって全て悪いという論調を見ると、どれだけ法案を客観的に評価できているのか?で疑わしいとしか言いようがない
そもそも、多くの批判者は現行法で十分だと言い切れるほど自信があるのだろうか?そこまで踏まえて教育基本法を改定するべきではない、という方向性ではなく、改正案のどこが悪くて、基本法はどうあるべきか?という問題で論議するべきだと思う。
僕は政府が提起してくる予算案・法律案の説明責任はすべて政権与党にあるのであり、政権与党の積極的な説明がマスメディアで報道されない以上は現状維持が妥当だと考えますがどうでしょうか。
むしろ、国民要求の熟している教育問題を解決していくことが政府に求められるのでないでしょうか。高額費の負担軽減とか、学校給食、少人数制学級、不合理な校則の見直し、受験競争の緩和、学歴・学閥制度の廃止等いろいろあります。
では、上記で述べているような改正案の長所を個人とした誰が表記しているでしょうか?政府が表面化しても、「改悪だ、改悪だ」と詳細を見ないで偏見で取り掛かってる人が圧倒的だと言う主張なわけです。
同時に指摘しておきますが、生涯教育が現行法の運用改善で十分対応できるという根拠が現実的にはないでしょう・そもそも、教育基本法は教育の基本的枠組みを構成するものであり、現代の教育において、生涯学習も重要な地位であることは否定できません。それが基本法に盛り込まれていないからこそ問題だといってるわけです。教育に関する基本法規であるこの法において生涯教育の枠組みを改めて制定することになんの問題があるというのでしょうか?その説明なしに現状でいいというのは、理解できません。現状は現行法の時代よりも進化しているわけです。同時に学校教育よりもこれからは生涯学習の枠組みが大きくなると予想されます。(人口比からして当然)
それでも生涯教育の枠組みを基本法に盛り込む必要がないと言い切れるのか?理解できません
>僕は政府が提起してくる予算案・法律案の説明責任はすべて政権与党にあるのであり、政権与党の積極的な説明がマスメディアで報道されない以上は現状維持が妥当だと考えますがどうでしょうか。
説明責任があることは当然でしょうが、マスメディアに報道しないでも情報公開法で漸次的に情報を取るべきでしょう。政府だけに責任を一元化して、監視するべき国民の権利と責務を放置するのは、国民の堕落であり、堕落した国民だからこそ、政治の責任して、自己責任を回避するという衆愚政治の道のりになるでしょう。そこまで主権者である国民は責任があるのですが、そこまでの覚悟がないと政治を語る資格はないでしょう。だからこそ、私は法案一つ一つを精査して、選択するべきものは選択肢、空白を作らないという政治的措置まで行っているわけです。そこまでの責任があるのが民主国家の国民のはずです
>むしろ、国民要求の熟している教育問題を解決していくことが政府に求められるのでないでしょうか。高額費の負担軽減とか、学校給食、少人数制学級、不合理な校則の見直し、受験競争の緩和、学歴・学閥制度の廃止等いろいろあります。
国民の要求が熟しているなどと評価できません。そもそも、どれだけの人の改正案を詳細に煮詰めて言動しているのでしょうか?この中で思案でもいいので、現行法の短所長所踏まえて言動している人がいるでしょうか?同時にそれが教育現場の見解となれるでしょうか?
政府だけが法案提出権利があるわけではなく、事実、民主党草案も評価の対象であるべきことは言うまでもありません。そして、法案一つ一つを精査しない国民こそただ、メディアに煽動されるだけの人間だと思います。そもそも、批判対象である「愛国心」などという記述の問題以外でも多くの問題があるわけです。一つ一つつめないで改悪だ、と叫ぶだけの意見は乱暴だと言う批判は当然でしょう。それを否定できるほど、法案一つ一つを精査し、分析してるのでしょうか?
このブログでもそうですが、問題点を個人の雑感として指摘するだけで教育基本法を終わっています。条文がこうだから、というレベルでどういう問題があるのか?という次元まで述べればまだいい方でしょう。そこまで踏まえて議論するのが、当然だと思います。
そこまでする権利と義務があるからこそ、主権者でもあるし、情報公開が許されているわけですから・・・
現状の法律は「寄らしむべし、知らしむべし」の専門用語で制定され、解釈・運用されているのであります。一般国民に専門用語の法律制定・解釈・運用は必ずしも不要であるのではないでしょうか。野党議員だとか野党の職員は職業的な専門家であるから一般国民への説明責任があるのではないでしょうか。つまり、一般国民が官僚主義の法律の文言解釈を精査しているかどうかが民主主義の問題所在ではないのであり、本来、一般国民の社会規範である生ける法であるはずの法律の文言・解釈・運用が何故、難解を極めているのかが民主主義上の問題の所在ではないでしょうか。
一般国民に現状の官僚主義の法律の精査を要求することは誤りではないでしょうか。もちろん、職業的なプロが法律の文言、制定、解釈、運用を一般国民へわかりやすく説明できないのであれば、そのことこそ指弾されねばならないでしょう。法律という極めて専門的で難解なものを説明する責任は一般国民にはなく、一般国民にあるのは法律の専門家へ説明を要求する権利と義務ではないでしょうか。
要は、国民主権とは法律の職業専門家に対して一般国民が説明責任を追及していくプロセスではないでしょうか。公務員は全体の奉仕者なのであります。司法職も同様です。