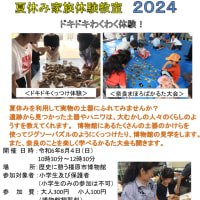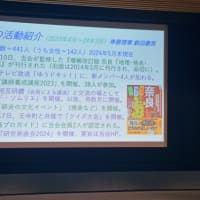明日(5/20)、大神(おおみわ)神社(桜井市三輪1422)で「献麺式」と「三麺交流会」が開催される。正午過ぎには3種類の麺の入った200袋が参拝者に配られる。今朝(5/19)の毎日新聞奈良版《「献麺式」に3市町 集結 あす・大神神社 お互いの繁栄願い》によると、
※トップ写真は、三輪素麺工業協働組合のホームページから拝借
桜井市三輪の大神神社で20日、三輪素麺(そうめん)、出雲そば(島根県出雲市)、讃岐うどん(香川県琴平町)を一緒に献上する「献麺式」と「三麺交流会」が開かれる。3市町の観光協会が企画し、昨年3月の出雲大社での開催に続いて2回目。桜井市観光協会は準備に追われている。
桜井市には日本最古の神社とされる大神神社、出雲市には八百万(やおよろず)の神々が集まるとされる出雲大社、琴平町には「こんぴらさん」の愛称で親しまれる金比羅宮(こんぴらぐう)があり、全国から多くの参拝者が訪れる。
また、桜井では滑らかで歯ごたえのある三輪素麺、出雲では皮ごとひいた風味豊かな出雲そば、琴平では強いこしの讃岐うどんが親しまれてきた。3神社は同じ祭神をまつり、麺の食文化も根付く共通点に観光協会が着目し、観光客にアピールしようと企画した。
当日は午前10時半に、各神社の宮司や3市町の首長ら関係者約30人が大神神社に参拝。持ち寄った袋入りの乾麺を奉納し、互いの末永い繁栄を祈願する。正午過ぎには、3種類の麺や観光パンフレットなどが入った200袋を参拝者らに配る。次回は琴平で開催予定。問い合わせは市観光協会(0744-42-7530)。【山本和良】
三輪素麺は、言わずと知れた日本の麺類のルーツ、いわば「粉もんのルーツ」である。三輪素麺が全国各地へ伝播して、揖保乃糸や小豆島素麺になった。『奈良まほろばソムリエ検定 公式テキストブック』(山と渓谷社刊)によると、
素麺
奈良時代に中国から伝えられた素麺は、中国後漢時代(25~220)の記録にある索餅(さくべい)が原形だという。索餅は索麺(さくめん)や麦縄(むぎなわ)とも呼ばれ、奈良時代の貴族が食べる特別な一品だった。素麺が作られるのは巻向川と初瀬川が流れる三輪山のふもと。かつて、巻向川にはいくつもの水車が回り、小麦をひいていた。夏の食品である素麺は極寒期に作られる。今でも寒風に晒される素麺は真冬の風物詩。
出雲そばは「割子そば」の名前で知られる。『日本大百科全書』の「日本のおもな郷土料理」島根県のところには、
割子そば(わりごそば)
出雲(いずも)そばは割子とよばれる円形の小さい漆器に盛るのでこの名がある。出雲そばは甘皮をつけて挽(ひ)くので、色が黒く香りが強い。これをゆでて割子に入れて重ね、濃いめのつゆを少量かけて食べるのが特徴である。
讃岐うどんは、近年になって大ブームを巻き起こした。『情報・知識 imidas 2016』によると、
讃岐うどん[新語流行語]
讃岐うどんブームが続いている。古くは昭和46年ごろ、最近ではバブル期にもブームがあり、現在は第3次ブームといわれる。讃岐うどんのふるさと香川県では、本場の味を求めて全国から訪れるファンが人気のうどん店を食べ歩きする姿も見られ、マニアの間では、地元のタウン情報誌「TJ KAGAWA」の連載をまとめた「恐るべきさぬきうどん」シリーズ(田尾和俊著、ホットカプセル)がバイブルとなっている。また、従来そば店が多い東京でも、最近は「うどん店」の開業が増えており、「健康的なファストフード」というイメージも手伝って、多くの人気スポットが誕生中。
つまり、日本の麺類のルーツ(三輪素麺)、食べかたと挽きかたに特徴のあるそば(出雲そば)、最近の大ヒット商品(讃岐うどん)が勢揃いするのである。また三社のご祭神がすべて大物主命(おおものぬしのみこと=大国主命)という共通点もある。
皆さん、ぜひ明日の土曜日は大神神社へお参りください!
※トップ写真は、三輪素麺工業協働組合のホームページから拝借
桜井市三輪の大神神社で20日、三輪素麺(そうめん)、出雲そば(島根県出雲市)、讃岐うどん(香川県琴平町)を一緒に献上する「献麺式」と「三麺交流会」が開かれる。3市町の観光協会が企画し、昨年3月の出雲大社での開催に続いて2回目。桜井市観光協会は準備に追われている。
桜井市には日本最古の神社とされる大神神社、出雲市には八百万(やおよろず)の神々が集まるとされる出雲大社、琴平町には「こんぴらさん」の愛称で親しまれる金比羅宮(こんぴらぐう)があり、全国から多くの参拝者が訪れる。
また、桜井では滑らかで歯ごたえのある三輪素麺、出雲では皮ごとひいた風味豊かな出雲そば、琴平では強いこしの讃岐うどんが親しまれてきた。3神社は同じ祭神をまつり、麺の食文化も根付く共通点に観光協会が着目し、観光客にアピールしようと企画した。
当日は午前10時半に、各神社の宮司や3市町の首長ら関係者約30人が大神神社に参拝。持ち寄った袋入りの乾麺を奉納し、互いの末永い繁栄を祈願する。正午過ぎには、3種類の麺や観光パンフレットなどが入った200袋を参拝者らに配る。次回は琴平で開催予定。問い合わせは市観光協会(0744-42-7530)。【山本和良】
三輪素麺は、言わずと知れた日本の麺類のルーツ、いわば「粉もんのルーツ」である。三輪素麺が全国各地へ伝播して、揖保乃糸や小豆島素麺になった。『奈良まほろばソムリエ検定 公式テキストブック』(山と渓谷社刊)によると、
素麺
奈良時代に中国から伝えられた素麺は、中国後漢時代(25~220)の記録にある索餅(さくべい)が原形だという。索餅は索麺(さくめん)や麦縄(むぎなわ)とも呼ばれ、奈良時代の貴族が食べる特別な一品だった。素麺が作られるのは巻向川と初瀬川が流れる三輪山のふもと。かつて、巻向川にはいくつもの水車が回り、小麦をひいていた。夏の食品である素麺は極寒期に作られる。今でも寒風に晒される素麺は真冬の風物詩。
出雲そばは「割子そば」の名前で知られる。『日本大百科全書』の「日本のおもな郷土料理」島根県のところには、
割子そば(わりごそば)
出雲(いずも)そばは割子とよばれる円形の小さい漆器に盛るのでこの名がある。出雲そばは甘皮をつけて挽(ひ)くので、色が黒く香りが強い。これをゆでて割子に入れて重ね、濃いめのつゆを少量かけて食べるのが特徴である。
讃岐うどんは、近年になって大ブームを巻き起こした。『情報・知識 imidas 2016』によると、
讃岐うどん[新語流行語]
讃岐うどんブームが続いている。古くは昭和46年ごろ、最近ではバブル期にもブームがあり、現在は第3次ブームといわれる。讃岐うどんのふるさと香川県では、本場の味を求めて全国から訪れるファンが人気のうどん店を食べ歩きする姿も見られ、マニアの間では、地元のタウン情報誌「TJ KAGAWA」の連載をまとめた「恐るべきさぬきうどん」シリーズ(田尾和俊著、ホットカプセル)がバイブルとなっている。また、従来そば店が多い東京でも、最近は「うどん店」の開業が増えており、「健康的なファストフード」というイメージも手伝って、多くの人気スポットが誕生中。
つまり、日本の麺類のルーツ(三輪素麺)、食べかたと挽きかたに特徴のあるそば(出雲そば)、最近の大ヒット商品(讃岐うどん)が勢揃いするのである。また三社のご祭神がすべて大物主命(おおものぬしのみこと=大国主命)という共通点もある。
皆さん、ぜひ明日の土曜日は大神神社へお参りください!