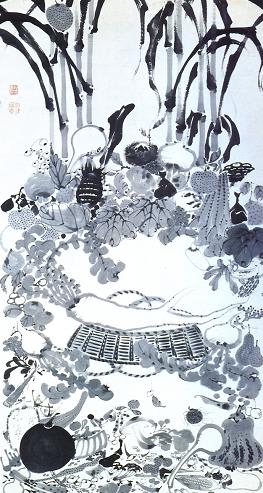レンブラント『机の前のティトゥス』

この少年には、これまで2度、出会ったことがある。
最初はもう十何年も前、大阪の百貨店で開かれた展覧会でのことだ。いろんな画家によるさまざまな肖像画が掛け並べられているコーナーに、少年はいた。
彼はまだ若かったが、父親譲りの豊かな巻き毛におおわれたその顔は憂いにみち、何かを深く考え込むふうだった。両眼を見開いてはいるが、彼には何も見えていないかのようだ。右手にペンを持ち、その手で神妙にあごを支えた姿は、おそらく勉強をしているところなのかもしれないけれど、ただそれだけとも思えなかった。
キャンバスのなかでポーズを作ったり、ぼくたちに向かって嫣然と微笑んだり、たくさんの肖像画が並んでいるなかで、この絵が放つオーラには独特のものがあった。少年がティトゥスという名であることも、かのレンブラントの息子であることも、まだよく知らなかったが、観る者をつかんで離さない、何か切々たる声がそこから聞こえてくるのだった。
同行していた友人に、この絵は抜きん出ているね、と耳打ちすると、一も二もなく同意され、やはり本当にいい絵というのは誰の心にも響くものだ、と感じたりした。この絵が専門家によっても高く評価され、レンブラントの代表作のひとつとされていることを知ったのは、ずっと後のことである。
***
その日から10年近く経ったころだろうか、レンブラントの大規模な展覧会が京都で開かれ、そこでティトゥスとの再会を果たした。ぼくはもう、彼の生い立ちと短かった生涯について、いくばくかの知識があった。
レンブラントの前半生は、画家として望み得るかぎりの成功に彩られていた。彼の肖像画は評価が高まり、多くのパトロンに気に入られ、大邸宅を構えることができた。妻に迎えた美貌のサスキアは資産家の娘で、自由になる金銭はいくらでもあった。彼らは文字どおり、富と名声をほしいままにできたのである。
ただ、ふたりの間に生まれた子供はみな早世してしまった。たったひとり生き残ったのが、ここに描かれたティトゥスだったのだ。彼が生まれた翌年、レンブラントは畢生の大作『夜警』を描き上げるが、サスキアは30歳で世を去ってしまう。
このときを境に、流行画家としての華やかな生活が、失意と窮乏と日々へと一変した。愛人問題で裁判沙汰となり、借金はたちまちふくれあがり、ついには邸宅も売らねばならなくなる。『机の前のティトゥス』が描かれたのは、まさにそんなときだった。この少年が、うら若いひたいに眉根を寄せ、深刻そうな表情で描かれているのも、理由のないことではないのである。
***
この絵から13年後、レンブラントの最後の望みだったひとり息子ティトゥスも、若くして死んでしまった。天涯孤独の身となったレンブラントは、日々おいぼれゆく自分の顔を見つめ、キャンバスにとどめる。世の中でもっとも素晴らしい自画像のいくつかは、不甲斐ないみずからの姿を赤裸々に描き出した、レンブラント最晩年のものだろう。すべてを失ったかつての巨匠には、絵を描くことしか残されていなかったのだ。
ティトゥスの後を追うように、レンブラントも世を去った。自画像では80歳ぐらいの老人に見えるが、彼はまだ63歳だった。
(ボイマンス・ファン・ビューニンゲン美術館蔵)
五十点美術館 No.7を読む

この少年には、これまで2度、出会ったことがある。
最初はもう十何年も前、大阪の百貨店で開かれた展覧会でのことだ。いろんな画家によるさまざまな肖像画が掛け並べられているコーナーに、少年はいた。
彼はまだ若かったが、父親譲りの豊かな巻き毛におおわれたその顔は憂いにみち、何かを深く考え込むふうだった。両眼を見開いてはいるが、彼には何も見えていないかのようだ。右手にペンを持ち、その手で神妙にあごを支えた姿は、おそらく勉強をしているところなのかもしれないけれど、ただそれだけとも思えなかった。
キャンバスのなかでポーズを作ったり、ぼくたちに向かって嫣然と微笑んだり、たくさんの肖像画が並んでいるなかで、この絵が放つオーラには独特のものがあった。少年がティトゥスという名であることも、かのレンブラントの息子であることも、まだよく知らなかったが、観る者をつかんで離さない、何か切々たる声がそこから聞こえてくるのだった。
同行していた友人に、この絵は抜きん出ているね、と耳打ちすると、一も二もなく同意され、やはり本当にいい絵というのは誰の心にも響くものだ、と感じたりした。この絵が専門家によっても高く評価され、レンブラントの代表作のひとつとされていることを知ったのは、ずっと後のことである。
***
その日から10年近く経ったころだろうか、レンブラントの大規模な展覧会が京都で開かれ、そこでティトゥスとの再会を果たした。ぼくはもう、彼の生い立ちと短かった生涯について、いくばくかの知識があった。
レンブラントの前半生は、画家として望み得るかぎりの成功に彩られていた。彼の肖像画は評価が高まり、多くのパトロンに気に入られ、大邸宅を構えることができた。妻に迎えた美貌のサスキアは資産家の娘で、自由になる金銭はいくらでもあった。彼らは文字どおり、富と名声をほしいままにできたのである。
ただ、ふたりの間に生まれた子供はみな早世してしまった。たったひとり生き残ったのが、ここに描かれたティトゥスだったのだ。彼が生まれた翌年、レンブラントは畢生の大作『夜警』を描き上げるが、サスキアは30歳で世を去ってしまう。
このときを境に、流行画家としての華やかな生活が、失意と窮乏と日々へと一変した。愛人問題で裁判沙汰となり、借金はたちまちふくれあがり、ついには邸宅も売らねばならなくなる。『机の前のティトゥス』が描かれたのは、まさにそんなときだった。この少年が、うら若いひたいに眉根を寄せ、深刻そうな表情で描かれているのも、理由のないことではないのである。
***
この絵から13年後、レンブラントの最後の望みだったひとり息子ティトゥスも、若くして死んでしまった。天涯孤独の身となったレンブラントは、日々おいぼれゆく自分の顔を見つめ、キャンバスにとどめる。世の中でもっとも素晴らしい自画像のいくつかは、不甲斐ないみずからの姿を赤裸々に描き出した、レンブラント最晩年のものだろう。すべてを失ったかつての巨匠には、絵を描くことしか残されていなかったのだ。
ティトゥスの後を追うように、レンブラントも世を去った。自画像では80歳ぐらいの老人に見えるが、彼はまだ63歳だった。
(ボイマンス・ファン・ビューニンゲン美術館蔵)
五十点美術館 No.7を読む