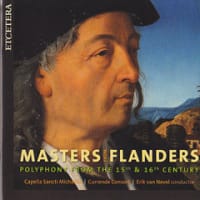イタリア軍団が去った前週末、ようやく自分の時間がとれて、国立劇場に行き人形浄瑠璃(文楽)を見物した。出しものは近松門左衛門作の『心中宵庚申』(享保七年=1722年初演)。演者は、序幕の「上田村の段」が竹本住大夫と野沢錦糸、続く「八百屋の段」が豊竹嶋大夫と竹沢宗助。物語は、大坂の大きな八百屋が舞台で、姑と嫁の肌が合わず、養子・半兵衛が妻・千代とともに心中するにいたる顛末を描いた心理劇。
ここで人形浄瑠璃をほとんど観たことがないという人のために少し説明しておくと、人形浄瑠璃も歌舞伎も江戸時代以前にさかのぼる芸能だが、もともと物語性が強かったのは人形浄瑠璃で、こちらは江戸時代にはいってから人形芝居というジャンルとして確立され、近松門左衛門をはじめとするすぐれた台本作者が出現するにいたる。これに対し歌舞伎は、歌と踊りを中心とするレビュー的な芸能というのが本来の姿で、芝居(演劇)とはなかなか結びつかなかった。それが、近松門左衛門が出現した頃から、人形浄瑠璃のすぐれた台本をそのまま取り入れ、人間による芝居へと変様していく。つまり、「歌舞伎=江戸時代の演劇」という一般的な図式は必ずしも正確とはいえないわけで、この『心中宵庚申』も、歌舞伎に取り入れられて人間によって演じられることもあるが、人形浄瑠璃の方がオリジナルのかたちだ。
しかしいずれにしても台本が同じなのだから、人形が演じようと人間が演じようと、同じ演目から受ける印象にはたいした違いがないのではないかというと、これがものすごく違うのである。
端的にいうと、生身の人間が演じる歌舞伎はものすごくダイナミックかつリアリスティックなのに対し、人形浄瑠璃の印象は非常に象徴的。ただ歌舞伎の場合、等身大のリアルさを強調し、観客をぐいぐい舞台に引きつけようとするとき、ある瞬間なにか急に現実に引き戻されて、舞台がリアルであればあるほど芝居が本質的にもつ虚構性が目立ち、芝居からはじきだされるように感じるときがなくはないのだが、はじめからあるリアルさを捨てている人形浄瑠璃は、どうせこれは虚の世界で行われているのだとおもって安心してみているうちに、いわば「虚の真」といったものにぐいっと引き込まれることがある。そんなとき、人形浄瑠璃の力は、歌舞伎以上に強い。
当ブログで少し前に使用した表現をつかえば(5月9日「欲望を開きつつ閉じ込める」)、人形浄瑠璃のおもしろさは、薄い肌着をとおして人間の肉体を想像する楽しみに似ているともいえる。生身の肉体はその印象が強烈な一方でわれわれの感覚を裏切る(=文字どおり、肌に合わない)こともままあるが、肌着には、直接性がない分、こうじゃなかったはずだと感覚が裏切られることもない。想像のなかで、われわれは最初から最後まで、ずっと理想の肉体を想像し続けることができる。
さて、住大夫(人間国宝)と錦糸の「上田村の段」は、そんな人形浄瑠璃の根源性にふれたような快演で、余分な表現はすべてはぶいて、聴き手を物語のなかにぐんぐん引きずり込んでいく。少し前まで、イタリア人の視覚から人間の身体性と人体模型の違いについていろいろ考えていた私は、ここに、その問題に対する強烈な問題提起が行われていることに気づき、灯台もと暗しだったと驚愕した。
続く「八百屋の段」は、嶋大夫と宗助のコンビが演じるのだが、私は以前から嶋大夫のビロードのような美声が大好きで、「夏も来て、青物見世に水乾く」という最初の詞書から、舞台にすっぽりとはまってしまった。
ところでこの「八百屋の段」は、最後に夫婦が死を決意して家を出るところで「地獄へ落ちるか極楽か、末は白茶の死に装束」といった詞書があるのだが、ものすごいリアルな場面のなかに「末は知らない」と「白茶」の掛詞が優雅に顔を出すといったほとんどアクロバットのようなレトリックが、嶋大夫で聴いているととても美しくておもわずはっとさせられる。なにか、感覚が空中に放り出されたような、そんな極上の浮遊観を味わった。
なお今回の人形浄瑠璃鑑賞は、知人のはからいで、芝居がはじまる前に楽屋と舞台裏を見せてもらい、人形にも直に触らせてもらった。こんな体験イタリア人たちにもさせてやりたかったと、スケジュール調整がうまくいかなかったことがとても悔やまれた。
ここで人形浄瑠璃をほとんど観たことがないという人のために少し説明しておくと、人形浄瑠璃も歌舞伎も江戸時代以前にさかのぼる芸能だが、もともと物語性が強かったのは人形浄瑠璃で、こちらは江戸時代にはいってから人形芝居というジャンルとして確立され、近松門左衛門をはじめとするすぐれた台本作者が出現するにいたる。これに対し歌舞伎は、歌と踊りを中心とするレビュー的な芸能というのが本来の姿で、芝居(演劇)とはなかなか結びつかなかった。それが、近松門左衛門が出現した頃から、人形浄瑠璃のすぐれた台本をそのまま取り入れ、人間による芝居へと変様していく。つまり、「歌舞伎=江戸時代の演劇」という一般的な図式は必ずしも正確とはいえないわけで、この『心中宵庚申』も、歌舞伎に取り入れられて人間によって演じられることもあるが、人形浄瑠璃の方がオリジナルのかたちだ。
しかしいずれにしても台本が同じなのだから、人形が演じようと人間が演じようと、同じ演目から受ける印象にはたいした違いがないのではないかというと、これがものすごく違うのである。
端的にいうと、生身の人間が演じる歌舞伎はものすごくダイナミックかつリアリスティックなのに対し、人形浄瑠璃の印象は非常に象徴的。ただ歌舞伎の場合、等身大のリアルさを強調し、観客をぐいぐい舞台に引きつけようとするとき、ある瞬間なにか急に現実に引き戻されて、舞台がリアルであればあるほど芝居が本質的にもつ虚構性が目立ち、芝居からはじきだされるように感じるときがなくはないのだが、はじめからあるリアルさを捨てている人形浄瑠璃は、どうせこれは虚の世界で行われているのだとおもって安心してみているうちに、いわば「虚の真」といったものにぐいっと引き込まれることがある。そんなとき、人形浄瑠璃の力は、歌舞伎以上に強い。
当ブログで少し前に使用した表現をつかえば(5月9日「欲望を開きつつ閉じ込める」)、人形浄瑠璃のおもしろさは、薄い肌着をとおして人間の肉体を想像する楽しみに似ているともいえる。生身の肉体はその印象が強烈な一方でわれわれの感覚を裏切る(=文字どおり、肌に合わない)こともままあるが、肌着には、直接性がない分、こうじゃなかったはずだと感覚が裏切られることもない。想像のなかで、われわれは最初から最後まで、ずっと理想の肉体を想像し続けることができる。
さて、住大夫(人間国宝)と錦糸の「上田村の段」は、そんな人形浄瑠璃の根源性にふれたような快演で、余分な表現はすべてはぶいて、聴き手を物語のなかにぐんぐん引きずり込んでいく。少し前まで、イタリア人の視覚から人間の身体性と人体模型の違いについていろいろ考えていた私は、ここに、その問題に対する強烈な問題提起が行われていることに気づき、灯台もと暗しだったと驚愕した。
続く「八百屋の段」は、嶋大夫と宗助のコンビが演じるのだが、私は以前から嶋大夫のビロードのような美声が大好きで、「夏も来て、青物見世に水乾く」という最初の詞書から、舞台にすっぽりとはまってしまった。
ところでこの「八百屋の段」は、最後に夫婦が死を決意して家を出るところで「地獄へ落ちるか極楽か、末は白茶の死に装束」といった詞書があるのだが、ものすごいリアルな場面のなかに「末は知らない」と「白茶」の掛詞が優雅に顔を出すといったほとんどアクロバットのようなレトリックが、嶋大夫で聴いているととても美しくておもわずはっとさせられる。なにか、感覚が空中に放り出されたような、そんな極上の浮遊観を味わった。
なお今回の人形浄瑠璃鑑賞は、知人のはからいで、芝居がはじまる前に楽屋と舞台裏を見せてもらい、人形にも直に触らせてもらった。こんな体験イタリア人たちにもさせてやりたかったと、スケジュール調整がうまくいかなかったことがとても悔やまれた。