バッハの『無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータ』は、バイオリン弾きにとっては特別な曲である。パルティータ第二番のシャコンヌは「バッハが一生にこの一曲だけを作ったとしても大作曲家と呼ばれるだろう」といわれるほどの名曲であるが、演奏は当時のほかのバイオリン曲と比べても極端に難しい。バイオリンは伴奏を伴って厚みを出すべき楽器だという概念を見事に打ち崩しただけならまだかわいいもので、完璧な和声と対位法を駆使してバイオリン演奏の極限にまで迫っていくうちに、バイオリン一本で宇宙を奏でるかのような壮大な音楽が結晶しているのだ。
だから古今のバイオリニストたちはこの曲を演奏するときにはことさら、気合を入れることになり、名盤も多い。
なかでも有名なのは、外面の体裁をかなぐり捨てて音楽の確信へと迫るかのような鬼気迫るヨーゼフ・シゲティの演奏と、バイオリンの響きを最大限生かしてまるでパイプオルガンのように響かせながら聖なる響きへと昇華させたヘンリク・シェリングの演奏だ。ほかにも線は細いながらピンと張り詰めたナタン・ミルシテイン、古楽器の軽やかさを生かしきったポッジャーの演奏など名演に事欠かない。
今回、タワーレコードとソニーの共同企画で実現したのがシェリングの旧盤の復刻である。
後年のシェリングと比べると、音楽への情熱を感じさせる音楽である。まだ30代の若い演奏であるせいかもしれない。ちょうどニューヨークでの演奏会が大成功を収めてアルトゥール・ルービンシュタインの目に留まったころで演奏家としては、やや遅めの国際舞台への登場を果たしたころだ。
バイオリンはドイツの名バイオリニストで名教師であるカール・フレッシュに師事する。その後、パリでナディア・ブーランジェに師事する。
シェリングはユダヤ系のポーランド人なので、第二次世界大戦中は例によってナチスに追われることになる。ポーランド亡命政府の通訳や慰問演奏を重ねるうちに慰問先のメキシコの大学に職を得る。
この経歴からも分かるように、特定の国の強い伝統のもとにある音楽家ではない。彼は常に異国の地で、自分の感受性とは異なる音楽に触れ、それを昇華しながら取り込んでいった。
その結果、彼の演奏は「これほどうまい演奏は聴いたことがない。だが誰の演奏かは分からない」と揶揄されるほど個性的とは言い難いものとなった。良くも悪くもそれがシェリングの持ち味である。
シェリングの場合、そこに知性が出現する。
理知的であること、論理的であることは、他者と何を共有可能なのかを考え抜くことにある。「感性」は共有できない。私たちはどこに何を感じても、感じた瞬間それは「私の」感性となるからだ。いま目の前に厳然としてある客観にのみ立脚することで、より多くの人と共有できる芸術を作り上げる。シェリングはそう考えたのではあるまいか。
37歳で録音された旧盤の「無伴奏」を聴くと、それ単体ではなるほど他の演奏家の演奏よりは「理知的」である。しかし彼はここに満足しなかった。まだ、この演奏にはシェリングの「私」が表現されているからだ。シェリングはバッハの音楽に共感し、それを音にしようとしながら、ギリギリの客観性を保とうとしている。そこに瑞々しい気品が生み出される。
シェリングの新盤を聞くと、ここからさらにシェリングの感受性をそぎ落としていったことが分かる。バッハを弾くということは、シェリングを聞かせることではない。シェリングはそうした音楽にさらに磨き上げていったのだろう。そこには堂々としたバッハの音楽が立ち現れる……このようなバッハをシェリング以外のだれが表現しえるだろう? ここには確かに確固たるシェリングの個性が表現されるのである。
ここに「個性」とはなにかという問への、1つのはっきりとした答えが現れる。
個性とは、個をそぎ落として言った後に見えてくる個なのだ。
日本の教育の場面で「個性を大切にする」といったときに、多くの場合、子どもたちの感受性を保護し、傷つかないようにすることを意味するようになった。そこにはシェリングのような、個をそぎ落としていく作業はどこにも現れない。そこに出現するのは、お互いの自尊心を傷つけないようにし、それを「空気を読む」というような脆弱な個性の群れだ。
シェリングが頑固一徹に貫いてきた精神に学ぶべきものは、「個性」が氾濫する現代には大変多いだろう。
だから古今のバイオリニストたちはこの曲を演奏するときにはことさら、気合を入れることになり、名盤も多い。
なかでも有名なのは、外面の体裁をかなぐり捨てて音楽の確信へと迫るかのような鬼気迫るヨーゼフ・シゲティの演奏と、バイオリンの響きを最大限生かしてまるでパイプオルガンのように響かせながら聖なる響きへと昇華させたヘンリク・シェリングの演奏だ。ほかにも線は細いながらピンと張り詰めたナタン・ミルシテイン、古楽器の軽やかさを生かしきったポッジャーの演奏など名演に事欠かない。
今回、タワーレコードとソニーの共同企画で実現したのがシェリングの旧盤の復刻である。
後年のシェリングと比べると、音楽への情熱を感じさせる音楽である。まだ30代の若い演奏であるせいかもしれない。ちょうどニューヨークでの演奏会が大成功を収めてアルトゥール・ルービンシュタインの目に留まったころで演奏家としては、やや遅めの国際舞台への登場を果たしたころだ。
バイオリンはドイツの名バイオリニストで名教師であるカール・フレッシュに師事する。その後、パリでナディア・ブーランジェに師事する。
シェリングはユダヤ系のポーランド人なので、第二次世界大戦中は例によってナチスに追われることになる。ポーランド亡命政府の通訳や慰問演奏を重ねるうちに慰問先のメキシコの大学に職を得る。
この経歴からも分かるように、特定の国の強い伝統のもとにある音楽家ではない。彼は常に異国の地で、自分の感受性とは異なる音楽に触れ、それを昇華しながら取り込んでいった。
その結果、彼の演奏は「これほどうまい演奏は聴いたことがない。だが誰の演奏かは分からない」と揶揄されるほど個性的とは言い難いものとなった。良くも悪くもそれがシェリングの持ち味である。
シェリングの場合、そこに知性が出現する。
理知的であること、論理的であることは、他者と何を共有可能なのかを考え抜くことにある。「感性」は共有できない。私たちはどこに何を感じても、感じた瞬間それは「私の」感性となるからだ。いま目の前に厳然としてある客観にのみ立脚することで、より多くの人と共有できる芸術を作り上げる。シェリングはそう考えたのではあるまいか。
37歳で録音された旧盤の「無伴奏」を聴くと、それ単体ではなるほど他の演奏家の演奏よりは「理知的」である。しかし彼はここに満足しなかった。まだ、この演奏にはシェリングの「私」が表現されているからだ。シェリングはバッハの音楽に共感し、それを音にしようとしながら、ギリギリの客観性を保とうとしている。そこに瑞々しい気品が生み出される。
シェリングの新盤を聞くと、ここからさらにシェリングの感受性をそぎ落としていったことが分かる。バッハを弾くということは、シェリングを聞かせることではない。シェリングはそうした音楽にさらに磨き上げていったのだろう。そこには堂々としたバッハの音楽が立ち現れる……このようなバッハをシェリング以外のだれが表現しえるだろう? ここには確かに確固たるシェリングの個性が表現されるのである。
ここに「個性」とはなにかという問への、1つのはっきりとした答えが現れる。
個性とは、個をそぎ落として言った後に見えてくる個なのだ。
日本の教育の場面で「個性を大切にする」といったときに、多くの場合、子どもたちの感受性を保護し、傷つかないようにすることを意味するようになった。そこにはシェリングのような、個をそぎ落としていく作業はどこにも現れない。そこに出現するのは、お互いの自尊心を傷つけないようにし、それを「空気を読む」というような脆弱な個性の群れだ。
シェリングが頑固一徹に貫いてきた精神に学ぶべきものは、「個性」が氾濫する現代には大変多いだろう。












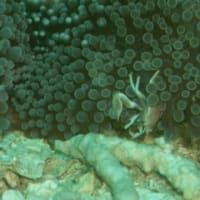







ところで、シェリングのバッハ無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータは私もよく聞きます(玉野さんが言及しておられる新版[=グラモフォン版])。シェリングの演奏、これまで私はユダヤ性ということをあまり考えたことがなかったのですが、指摘されてみればなるほどという感じで、ユダヤ性が強いのかもしれませんね。こうした音楽演奏におけるユダヤ性ということ、私も自分のブログでちょっと考えたことがあります。
つまり、(ゲイ同様)ユダヤ人も一般社会からの迫害、抑圧を強くうけてきた人たちなわけですが、するとユダヤ人演奏家の音楽演奏というのは、主観性の強い、自分の情念をストレートにうったえかけてくるようなものになるかというと、かならずしもそうじゃないんですね。ワルター、クレンペラー、セルといった人たちの演奏は、ものすごく客観的というか、ある種の職人技に通ずるようなものを私は感じます(シェリングもそうしたタイプの演奏家だと私はおもいます)。問題は、ではなぜそうなるのかということなんですが、唐突ながら私は、伏見憲明さんの『欲望問題』にそれに対するこたえを垣間見たような気がしました。つまり、「人は差別をなくすためだけに生きるのではない」ということですね。あるいは、社会に対して「差別」をうったえかけようとおもったら、ある客観性がいるんじゃないかということです。この本のすごいところは、だから、差別の状況を自分に即して強い調子で書いていることじゃなくて(この本は、そういうタイプの本では全然ありませんよね)、差別を客観化、相対化しようとしてるところじゃないかとおもうんです。
シェリングの演奏から問題はどんどんそれていきますけど、ゲイの社会運動といった場合も、それが「社会運動」であろうとするからには、はたらきかけられる側の社会による受容、あるいは調停者の存在ということ、やはり意識すべきなんじゃないでしょうか。
たまたまそんなことを考えていたので、玉野さんのこの記事はすごく刺激的でした。
もっとも、ユダヤ人の演奏というのをあまり簡単にひとくくりにしてしまうと、バーンスタインは違うじゃないかとか、いろいろ反論もありそうなので、そこでまたちょっと考えてはいるんですが…。