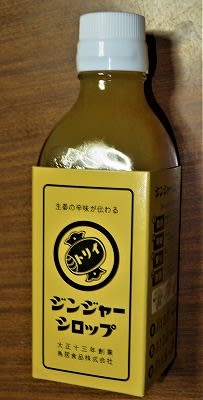最近、わが家の入口付近の道路や駐車場や畑に小さな糞が落ちていることがたびたびある。意外に目立つ所にあるので致し方なく犬のウンコのようにスコップですくって畑に肥やしとして捨てている。糞のなかには柿やギンナンの種が混ざっているのも特徴だ。
そうすると、ハクビシンの可能性が高いがまだ本人にはお目にかかってはいない。目立つ所に糞をするのでオイラはイタチ説をとっている。でも、柿を食べるのだろうか、木に登るのだろうかと疑問の迷宮が襲う。ぐーたら当局に聞くと、秘密保護法を盾に教えてくれない。最近の当局は情報を改竄してしまう恐れもあるから始末が悪い。

同じ糞でも違う動物のような気がするのが畑のとなりにあった。こちらは十月上旬のことだったが植物性の細かい消化物が目立つ。そこにウラナミシジミが訪れていた。蝶が糞に集まる行為は、どうやら糞の乾いた所にあるナトリウムやアンモニアの成分を口吻先で感知し自分の体液で溶かしたうえで摂取するらしい。しかもそれはオスのみの行為だという。
さて、この糞の犯人は誰なのだろうか。近所の人も玄関先で糞をされ、頭が黒いタヌキかアナグマを見た気がするという。いずれにしても餌が少ない寒さの中、家と畑を徘徊する魑魅魍魎(チミモウリョウ)がいるのは確かなことだ。糞をまき散らすのは故意なのか、間に合わなかったのか、縄張りのサインなのか、弁護士を含む肩書の好きな有識者で構成された第三者委員会において、犯人の行為はいやがらせなのか、「未必の故意」なのかどうかの調査をなんとなく始めた!?