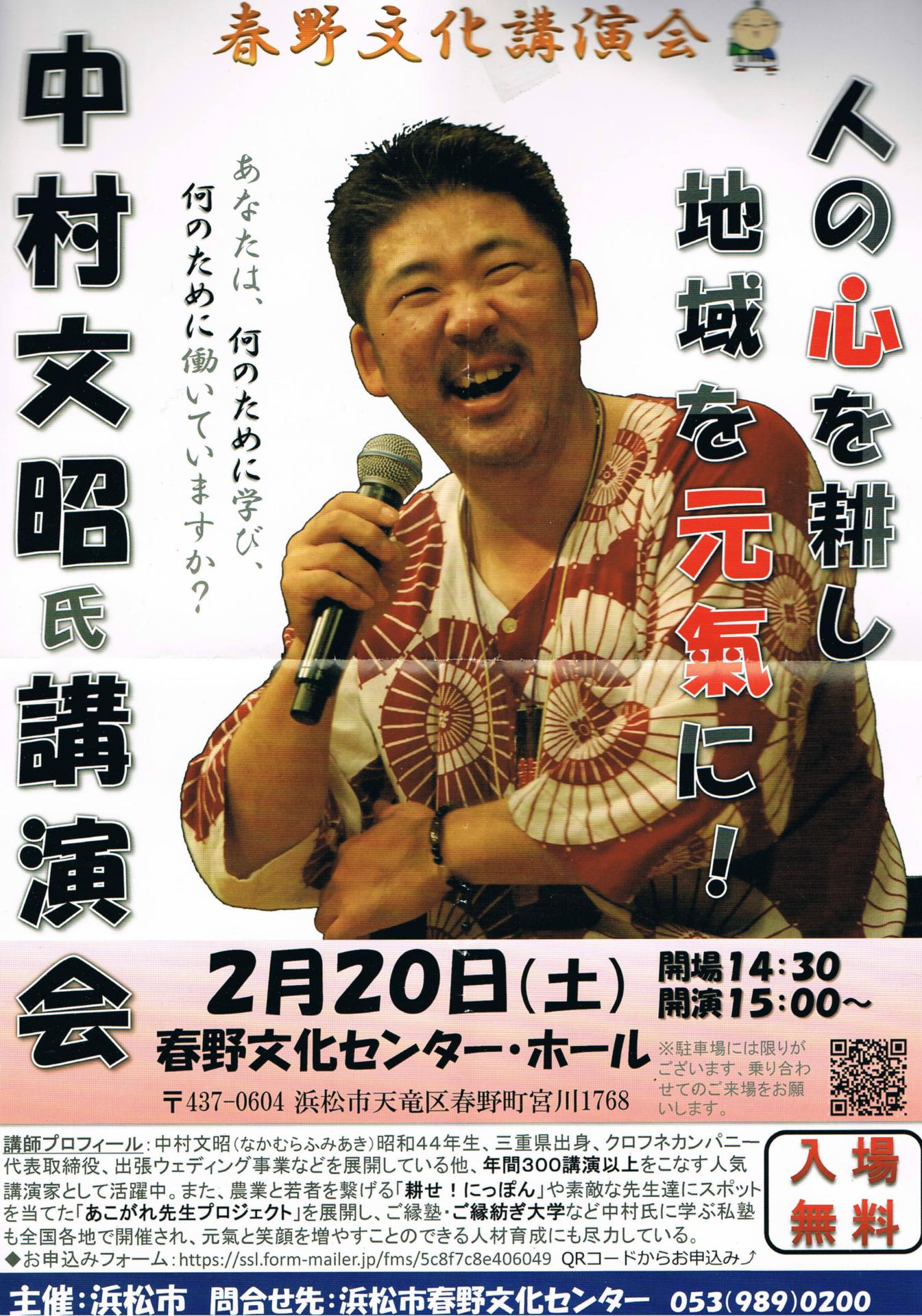昨年は、和宮様の入院、書架の完成、新たな出会い、森林散策会の発展、多品目の野菜栽培等々ドラマチックな年となった。
同時に、オイラも時代もいつのまにか古希を迎えてしまった。
世界はテロの頻発、格差社会の拡大など今までの歴史とは違う段階に入った。
先進国日本の発展はわからなくもないが、人間性の解体過程も同時に進行している。
花森安治の言葉。
「美しいことについての 感覚のまるでないひとたちが、
日本の政治や経済を 動かしているところに、
いまの世の中の不幸がある。」

こうした混沌のなかで何に向かって生きていくか、何をアイテムに自分を生かしていくのか、を確かめる今年が始まる。
初詣も行かない、「紅白」もバラエティも見ない静けさがいい。
みんなと同化しない、同質にならないのが大切な時代。
玄関前で生け花もどきの、オンリーワンのパフォーマンスを楽しむ。
同時に、オイラも時代もいつのまにか古希を迎えてしまった。
世界はテロの頻発、格差社会の拡大など今までの歴史とは違う段階に入った。
先進国日本の発展はわからなくもないが、人間性の解体過程も同時に進行している。
花森安治の言葉。
「美しいことについての 感覚のまるでないひとたちが、
日本の政治や経済を 動かしているところに、
いまの世の中の不幸がある。」

こうした混沌のなかで何に向かって生きていくか、何をアイテムに自分を生かしていくのか、を確かめる今年が始まる。
初詣も行かない、「紅白」もバラエティも見ない静けさがいい。
みんなと同化しない、同質にならないのが大切な時代。
玄関前で生け花もどきの、オンリーワンのパフォーマンスを楽しむ。