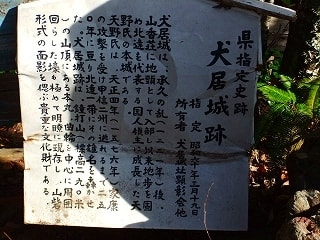遠州光明寺跡地のてっぺんからの眺望は素晴らしい。 天竜川やアクトタワーも見られた。保存会の人が道や草刈等をやることで、藪の状態からこれだけの見晴らしができるようになったということだ。 ここは同時に戦国時代は山城だったので、にらみを利かした場所でもあったわけだ。 右の大木がタラヨウ。

この階段を登りきるときっと光明時の本殿が迫力を持って見えてきたのであろう。 しかしいまや、廃墟のせつなさが漂っている。

石塔らしきものもあちこち散在しているがまともなものはこれくらいだった。 これもきっと、常夜灯なのだろうけど、火袋の部分が欠落している気がする。 弘化3年(1846年)、名古屋の人が奉納したものだ。

痕跡を探していると、小さな小屋の中に木造が見えた。 荒削りだが、いつごろのものだろうか。

よく見ないと、この小屋にある木造の存在もわからない。 江戸幕府スタートの慶長8年(1603年)には、徳川将軍家の祈願所となり、その後ずっと保護を受けていたほどの大きな寺であったらしい。
人間の営みのはかなさをまわりの樹木が癒してくれている気がした。 タラヨウの見事な大木が往時を静かに伝えてくれている。