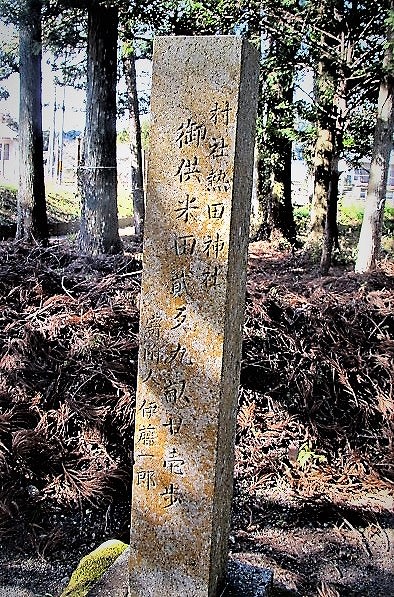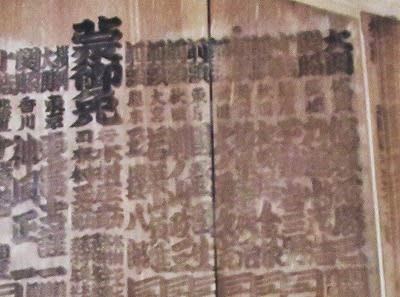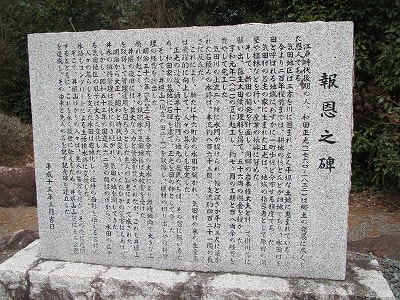縣居神社の隣は、立派な「浜松市立賀茂真淵記念館」があった。
退職校長らしき学芸員さんがつきっきりで説明してくれた。
実に丁寧でよどみない説明に頭が下がる。
ただ、入館者がずっとオイラ一人だけだった現実が気になる。

真淵の功績は、従来の仏教・儒教などの外来の思想を排し、日本固有の精神のありようを「万葉集」などの古典から提起したものだ。
古代から明治までその外来思想の影響は庶民の生活まで貫徹していたといっても過言ではない。
その中で、朱子学の封建的な教えを否定し作為のない自然の心情・態度を唱えたのは、日本のルネッサンスと言ってもよい出来事だった。
しかも、江戸幕府の政権の中枢にまで招聘されるほどだった。

弟子の本居宣長との出会いも戦前の教科書に掲載されるほどだった。
真淵は万葉集の凛とした「ますらおぶり」、宣長は女性的で自由な「たをやめぶり」にこだわり、閉塞的な建て前社会に一石を投じた。
しかしながら、幕末の尊王攘夷運動や戦前の軍国主義に利用されてしまった。

真淵や宣長の業績に比肩する改革者は現代にいるのだろうか。
国学は破綻したのだろうか。
少なくとも、いまの神道のていたらくの現状からは何も生まれないが、戦前と現代の過誤を見つめた中から新しい「まごころ」イズムが生まれても不思議ではない。
この記念館や内山真龍資料館は民間に委ねて、新しいコンセプトと複合施設にしていく発想を持たないと、天下りの受け皿に堕したり赤字予算を生む元凶になる。
先人の偉業を生かすには現代に連動したイノベーションが必要だ。
最近の博物館・水族館・動物園の斬新さに頭の固い教育委員会は学ぶべきだとぶつぶつ言いながら帰路に就く。
退職校長らしき学芸員さんがつきっきりで説明してくれた。
実に丁寧でよどみない説明に頭が下がる。
ただ、入館者がずっとオイラ一人だけだった現実が気になる。

真淵の功績は、従来の仏教・儒教などの外来の思想を排し、日本固有の精神のありようを「万葉集」などの古典から提起したものだ。
古代から明治までその外来思想の影響は庶民の生活まで貫徹していたといっても過言ではない。
その中で、朱子学の封建的な教えを否定し作為のない自然の心情・態度を唱えたのは、日本のルネッサンスと言ってもよい出来事だった。
しかも、江戸幕府の政権の中枢にまで招聘されるほどだった。

弟子の本居宣長との出会いも戦前の教科書に掲載されるほどだった。
真淵は万葉集の凛とした「ますらおぶり」、宣長は女性的で自由な「たをやめぶり」にこだわり、閉塞的な建て前社会に一石を投じた。
しかしながら、幕末の尊王攘夷運動や戦前の軍国主義に利用されてしまった。

真淵や宣長の業績に比肩する改革者は現代にいるのだろうか。
国学は破綻したのだろうか。
少なくとも、いまの神道のていたらくの現状からは何も生まれないが、戦前と現代の過誤を見つめた中から新しい「まごころ」イズムが生まれても不思議ではない。
この記念館や内山真龍資料館は民間に委ねて、新しいコンセプトと複合施設にしていく発想を持たないと、天下りの受け皿に堕したり赤字予算を生む元凶になる。
先人の偉業を生かすには現代に連動したイノベーションが必要だ。
最近の博物館・水族館・動物園の斬新さに頭の固い教育委員会は学ぶべきだとぶつぶつ言いながら帰路に就く。