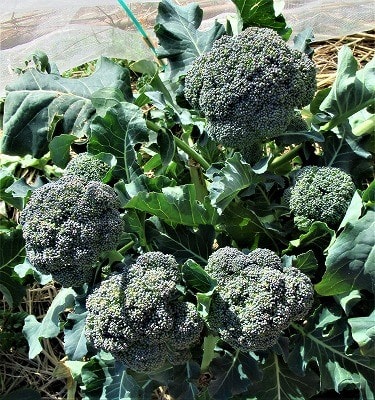種が古かったせいか、成長が危なかった「クウシンサイ」がやっと元気になってきた。今までの経験から「初心者の期待の星・空芯菜だから」と安心していたが、やっと本来の生命力あふれる伸びやかさを見せ始めてくれた。また、間引きをしていなかった「ニンジン」も、期待に応えて伸びやかな姿を見せてくれた。一時畑からの調達ができなくなって購入していたが、いよいよ常連となって復帰。葉っぱもジュースの一員となった。

わが畑の今の旬は「インゲン」だ。2~3日毎に収穫している。ちょっと収穫が遅れると太目になってしまう。生で食べてみても結構いける。初期は根っこ側に実が多くできるので坐りながら収穫するのがキツイのが難点。

そして、きょうの昼飯はパクチー入りの焼きうどんだった。いよいよ「パクチー」の初登場だ。和宮様も「パクチーが焼うどんとピッタリ合う食材であるぞな」と感激する。畑で採れたインゲンも仲間入り。夕飯はパクチー入りのサラダとする。これにも絶賛の和宮様であった。




























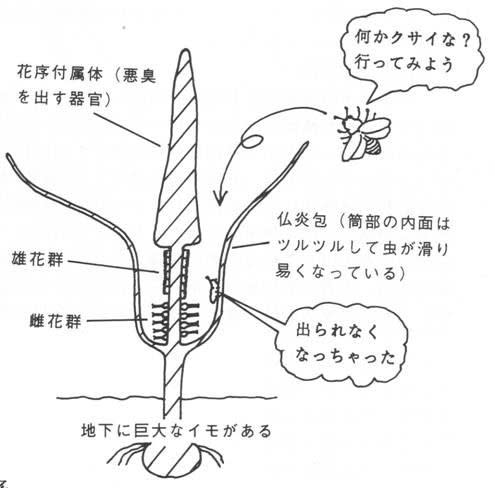 「
「