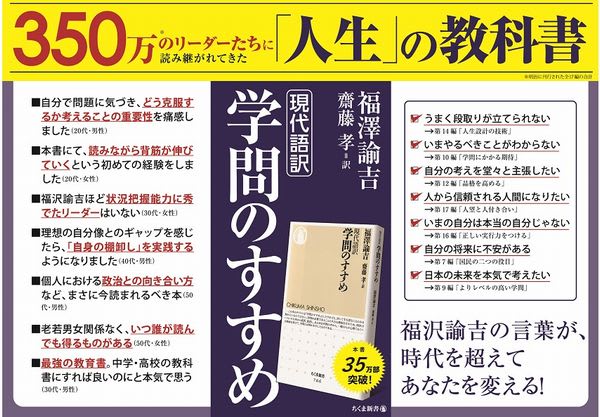🌸『贈与論』
☆私自身、すぐ忘れますが,書いている時
*間違かも知れませんが、それなりに少し理解出来ているつもりです?
☆経済原則を超える『贈与』行為のインパクト
*自らを与えること、他者を受け入れることも必要
*贈与でもたらされる、双方への影響力を意識するのも必要
☆著者、マルセル・モース
⛳著者『贈与論』モースプロフィール
☆モースは、フランスのロレーヌに生まれた
*自らを与えること、他者を受け入れることも必要
*贈与でもたらされる、双方への影響力を意識するのも必要
☆著者、マルセル・モース
⛳著者『贈与論』モースプロフィール
☆モースは、フランスのロレーヌに生まれた
*統計データの初期社会学に定式化したデユルケームの甥
*モースは、ボルドー大学時代から叔父に師事
*デユルケームの方法で研究を進める
☆フランス社会学派の中心的位置で業績を重ねる
☆師の死後『社会学年報』を主導
☆フランス社会学派の中心的位置で業績を重ねる
☆師の死後『社会学年報』を主導
☆社会学年報に『贈与論』発表
*アルカイックな社会における交換の形態と理由
⛳『贈与論』の関連する現代社会の実際の光景
☆若いAは、生活費や学費を稼ぐため夜はバーで働いていた
*父親ほどの歳の男性Bが、A目当てに通ってくる
*Bは金を落とし、ブランド品の贈り物などをくれることある
*Bは金を落とし、ブランド品の贈り物などをくれることある
*AはBがタイプではなかった
*Aは、給料と割り切ってやっている
*店でBと話すのは仕事だと思い笑顔を絶やさなかった
*Aは、店を出れば何の拘束もないと思っていた
*しかし、Bの要求の中で、Aはノーと言えない自分を感じる
☆若いAに道を誤らせそうな社会的な背景
*謎の力は一体何か?
☆それに答えるのが『贈与論』だ
⛳『贈与論』の概要
☆『贈与論』は、サブタイトルで「交換」と言う
*『贈与』は贈り物だが、物々交換ではない
☆交換や購入に際し、我々は品物のよし悪しを見る
*物をもらう場合、くれた人の人品の軽重も測ろうとする
☆贈与と交換を同じ言葉のように並べること
*モースは、これらは現実にはグラデーションをなしていると述べる
(グラデーション、段階的変化)
*中間的なさまざまな「形態」で現れると考えた
☆経済活動も、Aを支配する謎の力も根っこには同じ「理由」
☆現代社会では、個人間の『贈与』以外
☆現代社会では、個人間の『贈与』以外
*マーケティング手段として物をくれたりする
*気づけば消費者として囲い込まれたりもする
☆『贈与』が双方の関係性に影響を与える場合
*「A」たる私たち「理由」をひもとくには本書が必要
*「A」たる私たち「理由」をひもとくには本書が必要
⛳「贈与論」では「贈与=ギフト」の役割や社会的影響を述べている
☆ 様々な文化圏に残る伝統的な習慣で『贈与に』3つの義務が残っている
☆伝統的な『贈与』では
*贈る、受け取る、返すが義務として生じる
☆物には、「金銭的価値」だけでなく「精神的価値」もある
*『贈与』は、精神的コミュニケーションである
*『贈与』は、物々交換や現代の経済活動とは別のもの
☆現代の経済循環においても
*「精神的価値」を意識することが大切
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
⛳出典、『世界の古典』
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
⛳出典、『世界の古典』


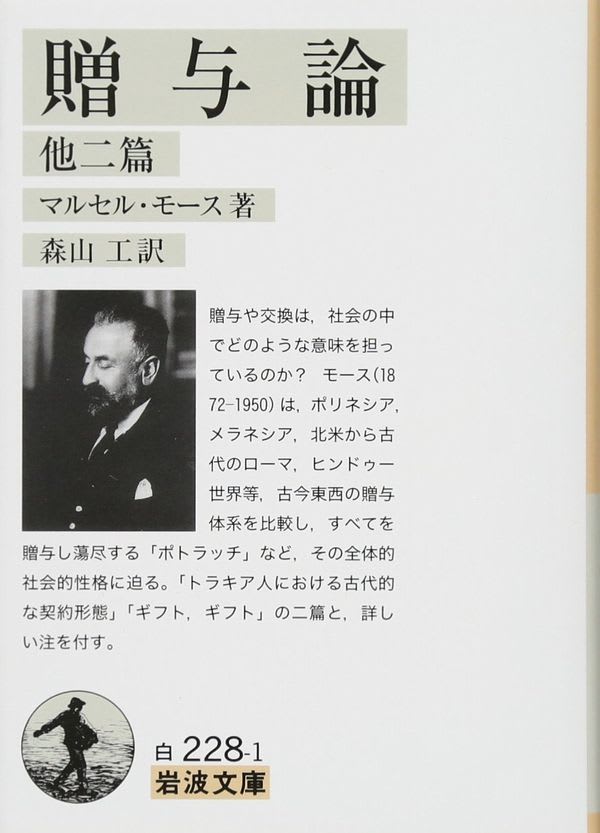

『贈与論』4(世の中の仕組みを俯瞰する)
(ネットより画像引用)