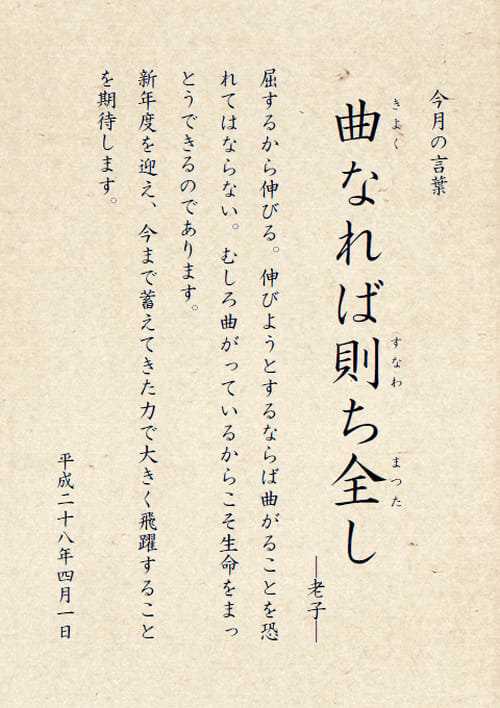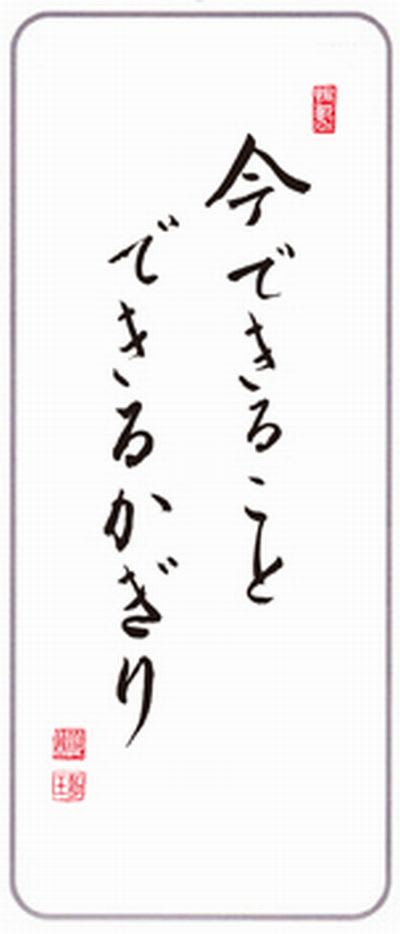真田 昌幸(戦国時代きっての知将・謀将と評価されている)
真田 昌幸(戦国時代きっての知将・謀将と評価されている) 上司(武田信玄→勝頼→織田信長→北条氏直→上杉景勝→豊臣秀吉→秀頼→徳川家康)
上司(武田信玄→勝頼→織田信長→北条氏直→上杉景勝→豊臣秀吉→秀頼→徳川家康) 子供(男):信之、信繁(幸村)、信勝、昌親他
子供(男):信之、信繁(幸村)、信勝、昌親他 子供(女):娘(真田幸政室)、娘(鎌原重春室)、娘(保科正光室)他2名
子供(女):娘(真田幸政室)、娘(鎌原重春室)、娘(保科正光室)他2名 真田幸村の父『この親(昌幸)してこの子あり(幸村)』
真田幸村の父『この親(昌幸)してこの子あり(幸村)』 BS11(尾上松也さんの古地図で謎解き!)の番組参考&引用
BS11(尾上松也さんの古地図で謎解き!)の番組参考&引用






街角とお寺より
真田昌幸(尾上松也さんの古地図で謎解き番組他引用)
 真田 昌幸
真田 昌幸 戦国時代から江戸時代初期にかけての武将・大名
戦国時代から江戸時代初期にかけての武将・大名 武田信玄・勝頼に仕え、武田氏滅亡後に自立した
武田信玄・勝頼に仕え、武田氏滅亡後に自立した 織田信長の軍門に降り、滝川一益の与力となった
織田信長の軍門に降り、滝川一益の与力となった 本能寺の変後に再び自立して、豊臣政権下において所領を安堵された
本能寺の変後に再び自立して、豊臣政権下において所領を安堵された 上田合戦で2度にわたって徳川軍を撃退した
上田合戦で2度にわたって徳川軍を撃退した 関ヶ原の戦いで西軍につき、敗れたので改易された
関ヶ原の戦いで西軍につき、敗れたので改易された 昌幸の上司武田信玄の時代
昌幸の上司武田信玄の時代 甲斐武田家への人質として7歳で甲斐国へ下り、武田信玄の奥近習衆に加わった
甲斐武田家への人質として7歳で甲斐国へ下り、武田信玄の奥近習衆に加わった 信玄は、昌幸の才能を早くから見抜き、寵愛した(武田二十四将)
信玄は、昌幸の才能を早くから見抜き、寵愛した(武田二十四将) 父と兄弟3人が武田二十四将に数えられるような家は真田家だけである
父と兄弟3人が武田二十四将に数えられるような家は真田家だけである 武藤家の養子となり、足軽大将に任じられた
武藤家の養子となり、足軽大将に任じられた 昌幸の上司武田勝頼の時代
昌幸の上司武田勝頼の時代 信玄の病死により家督を継いだ武田勝頼に仕えた
信玄の病死により家督を継いだ武田勝頼に仕えた 長篠の戦いで、真田信綱、次兄昌輝が討死したため、昌幸は真田氏に復して家督を相続した
長篠の戦いで、真田信綱、次兄昌輝が討死したため、昌幸は真田氏に復して家督を相続した 織田信長・徳川家康連合軍による甲州征伐が開始され、本格的な武田領国への侵攻が行われた
織田信長・徳川家康連合軍による甲州征伐が開始され、本格的な武田領国への侵攻が行われた 昌幸の上司織田信長と信長の死後
昌幸の上司織田信長と信長の死後 武田氏滅亡後、昌幸は織田信長の家臣となって本領を安堵された
武田氏滅亡後、昌幸は織田信長の家臣となって本領を安堵された 織田氏に従属してから僅か3ヶ月後本能寺の変で信長が横死する
織田氏に従属してから僅か3ヶ月後本能寺の変で信長が横死する 甲斐・信濃の旧武田領は無主とり、、徳川家康・上杉景勝・北条氏直らが熾烈な争奪戦を繰り広げた
甲斐・信濃の旧武田領は無主とり、、徳川家康・上杉景勝・北条氏直らが熾烈な争奪戦を繰り広げた 昌幸もこの好機を見逃さず、旧武田家臣の取り込みを策した
昌幸もこの好機を見逃さず、旧武田家臣の取り込みを策した 昌幸の上司北条氏直&上杉景勝時代
昌幸の上司北条氏直&上杉景勝時代 北条氏直が上野に侵攻し、滝川一益が破れ上野も無主になる
北条氏直が上野に侵攻し、滝川一益が破れ上野も無主になる 昌幸は、上杉景勝に臣従したが、次に北条氏直にも臣従した
昌幸は、上杉景勝に臣従したが、次に北条氏直にも臣従した 北条氏との同盟を選択した家康は、氏直に和睦の条件として沼田領を譲渡するという条件を出した
北条氏との同盟を選択した家康は、氏直に和睦の条件として沼田領を譲渡するという条件を出した 昌幸は、沼田割譲について反発し、徳川・北条と敵対していた越後の上杉景勝に臣従する
昌幸は、沼田割譲について反発し、徳川・北条と敵対していた越後の上杉景勝に臣従する 徳川・北条連合と対立する上杉・羽柴ブロックへの参加
徳川・北条連合と対立する上杉・羽柴ブロックへの参加 昌幸、徳川家康との対立
昌幸、徳川家康との対立 昌幸は、上杉氏に対する千曲川領域を抑える城が必要になり、徳川家康が上田城建築
昌幸は、上杉氏に対する千曲川領域を抑える城が必要になり、徳川家康が上田城建築 家康は、北条氏直から和議の条件の履行を迫られたため、昌幸に対し沼田領を北条氏に引き渡すように求めた
家康は、北条氏直から和議の条件の履行を迫られたため、昌幸に対し沼田領を北条氏に引き渡すように求めた 昌幸は、引き渡しに応じないと拒否し、徳川軍の侵攻に備えて、次男の信繁を人質にして上杉景勝に従属する
昌幸は、引き渡しに応じないと拒否し、徳川軍の侵攻に備えて、次男の信繁を人質にして上杉景勝に従属する 徳川家康と北条氏直は、約7,000の兵力で昌幸の居城・上田城・沼田城に侵攻した
徳川家康と北条氏直は、約7,000の兵力で昌幸の居城・上田城・沼田城に侵攻した 昌幸は、2,000の兵力で、徳川連合軍大勝利する
昌幸は、2,000の兵力で、徳川連合軍大勝利する 昌幸は、武田の旧臣から信濃の独立勢力(大名)として豊臣系大名の間で認知されることになった
昌幸は、武田の旧臣から信濃の独立勢力(大名)として豊臣系大名の間で認知されることになった 昌幸の上司豊臣秀吉時代
昌幸の上司豊臣秀吉時代 次男の信繁を、盟主である豊臣秀吉の人質として大坂に出仕し豊臣家に臣従した
次男の信繁を、盟主である豊臣秀吉の人質として大坂に出仕し豊臣家に臣従した 秀吉の命令で、昌幸は家康の与力大名となった
秀吉の命令で、昌幸は家康の与力大名となった 北条氏の小田原征伐では、昌幸は秀吉・石田三成らと相互に情報交換を繰り返している
北条氏の小田原征伐では、昌幸は秀吉・石田三成らと相互に情報交換を繰り返している 秀吉軍に、上野の北条家の属城を次々と落とし、北条家が降伏する
秀吉軍に、上野の北条家の属城を次々と落とし、北条家が降伏する 家康は関東に移され、関東の周囲には豊臣系大名が配置されて家康の牽制を担った
家康は関東に移され、関東の周囲には豊臣系大名が配置されて家康の牽制を担った 昌幸は、秀吉から旧領を安堵され、同じく家康牽制の一端を担った
昌幸は、秀吉から旧領を安堵され、同じく家康牽制の一端を担った 昌幸と関ヶ原合戦
昌幸と関ヶ原合戦 秀吉死後の豊臣政権においては、五大老筆頭の家康が台頭し影響力を強めた、
秀吉死後の豊臣政権においては、五大老筆頭の家康が台頭し影響力を強めた、 徳川秀忠約38,000の部隊を、昌幸は2,000兵力で上田城に篭城して迎え撃った(第二次上田合戦)
徳川秀忠約38,000の部隊を、昌幸は2,000兵力で上田城に篭城して迎え撃った(第二次上田合戦) 徳川秀忠は城攻めに手を焼いて小諸に撤退した
徳川秀忠は城攻めに手を焼いて小諸に撤退した 徳川秀忠軍、利根川の増水で、関ヶ原の戦に遅参した(上田合戦は本戦遅参の原因ではない)
徳川秀忠軍、利根川の増水で、関ヶ原の戦に遅参した(上田合戦は本戦遅参の原因ではない) 関ケ原の戦で、西軍は徳川軍に敗れた
関ケ原の戦で、西軍は徳川軍に敗れた 昌幸の配流
昌幸の配流 関ヶ原の戦後処理で、徳川家康より昌幸・信繁父子には上田領没収と死罪が下される
関ヶ原の戦後処理で、徳川家康より昌幸・信繁父子には上田領没収と死罪が下される 東軍に属した長男の信之の助命嘆願で助命され、高野山への蟄居が決められた
東軍に属した長男の信之の助命嘆願で助命され、高野山への蟄居が決められた 信濃上田の真田領に関しては、長男の信之に与えられ、約10石を領する大名となる
信濃上田の真田領に関しては、長男の信之に与えられ、約10石を領する大名となる 昌幸の最期
昌幸の最期 流人生活は昌幸の気力を萎えさせた
流人生活は昌幸の気力を萎えさせた 晩年の昌幸は病気がちだで、配流生活は年老いた昌幸を苦しめた
晩年の昌幸は病気がちだで、配流生活は年老いた昌幸を苦しめた 昌幸、九度山で病死(享年67歳)
昌幸、九度山で病死(享年67歳)