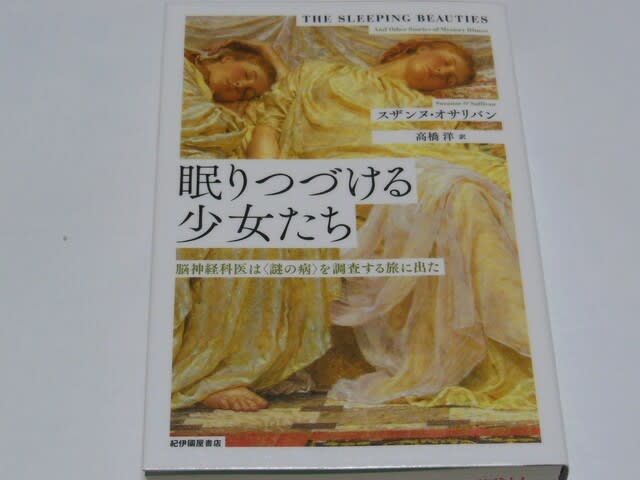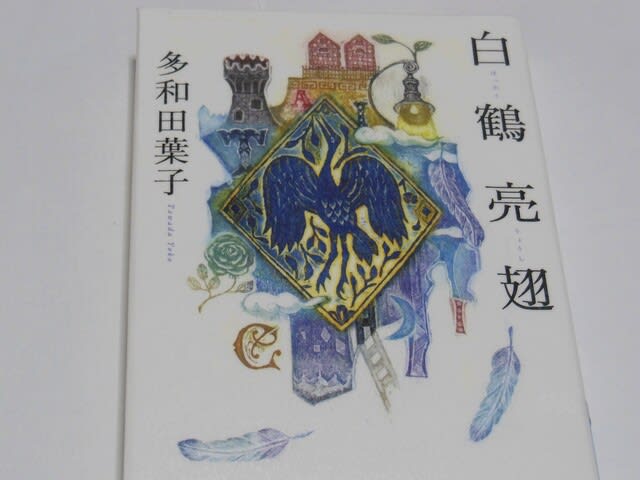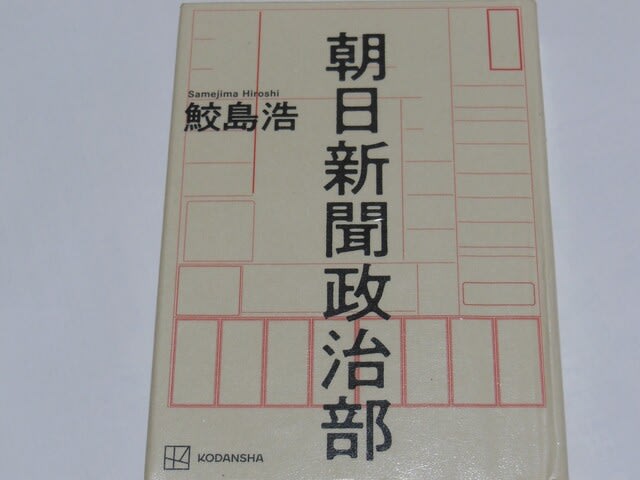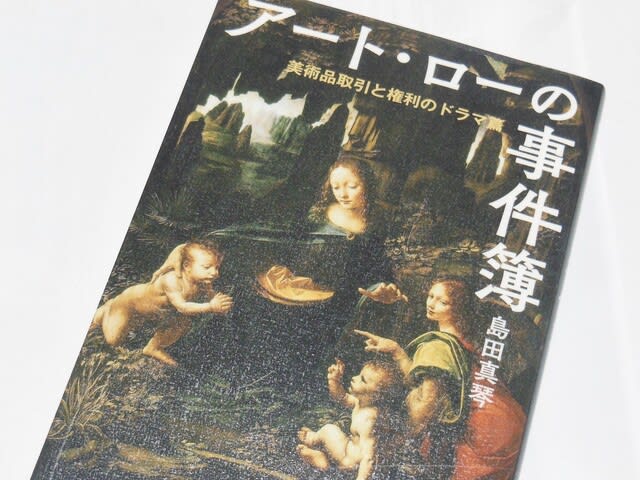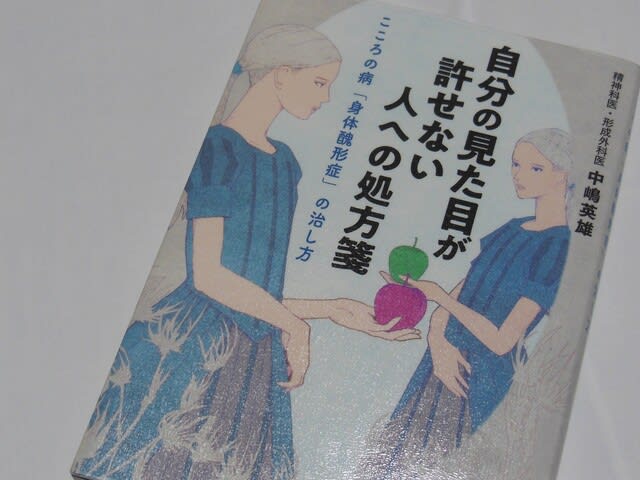世界各地で発生したさまざまな検査を行ったが検査上異常値が見いだせない原因不明の集団的な昏睡等について、神経科医である著者が現地を訪れる等して得た知見に基づいて、それらの症状について論じた本。
著者が序章で「謎の病」として採り上げ第1章で「眠りつづける少女たち」と題して紹介しているスウェーデンの難民申請中の子どもに発症した「あきらめ症候群」と名付けられた昏睡症状は、難民申請手続が遅滞する状況に家族が直面したときに生じ始め(30ページ)、難民申請が通り将来の生活に希望が持てるようになると回復する(42ページ)とされています。そうなると、検査で異常が発見できないことも併せて、世間からは仮病・詐病疑惑の目を向けられることになります。著者はこれらの身体症状が心の影響によるものとしつつ、詐病ではなくリアルな身体症状であること(長期間の昏睡状態等、意図してそれを装いつづけることはできない)を繰り返し述べています。
人間の体は頻繁に些細なゆらぎ、動悸や痛み、めまいなどを生じているが、健康なときは脳はそれを正常なものとして無視している。しかし、身体に過度の注意を向け、それらの雑音に何らかの病的な兆候を探し始め、また何らかの異常があると認定されると、それらは症状と化し、うずきや痛みに気がつき始めると心配になりそのためにさらに注意が向けられ、特定の病気と疑うとその病気らしい兆候に注意を払うこととなり、悪循環を生じる(195~201ページ、389~392ページ)、異常(発作)を予期することで異常の兆候を探し、結果として予期通りになる(373ページ、401ページ等)というような機序で、機能性(心因性)のリアルな身体症状が生じるというのです。
集団ヒステリーなどと言われ詐病を疑われた人々とそれを支援する者たちは、何らかの身体的な異常の検出を期待して検査をつづけ、その一環として専門家である著者を呼ぶ。しかし著者は機能性(心因性)のものだと評価をする。著者は機能性(心因性)だから詐病ということではなく、重篤な身体症状はある、その原因は個人の心理よりもむしろ文化的・社会的なものと捉えるべきというのですが、患者たちは失望するということが繰り返されています。著者のような考え方・主張が世の大勢を占めるようになれば問題は解決に向かうのでしょうけれども、それはなかなかに困難に思えます。
眠り病という紹介もあるので、私は、子どもの頃に習ったツェツェバエが媒介する寄生虫によるアフリカの難病の話かと思って読み始めたのですが、そちらのことはまったく扱われていませんでした。もちろん、いばら姫の話もまったく…

原題:THE SLEEPING BEAUTIES : And Other Stories of Mystery Illness
スザンヌ・オサリバン 訳:高橋洋
紀伊國屋書店 2023年5月10日発行(原書は2021年)
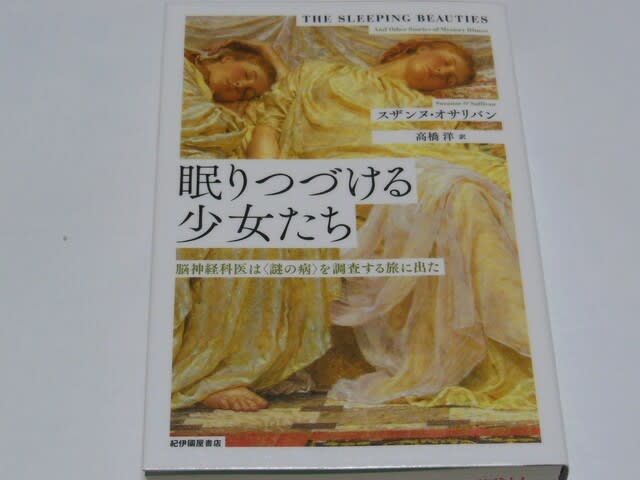
著者が序章で「謎の病」として採り上げ第1章で「眠りつづける少女たち」と題して紹介しているスウェーデンの難民申請中の子どもに発症した「あきらめ症候群」と名付けられた昏睡症状は、難民申請手続が遅滞する状況に家族が直面したときに生じ始め(30ページ)、難民申請が通り将来の生活に希望が持てるようになると回復する(42ページ)とされています。そうなると、検査で異常が発見できないことも併せて、世間からは仮病・詐病疑惑の目を向けられることになります。著者はこれらの身体症状が心の影響によるものとしつつ、詐病ではなくリアルな身体症状であること(長期間の昏睡状態等、意図してそれを装いつづけることはできない)を繰り返し述べています。
人間の体は頻繁に些細なゆらぎ、動悸や痛み、めまいなどを生じているが、健康なときは脳はそれを正常なものとして無視している。しかし、身体に過度の注意を向け、それらの雑音に何らかの病的な兆候を探し始め、また何らかの異常があると認定されると、それらは症状と化し、うずきや痛みに気がつき始めると心配になりそのためにさらに注意が向けられ、特定の病気と疑うとその病気らしい兆候に注意を払うこととなり、悪循環を生じる(195~201ページ、389~392ページ)、異常(発作)を予期することで異常の兆候を探し、結果として予期通りになる(373ページ、401ページ等)というような機序で、機能性(心因性)のリアルな身体症状が生じるというのです。
集団ヒステリーなどと言われ詐病を疑われた人々とそれを支援する者たちは、何らかの身体的な異常の検出を期待して検査をつづけ、その一環として専門家である著者を呼ぶ。しかし著者は機能性(心因性)のものだと評価をする。著者は機能性(心因性)だから詐病ということではなく、重篤な身体症状はある、その原因は個人の心理よりもむしろ文化的・社会的なものと捉えるべきというのですが、患者たちは失望するということが繰り返されています。著者のような考え方・主張が世の大勢を占めるようになれば問題は解決に向かうのでしょうけれども、それはなかなかに困難に思えます。
眠り病という紹介もあるので、私は、子どもの頃に習ったツェツェバエが媒介する寄生虫によるアフリカの難病の話かと思って読み始めたのですが、そちらのことはまったく扱われていませんでした。もちろん、いばら姫の話もまったく…

原題:THE SLEEPING BEAUTIES : And Other Stories of Mystery Illness
スザンヌ・オサリバン 訳:高橋洋
紀伊國屋書店 2023年5月10日発行(原書は2021年)