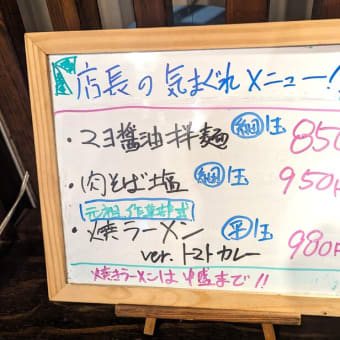五木の子守唄 熊本県民謡 The Lullaby of Itsuki
この曲、知っている人も多いと思いますが、改めて…。
「子守歌」って、お母さんだけが歌ってきたものじゃないんだな、と改めて。
(いわゆる「子守歌」の他に、「守り子歌」というのがあって、この曲は後者です)
かつての日本には、「子守奉公」というのがあって、貧しい家庭の女の子は、「口減らし」で、よそに出されていたと言われています。
ここに出ている女の子が「子守奉公」で、この曲に出てくるような子だと思われます。
民謡なので、どれが正解というわけではないですが、戦後になって出されたのがこの歌詞です。
この歌詞がとてもとても重く、悲しいんです。
1 おどま盆ぎり盆ぎり
盆から先ゃおらんと
盆が早(はよ)くりゃ早もどる
2 おどまかんじんかんじん
あん人たちゃよか衆(し)
よか衆よか帯 よか着物(きもん)
3 おどんがうっ死(ち)んちゅうて
誰(だい)が泣(に)ゃてくりゅか
裏の松山蝉が鳴く
4 蝉じゃごんせぬ
妹(いもと)でござる
妹泣くなよ 気にかかる
5 おどんがうっ死んだら
道ばちゃいけろ
通る人ごち花あぎゅう
6 花はなんの花
つんつん椿
水は天からもらい水
引用元はこちら(とても詳しい解説付き)
*「おどま」は「私たち」で、「おどん(おいどん)」は、「わたし」のこと。
*「かんじん(勧進)」は、「小作人」「乞食」「物乞い」のこと。
3で、「私が死んだところで、誰が泣いてくれるだろうか。蝉だけは泣いてくれるだろう」と歌いつつも、
4では、「でも、泣いているのは、蝉じゃなくて、おぶっている妹のほうで。泣くなよ」、と歌うんです。
そして、5で、「私が死んだら、道ばたに埋めて。通る人が花を供えてくれるから」、と。
…
これを「子守歌」と呼んでよいのか分かりませんが、当時の日本の守り子の心情が伝わってきます。
先日、「石井のおとうさんありがとう」という本を読みました。
石井十次さんの物語です。
親に育ててもらえない「孤児」を集めて、「孤児院」を日本で初めて作った人です。
この本の世界とも通じる「五木の子守歌」。
五木の子守歌は、とても重たく悲しさのある曲ですが、どこか「強さ」も感じます。
この「強さ」がなんなのかは分かりませんが、「生命的な強さ」のようにも思います。
…
子どもたちって、弱い存在でもあるけれど、強い存在でもあるんです。
大人とは違う世界を生きていて、そこでたくましく生きることができるんです。
「水は天からもらい水」という最後のフレーズに、そんな子どもの強さを感じます。
YouTubeに、この曲の色々なバージョンが出ているので、是非聴いてもらいたいですね。
三橋美智也さんの歌とオーケストラ風のアレンジがとても綺麗です。
解説付き。ギターで奏でるこの曲も本当に心に響きます。
歌詞も違う五木の子守歌。こちらもよく知られています。