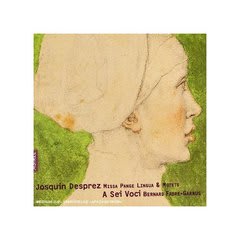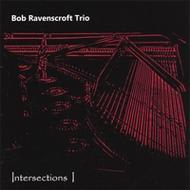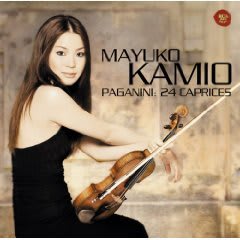今日、ヤマテツさんがつぶやきにアップしていた「演奏家のいない演奏会」に行ってきました。
素晴らしい天気だったので、カミさんの誘いもあり香雪美術館に細川護熙 陶と書を観に行く予定でしたが
できれば波動スピーカーの試聴もしたかったので、こちらのほうにしてもらいました。
しかし、当日の申し込みだったので席が取れるかわからなかったのですが、
幸いにも席が取れたので西宮北口にある会場に直行しました。
偶然と言うよりもやっぱりという表現がぴったりだと思いますが、ヤマテツさん御夫妻もいらっしゃっておりました。
簡単なご挨拶を済ませていよいよ開演の時間になりました。
会場は「スタインウェイ関西ミニホール」です。
第1部は「演奏家のいない演奏会」
第2部は「長谷川美沙Piano Recital」
というプログラムでしたが、ほとんどが長谷川美沙さんの紹介とプログラムに使われている作曲家と演目の説明でした。
演奏家自身が事前に演目の背景にある思いや作曲家に対する見解を説明しながらのお話も興味深かったです。
このミニホールはホームページの説明にもあるように、客席数36でスタインウェイのセミコンサートグランドC型(奥行227cm)
が置かれています。予想以上に狭い印象でした。


背面には音響ポールが作り付けで設置されておりました。

当然ながらステージの両手にも配置されており、とても響きの多いホールのように感じられました。

最初に少し波動スピーカーを聴きましたがホールの残響の多さの為か定位が曖昧で無指向性のスピーカーを聴いているような
錯覚をおぼえました。
キャスリーンバトルのカーネギーホールコンサートのCDを最後に聴かせて頂きましたが、左前方の上の方からボーカルが聴こえてきて少し違和感のある再生でした。
演目は
最初に長谷川美沙さんの最近のフェイバリットである、マイケルジャクソン の ユーアーノットアローンと
映画「シンドラーのリスト」を聴かせて頂きました。
次にこれからが本番ですが
アストラ・ピアソラから
オブリピオン
ブエノスアイレスの四季より「冬」
リベルタンゴの3曲
ヨハネス・ブラームスから
2つのラプソディ Op.79
セザール・フランクから
前奏曲、フーガと変奏曲
フランツ・リストから
巡礼の年第3年「エステ荘の噴水」
愛の夢-3つのノクターンより第3番「おお、愛しうる限り愛せ」
最後はルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーベンから
ピアノソナタ第8番「悲愴」
以上でした。
クラシックに詳しくない私にとっては、第1部で長谷川さんから聞いた
曲が書かれた背景や演奏家・作曲家の思いがどうであったかなどの説明が
非常に参考になりとても解り易かったですね。
演奏の方も比較的やさしいサロン的なものだと勝手に想像しておりましたが、
演奏が始まるや否やその想像が木っ端微塵に砕かれました。
女性らしからぬダイナミックなタッチでぐいぐい迫ってくる演奏には圧倒されました。
クラシックの演奏会にはほとんど行ったことがないので全くの私感として聞いて頂ければと思いますが
上手い下手は素人の私には解りませんが普段CDなどで聴いている演奏とは全く違ったもので
こんなに気合の入った演奏とは思いませんでした。
ただ、一つ残念だったことは演奏のスケールにホールのエアボリュームが付いて行っていない様に感じられました。
特にブラームスまではタッチの強さがより強調された感じで聴こえ、
放射された音が飽和状態になり歪ぎりぎりの音でとても抜けの悪い状態でした。
ちょうどピアノの共鳴板の中に頭を突っ込んで聴いているような感じで、
頭上から音が降ってくるようにホール全体に充満しています。
これは、ホールトーンとは程遠い直接音の洪水です。
ピアノとの距離が近いことの影響ではなくホール全体のエアボリュームの不足ではないかと思いました。
ずぶの素人が本格的に設計されたであろうホールの批判をしているのですから何と大それた行為でしょう。
設計者が見ていると怒り心頭でしょうね。
しかし、このように聴こえたのは事実でしたから何とかしてもらえないでしょうかねぇ!
その反面、微妙なタッチが手に取るように解り、ハンマーが弦を叩いた後に空間に広がっていく様も鮮明に聴こえてきます。
オーディオよりオーディオ的な再生音ですね。(変な表現ですね、生演奏ですから。)
西梅田のヒルトンホテルの夕暮れのサロン・クラシックなどとは全く違う音と演奏で
クラシックと言えども色々な聴こえ方があるということも大きな発見でした。
兎に角、今日は今迄に体験したことがないような音を演奏会で聴けた事と、
ホールと演奏内容とのマッチングの大切さも初めて体験できて非常に内容の濃い演奏会でした。
また、このような機会があれば積極的に参加しようと思いました。
素晴らしい天気だったので、カミさんの誘いもあり香雪美術館に細川護熙 陶と書を観に行く予定でしたが
できれば波動スピーカーの試聴もしたかったので、こちらのほうにしてもらいました。
しかし、当日の申し込みだったので席が取れるかわからなかったのですが、
幸いにも席が取れたので西宮北口にある会場に直行しました。
偶然と言うよりもやっぱりという表現がぴったりだと思いますが、ヤマテツさん御夫妻もいらっしゃっておりました。
簡単なご挨拶を済ませていよいよ開演の時間になりました。
会場は「スタインウェイ関西ミニホール」です。
第1部は「演奏家のいない演奏会」
第2部は「長谷川美沙Piano Recital」
というプログラムでしたが、ほとんどが長谷川美沙さんの紹介とプログラムに使われている作曲家と演目の説明でした。
演奏家自身が事前に演目の背景にある思いや作曲家に対する見解を説明しながらのお話も興味深かったです。
このミニホールはホームページの説明にもあるように、客席数36でスタインウェイのセミコンサートグランドC型(奥行227cm)
が置かれています。予想以上に狭い印象でした。


背面には音響ポールが作り付けで設置されておりました。

当然ながらステージの両手にも配置されており、とても響きの多いホールのように感じられました。

最初に少し波動スピーカーを聴きましたがホールの残響の多さの為か定位が曖昧で無指向性のスピーカーを聴いているような
錯覚をおぼえました。
キャスリーンバトルのカーネギーホールコンサートのCDを最後に聴かせて頂きましたが、左前方の上の方からボーカルが聴こえてきて少し違和感のある再生でした。
演目は
最初に長谷川美沙さんの最近のフェイバリットである、マイケルジャクソン の ユーアーノットアローンと
映画「シンドラーのリスト」を聴かせて頂きました。
次にこれからが本番ですが
アストラ・ピアソラから
オブリピオン
ブエノスアイレスの四季より「冬」
リベルタンゴの3曲
ヨハネス・ブラームスから
2つのラプソディ Op.79
セザール・フランクから
前奏曲、フーガと変奏曲
フランツ・リストから
巡礼の年第3年「エステ荘の噴水」
愛の夢-3つのノクターンより第3番「おお、愛しうる限り愛せ」
最後はルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーベンから
ピアノソナタ第8番「悲愴」
以上でした。
クラシックに詳しくない私にとっては、第1部で長谷川さんから聞いた
曲が書かれた背景や演奏家・作曲家の思いがどうであったかなどの説明が
非常に参考になりとても解り易かったですね。
演奏の方も比較的やさしいサロン的なものだと勝手に想像しておりましたが、
演奏が始まるや否やその想像が木っ端微塵に砕かれました。
女性らしからぬダイナミックなタッチでぐいぐい迫ってくる演奏には圧倒されました。
クラシックの演奏会にはほとんど行ったことがないので全くの私感として聞いて頂ければと思いますが
上手い下手は素人の私には解りませんが普段CDなどで聴いている演奏とは全く違ったもので
こんなに気合の入った演奏とは思いませんでした。
ただ、一つ残念だったことは演奏のスケールにホールのエアボリュームが付いて行っていない様に感じられました。
特にブラームスまではタッチの強さがより強調された感じで聴こえ、
放射された音が飽和状態になり歪ぎりぎりの音でとても抜けの悪い状態でした。
ちょうどピアノの共鳴板の中に頭を突っ込んで聴いているような感じで、
頭上から音が降ってくるようにホール全体に充満しています。
これは、ホールトーンとは程遠い直接音の洪水です。
ピアノとの距離が近いことの影響ではなくホール全体のエアボリュームの不足ではないかと思いました。
ずぶの素人が本格的に設計されたであろうホールの批判をしているのですから何と大それた行為でしょう。
設計者が見ていると怒り心頭でしょうね。
しかし、このように聴こえたのは事実でしたから何とかしてもらえないでしょうかねぇ!
その反面、微妙なタッチが手に取るように解り、ハンマーが弦を叩いた後に空間に広がっていく様も鮮明に聴こえてきます。
オーディオよりオーディオ的な再生音ですね。(変な表現ですね、生演奏ですから。)
西梅田のヒルトンホテルの夕暮れのサロン・クラシックなどとは全く違う音と演奏で
クラシックと言えども色々な聴こえ方があるということも大きな発見でした。
兎に角、今日は今迄に体験したことがないような音を演奏会で聴けた事と、
ホールと演奏内容とのマッチングの大切さも初めて体験できて非常に内容の濃い演奏会でした。
また、このような機会があれば積極的に参加しようと思いました。