ひめちゃんと獅子丸は、風花の中をお散歩スタートです
途中で風花は止みましたけど、寒い朝でした。

赤城山は、その姿を現しませんでした。
昼間も時折風花が舞いましたけど、ひめちゃんと獅子丸は、元気に七海ママの昼散歩にお供です


木々の間から見える赤城山には、雪があります

今夜も寒そうです。
また湯たんぽの出番かな?
仙台2日目は、気温も低い雨の一日でした。
昨日に引き続いて多賀城に行こうとの計画変更です。
多賀城以前に国府があったという郡山遺跡に向かいました。
実はひめちゃんちのおかあさんは、ほんの数ヶ月だけど、郡山に住んだことがあります。
もう遠い昔の話だけど、仙台で最初に住んだのが、郡山なのです。
通学に不便なので、八木山に引っ越しました。
まさか、郡山を再訪するなんて思ってもいませんでした。
東北本線で南に 1 駅、長町駅で降ります。
まず駅の大きさに驚き、町の大きさに驚きました。
駅前の大通りを下ります。

道路の大きさもさることながら、歩道と自転車道もしっかりとってあります
通勤通学時間帯には、人と自転車があふれるのでしょう。
名もない交差点を右折、心細くウロウロします。
間違えたかな?
でも、もう少し行ってみよう。
突然、郡山遺跡の看板(かなり劣化してますけど)が出現しました

よかった、間違えていなかった
さらに進んで、「郡山中学→」の表示を見付けて、左折します。
郡山遺跡は郡山中学の近くということなので、ホッとします。
道ばたに郡山遺跡の説明板です。

ちょっと古いけど、さっきのよりはズーッとましです。
下にわかりやすい地図もありました

左上のJR長町駅から現在地まで歩いてきたのです。
どうして国府は多賀城に移ってしまったのでしょう?
角を曲がってさらに行くと、この2枚にさらに新しい説明板がありました

詳しい説明がありますので、詠みやすいように4分割してみます。
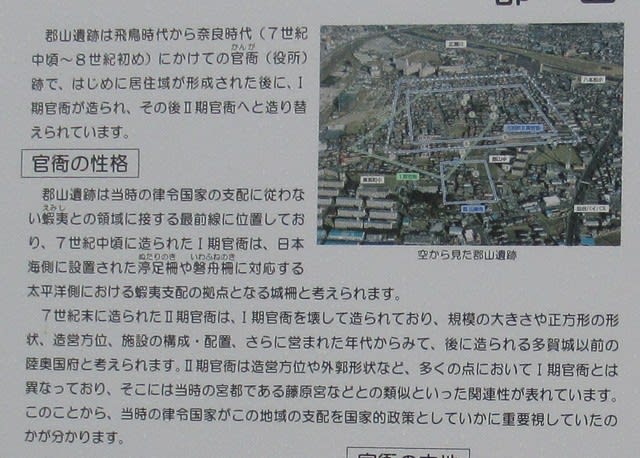
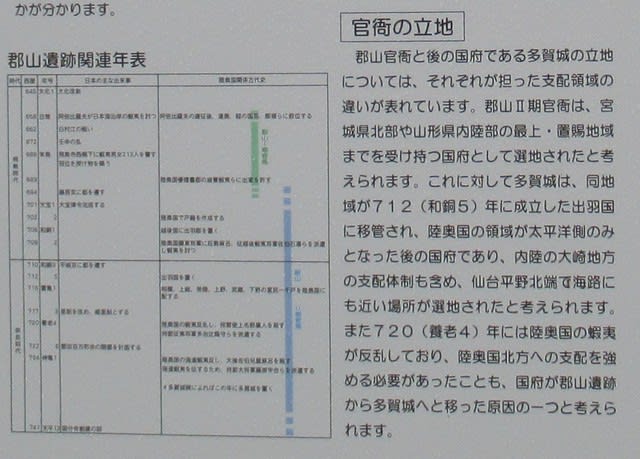

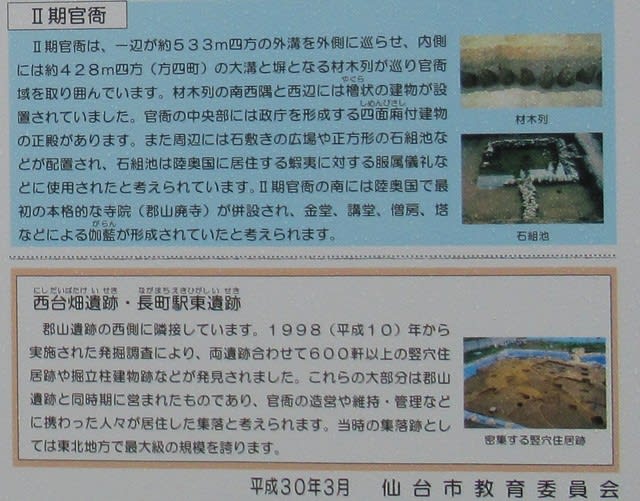
郡山官衙は、宮城県北部や山形県内陸部の最上・置賜地域までを受け持つ国府として選定された。
多賀城は、此れ等の地域が和銅5年(712)に成立した出羽国に移管され、陸奥国の領域が太平洋側のみになった後の国府で、仙台平野北端で海路にも近い所が選定された。
また、養老4年(720)の蝦夷の叛乱も原因の一つと考えられる。
だいたいこんなことで、国府は多賀城に移ることになったようです。
この遺跡が発掘調査される前に、ひめちゃんちのおかあさんは、仙台を去りました。
知らなかったわけです。
何にもないということでしたけど、本当に何もありませんでした

駅に戻ります。
キョロキョロしても、昔住んでいたところの見当も付きません
全く変わっているのです
長町駅前に、宮城交通のバスが見えます

電車ではなく、宮城交通のバスで、キャンパスのある川内まで通っていたのです
長い時を経て、郡山を訪れたことは、何かの因縁なのでしょう



























































