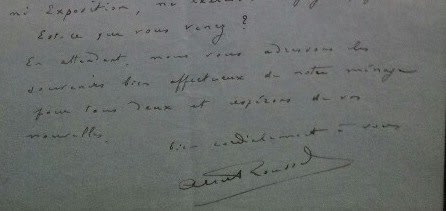○ゴーバーマン指揮管弦楽団、ラリー・カート、キャロル・ローレンス他オリジナル・ブロードウェイ・キャスト(sony)1957・CD
第一幕(前半)を中心に編まれたオリジナルキャストによる録音。オリジナルではバーンスタイン自身は振っていない(複数ある録音もシンフォニックダンスが殆ど)。音こそ古びて色彩的な派手さがないし歌も素朴、管弦楽もこの頃の雑味を帯びているが、生のままというか、リズムを中心とした粗野な味わいは劇音楽というより劇そのものを直接感じさせる。歌いながら踊っているわけでそこも評価に加味せねばなるまい。平易な英語なのでわかりやすいのも、これがダンス・ミュージカル、「アメリカのミュージカルの真の誕生」であることを実感させる。舞台では啓蒙的であろうとしたバーンスタインが、劇の構成要素であるプエルトリコからの舞踏音楽をジャズの要素と巧みに織り交ぜて、通俗的だが永遠に残る伝説的な素晴らしい歌のメドレー、「トゥナイト」「アメリカ」など(各々さほど長く何度も歌われるわけではない)、踊れるダンス、「マンボ!(体育館のダンス)」「クール」などといった曲でのはっきりしたリズムの連環という形で構成している。コープランド的な「アメクラ」の部分はあるのだが、バーンスタインにとってそれは同時代の風物として「中に取り込む相手」であり、明るく空疎な響きと複雑なリズムだけに純化されたそれとは違い、厚みある響きや色濃い旋律表現によってバーンスタイン化されており、他の要素も同様で、全部を見事に構造的に融和させている。世俗性は何も客受けだけを狙ったわけではなく、たった2日の間に大都会の底辺で起こった、対照的な移民系の若者同士の悲劇を、「刹那的なもの」の連続によって「ロメオとジュリエット」のフォーマットを使い表現したということだ。これは「アメリカ」を代表するミュージカルであるとともに「アメリカ」に問題提起する、今もし続けているミュージカルである。シェークスピアのフォーマットを使って若者を取り巻く社会問題を音楽化したというと、ディーリアスのケラーによる「村のロメオとジュリエット」があるが、ここではディーリアスの時代から半世紀を経、より肌につくような内容が語られている。ケラーは美談を書いたわけではないがディーリアスは世紀末の雰囲気そのままに二人の死を美化してしまった。バーンスタインは、トニーだけが死んで終わる。日常の続きまで描く。このオリジナルキャスト抜粋版では美しい高音でディミヌエンドはするが、あまりにあっけない、現代の悲劇は一瞬で終わると言わんばかりの「銃弾一発」(ま、筋書きはローレンツだが)。さすがに全編聴くのはしんどいが、バーンスタイン自身の豪華盤は話題にもなり、当時はよく聴かれていた(それすら全曲ではない)。ダンスを楽しむには舞台であり、音ではどうにもこうにもだが、それでも、バーンスタインの作曲の腕をもってこの録音くらいなら聴かせる力がある。けしてシリアスなバーンスタインの作風ではないが、ユダヤの出自を押し出した交響曲などよりある意味結局は「アメリカ人」である(トニーのような)自身を素直に投影した作品として聴くことも可能である。
第一幕(前半)を中心に編まれたオリジナルキャストによる録音。オリジナルではバーンスタイン自身は振っていない(複数ある録音もシンフォニックダンスが殆ど)。音こそ古びて色彩的な派手さがないし歌も素朴、管弦楽もこの頃の雑味を帯びているが、生のままというか、リズムを中心とした粗野な味わいは劇音楽というより劇そのものを直接感じさせる。歌いながら踊っているわけでそこも評価に加味せねばなるまい。平易な英語なのでわかりやすいのも、これがダンス・ミュージカル、「アメリカのミュージカルの真の誕生」であることを実感させる。舞台では啓蒙的であろうとしたバーンスタインが、劇の構成要素であるプエルトリコからの舞踏音楽をジャズの要素と巧みに織り交ぜて、通俗的だが永遠に残る伝説的な素晴らしい歌のメドレー、「トゥナイト」「アメリカ」など(各々さほど長く何度も歌われるわけではない)、踊れるダンス、「マンボ!(体育館のダンス)」「クール」などといった曲でのはっきりしたリズムの連環という形で構成している。コープランド的な「アメクラ」の部分はあるのだが、バーンスタインにとってそれは同時代の風物として「中に取り込む相手」であり、明るく空疎な響きと複雑なリズムだけに純化されたそれとは違い、厚みある響きや色濃い旋律表現によってバーンスタイン化されており、他の要素も同様で、全部を見事に構造的に融和させている。世俗性は何も客受けだけを狙ったわけではなく、たった2日の間に大都会の底辺で起こった、対照的な移民系の若者同士の悲劇を、「刹那的なもの」の連続によって「ロメオとジュリエット」のフォーマットを使い表現したということだ。これは「アメリカ」を代表するミュージカルであるとともに「アメリカ」に問題提起する、今もし続けているミュージカルである。シェークスピアのフォーマットを使って若者を取り巻く社会問題を音楽化したというと、ディーリアスのケラーによる「村のロメオとジュリエット」があるが、ここではディーリアスの時代から半世紀を経、より肌につくような内容が語られている。ケラーは美談を書いたわけではないがディーリアスは世紀末の雰囲気そのままに二人の死を美化してしまった。バーンスタインは、トニーだけが死んで終わる。日常の続きまで描く。このオリジナルキャスト抜粋版では美しい高音でディミヌエンドはするが、あまりにあっけない、現代の悲劇は一瞬で終わると言わんばかりの「銃弾一発」(ま、筋書きはローレンツだが)。さすがに全編聴くのはしんどいが、バーンスタイン自身の豪華盤は話題にもなり、当時はよく聴かれていた(それすら全曲ではない)。ダンスを楽しむには舞台であり、音ではどうにもこうにもだが、それでも、バーンスタインの作曲の腕をもってこの録音くらいなら聴かせる力がある。けしてシリアスなバーンスタインの作風ではないが、ユダヤの出自を押し出した交響曲などよりある意味結局は「アメリカ人」である(トニーのような)自身を素直に投影した作品として聴くことも可能である。