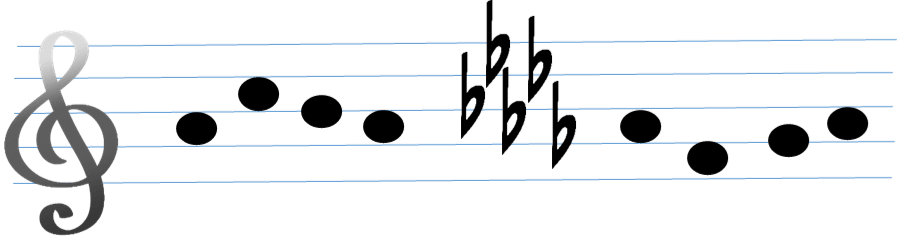第54回プロムナード・コンサートは明後日となりました。
新型コロナ感染症蔓延後は、イベント開催につきましても様々な対応を求められるようになりましたので、ご来場に際しては、下記の点にご留意いただきますようよろしくお願いします。
新型コロナ感染症蔓延後は、イベント開催につきましても様々な対応を求められるようになりましたので、ご来場に際しては、下記の点にご留意いただきますようよろしくお願いします。
ご入場の際は、マスク着用、消毒をお願いします。
マスクをお持ちでない場合は、受付にてお求めくださいますようお願いします。
また、座席は間をあけて着席いただきますようお願いします。
ご来場前に熱をお測りいただきますようお願いします。
37.5度以上ある場合や、体調不良、咳などの症状がある方は、ご来場をご遠慮下さいますよう、よろしくお願いします。
また、ご来場の方のお名前および連絡先をご記入いただくことになります。
ご連絡先情報は、万が一の場合は、保健所等の公的機関の要請により、提供させていただく場合があります。
いただいたご連絡先情報は個人情報として厳重に管理し、上記の目的以外には使用いたしません。
また、保管期間は1ヶ月とし、保管期間経過後に適切な方法により破棄させていただきます。
以上、ご理解いただきますよう、よろしくお願いします。
なお、今回の第54回プロムナード・コンサートは、「芸術文化公演再開緊急支援事業(兵庫県、姫路市、兵庫県芸術文化協会)」による開催となりました。
マスクをお持ちでない場合は、受付にてお求めくださいますようお願いします。
また、座席は間をあけて着席いただきますようお願いします。
ご来場前に熱をお測りいただきますようお願いします。
37.5度以上ある場合や、体調不良、咳などの症状がある方は、ご来場をご遠慮下さいますよう、よろしくお願いします。
また、ご来場の方のお名前および連絡先をご記入いただくことになります。
ご連絡先情報は、万が一の場合は、保健所等の公的機関の要請により、提供させていただく場合があります。
いただいたご連絡先情報は個人情報として厳重に管理し、上記の目的以外には使用いたしません。
また、保管期間は1ヶ月とし、保管期間経過後に適切な方法により破棄させていただきます。
以上、ご理解いただきますよう、よろしくお願いします。
なお、今回の第54回プロムナード・コンサートは、「芸術文化公演再開緊急支援事業(兵庫県、姫路市、兵庫県芸術文化協会)」による開催となりました。
会場費が半額補填してもらえるので、余分にかかるコロナ対策費を捻出できるのが、助かるところです。
我々のコンサートは、入場料無料なのであまり関係はないのですが、入場料をいただくコンサートなどは、会場入場者数を半分に制限されると、当然売り上げも落ちるわけで、それなのに使用料値引きがないのはおかしいと思っていましたので、こういう制度はいいですね。
ただ、申請書類がいろいろあって面倒でした。
それでも、19日からは、クラシックコンサートは入場者数制限がなくなるようなので、ヤレヤレです。
まぁ今さらですが、クラシックコンサートは来場者が声を出すわけではないから…ということで解除されるようですね。
わかりきったことなのに…と。