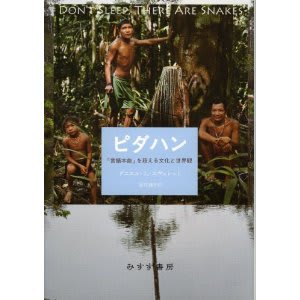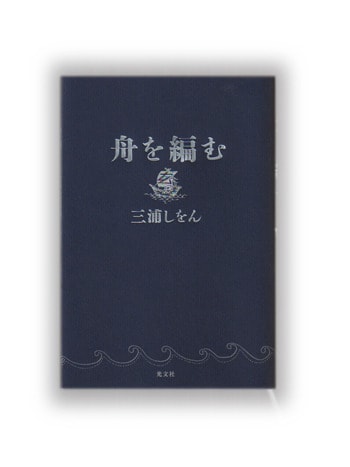最近読んだ本の中でも内容の詰まった厚い本でした。
サルファ剤の話って知らなかったんですが、医学の歴史を変えた薬であり、医薬品開発の礎になった化合物なんですね!
これはひとりの医師を核に、奇跡の薬の発見からそれがペニシリンなどの抗生物質に取って代わられるまでの物語です。
*あらすじ*
第一次世界大戦において、細菌による感染症にかかることはほぼ死を意味した。
重症のガス壊疽になれば医師に残された手段は感染部位の切断のみであり、このようにしても生き残る者は僅かであった。
衛生兵であったゲルハルト・ドーマクは野戦病院での惨状を見て、この人類の恐ろしい敵に立ち向かうことを心に誓った。
戦後、医師となったドーマクは「細菌を痛めつける薬」を探す研究に取りかかる。
おりしも、ドイツの有力コールタール染料会社、フリードリッヒ・バイエル&カンパニーでは医薬品の開発に力をいれようとしており、医薬品研究プログラムのリーダーであるハインリヒ・ヘルラインはドーマクを主要メンバーとして引き入れることに決める。
ドーマクはここで連鎖球菌に感染させたマウスを用いた評価系を確立し、社内で合成された化合物を片っ端からこの評価系にかけていった。
しかしどれも効かず、世界的な不景気により資金が干上がってきたころに、効果を示したと思われる化合物が見出だされる。1931年の夏のことであった。
さらに合成展開を進め、得られた赤い化合物は、副作用の殆どない、まさに魔法の薬であった―
なんと、この薬のスタートが色素染料であったことにまずびっくり。
動物を染めてしまう、ってそりゃあねぇ。。
でも、染色される=タンパク質と強く結合する、つまりなんらかの薬効を示すのでは?ってところに着目したと考えると、なるほど…と思う。
この薬以前の薬は化学に基づいたというよりも民間療法に近いものがほとんどで、動物実験や臨床試験も不要、宣伝には何書いてもOK、処方箋なしでも買える、、って今から思うと怖くて使えないようなものばかりだったらしい。
あちこちで色んな種類のサルファ剤が作られるようになった結果の延長で、大規模で悲惨な薬害事件が起き、それがきっかけとなってアメリカではFDAによる医薬品の管理体制が出来上がった…ということからも、ほんとに医薬品の世界を大きく変えた薬なんだなと思った。
バイエルにおける創薬の体制もまさに今の医薬品開発の体制と同じだし、歴史を知ると同時に医薬品開発の実際も理解できるんじゃないかなーと感じる内容でした。
今と決定的に違うのは臨床試験の大変さだと思いますが。
当時は治療法がなかったり、戦時中で負傷者がたくさんいたりで、臨床試験はわりと簡単にできたんですね。
軍隊は生活がほぼ完全にコントロールされているし、傷口から感染症にかかる兵士も多かったから、絶好の試験の場だったんでしょう。
戦争が医薬品開発を後押ししたっていうのも皮肉な話ですけど。
ここの本では科学の話と、第一次世界大戦~第二次世界大戦の歴史が絡んできてるので、物語が壮大になってます。
特にナチス政権下でのノーベル賞受賞妨害、強制収容所における人体実験など、ぞっとする話も…。
ほんとは化合物の色素の部分には活性はなく、ただのサルファに活性があることに気づかなかったっぽいところは片手落ち感があるものの、最後にドーマクの仕事が認められるあたりに救われます。
*データ*
著者:トーマス・ヘイガー
訳者:小林 力
出版社:中央公論新社
ISBN:9784120044793
サルファ剤の話って知らなかったんですが、医学の歴史を変えた薬であり、医薬品開発の礎になった化合物なんですね!
これはひとりの医師を核に、奇跡の薬の発見からそれがペニシリンなどの抗生物質に取って代わられるまでの物語です。
*あらすじ*
第一次世界大戦において、細菌による感染症にかかることはほぼ死を意味した。
重症のガス壊疽になれば医師に残された手段は感染部位の切断のみであり、このようにしても生き残る者は僅かであった。
衛生兵であったゲルハルト・ドーマクは野戦病院での惨状を見て、この人類の恐ろしい敵に立ち向かうことを心に誓った。
戦後、医師となったドーマクは「細菌を痛めつける薬」を探す研究に取りかかる。
おりしも、ドイツの有力コールタール染料会社、フリードリッヒ・バイエル&カンパニーでは医薬品の開発に力をいれようとしており、医薬品研究プログラムのリーダーであるハインリヒ・ヘルラインはドーマクを主要メンバーとして引き入れることに決める。
ドーマクはここで連鎖球菌に感染させたマウスを用いた評価系を確立し、社内で合成された化合物を片っ端からこの評価系にかけていった。
しかしどれも効かず、世界的な不景気により資金が干上がってきたころに、効果を示したと思われる化合物が見出だされる。1931年の夏のことであった。
さらに合成展開を進め、得られた赤い化合物は、副作用の殆どない、まさに魔法の薬であった―
なんと、この薬のスタートが色素染料であったことにまずびっくり。
動物を染めてしまう、ってそりゃあねぇ。。
でも、染色される=タンパク質と強く結合する、つまりなんらかの薬効を示すのでは?ってところに着目したと考えると、なるほど…と思う。
この薬以前の薬は化学に基づいたというよりも民間療法に近いものがほとんどで、動物実験や臨床試験も不要、宣伝には何書いてもOK、処方箋なしでも買える、、って今から思うと怖くて使えないようなものばかりだったらしい。
あちこちで色んな種類のサルファ剤が作られるようになった結果の延長で、大規模で悲惨な薬害事件が起き、それがきっかけとなってアメリカではFDAによる医薬品の管理体制が出来上がった…ということからも、ほんとに医薬品の世界を大きく変えた薬なんだなと思った。
バイエルにおける創薬の体制もまさに今の医薬品開発の体制と同じだし、歴史を知ると同時に医薬品開発の実際も理解できるんじゃないかなーと感じる内容でした。
今と決定的に違うのは臨床試験の大変さだと思いますが。
当時は治療法がなかったり、戦時中で負傷者がたくさんいたりで、臨床試験はわりと簡単にできたんですね。
軍隊は生活がほぼ完全にコントロールされているし、傷口から感染症にかかる兵士も多かったから、絶好の試験の場だったんでしょう。
戦争が医薬品開発を後押ししたっていうのも皮肉な話ですけど。
ここの本では科学の話と、第一次世界大戦~第二次世界大戦の歴史が絡んできてるので、物語が壮大になってます。
特にナチス政権下でのノーベル賞受賞妨害、強制収容所における人体実験など、ぞっとする話も…。
ほんとは化合物の色素の部分には活性はなく、ただのサルファに活性があることに気づかなかったっぽいところは片手落ち感があるものの、最後にドーマクの仕事が認められるあたりに救われます。
*データ*
著者:トーマス・ヘイガー
訳者:小林 力
出版社:中央公論新社
ISBN:9784120044793