https://1000ya.isis.ne.jp/
◆世界中がウイルス・パンデミックの渦中におかれることになった。RNAウイルスの暴風が吹き荒れているのである。新型コロナウイルスがSARSやMARSや新型インフルエンザの「変異体」であることを、もっと早くに中国は発表すべきだったのだろう。そのうえで感染症を抑える薬剤開発やワクチンづくりに臨んでみたかった。
◆ちなみに「変異」や「変異体」は21世紀の思想の中心になるべきものだった。せめてフランク・ライアンの『破壊する創造者』(ハヤカワ文庫)、フレデリック・ケックの『流感世界』(水声社)を読んでほしい。千夜千冊ではカール・ジンマーの『ウイルス・プラネット』を紹介したが、中身はたいしたことがなく、武村政春さんの何冊かを下敷きにしたので(講談社ブルーバックスが多い)、そちらを入手されるのがいいだろう。
◆それにしても東京もロックダウン寸前だ。「自粛嫌い」のぼくも、さすがに家族からもスタッフからも「自制」を勧告されていて、この2週間の仕事の半分近くがネット・コミュニケーションになってきた(リアル2・5割、ネット参加7・5割のハイブリッド型)。それはそれ、松岡正剛はマスクが嫌い、歩きタバコ大好き派なので、もはや東京からは排除されてしかるべき宿命の持ち主になりつつあるらしい。そのうち放逐されるだろう。
◆もともとぼくは外に出掛けないタチで(外出嫌い)、長らく盛り場で飲んだり話しこんだりしてこなかった。学生時代に、このコンベンションに付き合うのは勘弁してもらいたいと思って以来のことだ。下戸でもある。だから結婚式や葬儀がひどく苦手で、とっくに親戚づきあいも遠のいたままにある。
◆これはギリとニンジョーからするとたいへん無礼なことになるのだが、ぼくのギリとニンジョーはどちらかというと孟子的なので、高倉健さんふうの「惻隠・羞悪・辞譲・是非」の四端のギリギリで出動するようになっている。たいへん申し訳ない。
◆ついでにいえば動物園はあいかわらず好きだけれど、ディズニーランドは大嫌いだ。レイ・ブラッドベリの家に行ったとき、地下室にミッキーマウスとディズニーグッズが所狭しと飾ってあったので、この天下のSF作家のものも読まなくなったほどだ。これについては亡きナムジュン・パイクと意見が一致した。かつての豊島園には少し心が動いたが、明るい改装が続いてからは行っていない。
◆スポーツ観戦は秩父宮のラグビーが定番だったけれど、平尾誠二が早逝してから行かなくなった。格闘技はリングスが好きだったけれど、横浜アリーナで前田日明がアレクサンダー・カレリンに強烈なバックドロップを食らって引退して以来、行かなくなった。ごめんなさい。子供時代はバスケットの会場と競泳大会の観戦によく行っていた。
◆つまりぼくは、できるかぎりの脳内散歩に徹したいほうなのである。それは7割がたは「本」による散策だ(残りはノートの中での散策)。実は、その脳内散歩ではマスクもするし、消毒もする。感染を遮断するのではなく、つまらない感染に出会うときに消毒をする。これがわが「ほん・ほん」の自衛策である。
◆ところで、3月20日に『日本文化の核心』(講談社現代新書)という本を上梓した。ぼくとしてはめずらしくかなり明快に日本文化のスタイルと、そのスタイルを読み解くためのジャパン・フィルターを明示した。パンデミックのど真ん中、本屋さんに行くのも躊らわれる中での刊行だったけれど、なんとか息吹いてくれているようだ。
◆ほぼ同じころ、『花鳥風月の科学』の英語版が刊行された。“Flowers,Birds,Wind,and Moon”というもので、サブタイトルに“The Phenomenology of Nature in Japanese Culture”が付く。デヴィッド・ノーブルさんが上手に訳してくれた。出版文化産業振興財団の発行である。
◆千夜千冊エディションのほうは『心とトラウマ』(角川ソフィア文庫)が並んでいる最中で、こちらはまさに心の「変異」を扱っている。いろいろ参考になるのではないかと思う。中井久夫ファンだったぼくの考え方も随所に洩しておいた。次の千夜千冊エディションは4月半ばに『大アジア』が出る。これも特異な「変異体」の思想を扱ったもので、竹内好から中島岳志に及ぶアジア主義議論とは少しく別の見方を導入した。日本人がアジア人であるかどうか、今後も問われていくだろう。
2020・3・30(月)
◆このところ、千夜千冊エディションの入稿と校正、ハイパーコーポーレート・ユニバシティの連続的実施(ビリヤード、遠州流のお茶)、講談社現代新書『日本文化の核心』の書きおろしと入稿、角川武蔵野ミュージアムの準備、ネットワン「縁座」のプロデュース(本條秀太郎の三味線リサイタル)、九天玄気組との記念的親交、イシス編集学校のさまざま行事などなどで、なんだかんだと気ぜわしかった。
◆こういうときは不思議なもので、前にも書いたけれど、隙間時間の僅かな読書がとても愉しい。1月~2月はガリレオやヘルマン・ワイルなどの物理や数学の古典にはまっていた。この、隙間読書の深度が突き刺すようにおもしろくなる理由については、うまく説明できない。「間食」の誘惑? 「別腹」のせい? 「脇見」のグッドパフォーマンス? それとも「気晴らし演奏」の醍醐味? などと考えてみるのだが、実はよくわからない。
◆さて、世間のほうでも隙間を狙った事態が拡大しつつあるようだ。新型コロナウィルス騒ぎでもちきりなのだ。パンデミック間近かな勢いがじわじわ報道されていて、それなのに対策と現実とがそぐわないと感じている市民が、世界中にいる。何をどうしていくと、何がどうなるはかわからないけれど、これはどう見ても「ウィルスとは何か」ということなのである。
◆ウィルス(virus)とはラテン語では毒液とか粘液に由来する言葉で、ヒポクラテスは「病気をひきおこす毒」だと言った。けれどもいわゆる細菌や病原菌などの「バイキン」とは異なって、正体が説明しにくい。まさに隙間だけで動く。
◆定義上は「感染性をもつ極微の活動体」のことではあるのだが、他の生物の細胞を利用して自分を複製させるので、まさに究極の生物のように思えるのにもかかわらず、そもそもの生体膜(細胞膜)がないし、小器官ももっていないので、生物の定義上からは非生物にもなりうる超奇妙な活動体なのである。
◆たとえば大腸菌、マイコプラズマ、リケッチアなどの「バイキン」は細胞をもつし、DNAが作動するし、タンパク質の合成ができるわけだ。ところがウィルスはこれらをもってない。自分はタンパク質でできているのに、その合成はできない。生物は細胞があれば、生きるのに必要なエネルギーをつくる製造ラインが自前でもてるのだが、ウィルスにはその代謝力がないのである。だから他の生物に寄生する。宿主を選ぶわけだ、宿主の細胞に入って仮のジンセーを生きながらえる。
◆気になるのはウィルスの中核をつくっているウィルス核酸と、それをとりかこむカプシド(capsid)で、このカプシドがタンパク質の殻でできている粒子となって、そこにエンベロープといった膜成分を加え、宿主に対して感染可能状態をつくりあげると、一丁前の「完全ウィルス粒子」(これをビリオンという)となってしまうのである。ところがこれらは自立していない。他の環境だけで躍如する。べつだん「悪さ」をするためではなく、さまざまな生物に宿を借りて、鳥インフルエンザ・ウィルスなどとなる。
◆おそらくウィルスは「仮りのもの」なのである。もっとはっきり予想していえば「借りの情報活動体」なのだ。鍵と鍵穴のどちらとは言わないが、半分ずつの鍵と鍵穴をつくったところで、つまり一丁「前」のところで「仮の宿」にトランジットする宿命(情報活動)を選んだのだろうと思う。
◆ということは、これは知っていることだろうと思うけれど、われわれの体の中には「悪さ」をしていないウィルスがすでにいっぱい寝泊まりしているということになる。たとえば一人の肺の中には、平均174種類ほどのウィルスが寝泊まりしているのである。
◆急にウィルスの話になってしまったが、ぼくが数十年かけてやってきたことは、どこかウィルスの研究に似ていたような気もする。さまざまな情報イデオロギーや情報スタイルがどのように感染してきたのか、感染しうるのか、そのプロセスを追いかけてきたようにも思うのだ。
2020・2・25(火)
◆世界中がウイルス・パンデミックの渦中におかれることになった。RNAウイルスの暴風が吹き荒れているのである。新型コロナウイルスがSARSやMARSや新型インフルエンザの「変異体」であることを、もっと早くに中国は発表すべきだったのだろう。そのうえで感染症を抑える薬剤開発やワクチンづくりに臨んでみたかった。
◆ちなみに「変異」や「変異体」は21世紀の思想の中心になるべきものだった。せめてフランク・ライアンの『破壊する創造者』(ハヤカワ文庫)、フレデリック・ケックの『流感世界』(水声社)を読んでほしい。千夜千冊ではカール・ジンマーの『ウイルス・プラネット』を紹介したが、中身はたいしたことがなく、武村政春さんの何冊かを下敷きにしたので(講談社ブルーバックスが多い)、そちらを入手されるのがいいだろう。
◆それにしても東京もロックダウン寸前だ。「自粛嫌い」のぼくも、さすがに家族からもスタッフからも「自制」を勧告されていて、この2週間の仕事の半分近くがネット・コミュニケーションになってきた(リアル2・5割、ネット参加7・5割のハイブリッド型)。それはそれ、松岡正剛はマスクが嫌い、歩きタバコ大好き派なので、もはや東京からは排除されてしかるべき宿命の持ち主になりつつあるらしい。そのうち放逐されるだろう。
◆もともとぼくは外に出掛けないタチで(外出嫌い)、長らく盛り場で飲んだり話しこんだりしてこなかった。学生時代に、このコンベンションに付き合うのは勘弁してもらいたいと思って以来のことだ。下戸でもある。だから結婚式や葬儀がひどく苦手で、とっくに親戚づきあいも遠のいたままにある。
◆これはギリとニンジョーからするとたいへん無礼なことになるのだが、ぼくのギリとニンジョーはどちらかというと孟子的なので、高倉健さんふうの「惻隠・羞悪・辞譲・是非」の四端のギリギリで出動するようになっている。たいへん申し訳ない。
◆ついでにいえば動物園はあいかわらず好きだけれど、ディズニーランドは大嫌いだ。レイ・ブラッドベリの家に行ったとき、地下室にミッキーマウスとディズニーグッズが所狭しと飾ってあったので、この天下のSF作家のものも読まなくなったほどだ。これについては亡きナムジュン・パイクと意見が一致した。かつての豊島園には少し心が動いたが、明るい改装が続いてからは行っていない。
◆スポーツ観戦は秩父宮のラグビーが定番だったけれど、平尾誠二が早逝してから行かなくなった。格闘技はリングスが好きだったけれど、横浜アリーナで前田日明がアレクサンダー・カレリンに強烈なバックドロップを食らって引退して以来、行かなくなった。ごめんなさい。子供時代はバスケットの会場と競泳大会の観戦によく行っていた。
◆つまりぼくは、できるかぎりの脳内散歩に徹したいほうなのである。それは7割がたは「本」による散策だ(残りはノートの中での散策)。実は、その脳内散歩ではマスクもするし、消毒もする。感染を遮断するのではなく、つまらない感染に出会うときに消毒をする。これがわが「ほん・ほん」の自衛策である。
◆ところで、3月20日に『日本文化の核心』(講談社現代新書)という本を上梓した。ぼくとしてはめずらしくかなり明快に日本文化のスタイルと、そのスタイルを読み解くためのジャパン・フィルターを明示した。パンデミックのど真ん中、本屋さんに行くのも躊らわれる中での刊行だったけれど、なんとか息吹いてくれているようだ。
◆ほぼ同じころ、『花鳥風月の科学』の英語版が刊行された。“Flowers,Birds,Wind,and Moon”というもので、サブタイトルに“The Phenomenology of Nature in Japanese Culture”が付く。デヴィッド・ノーブルさんが上手に訳してくれた。出版文化産業振興財団の発行である。
◆千夜千冊エディションのほうは『心とトラウマ』(角川ソフィア文庫)が並んでいる最中で、こちらはまさに心の「変異」を扱っている。いろいろ参考になるのではないかと思う。中井久夫ファンだったぼくの考え方も随所に洩しておいた。次の千夜千冊エディションは4月半ばに『大アジア』が出る。これも特異な「変異体」の思想を扱ったもので、竹内好から中島岳志に及ぶアジア主義議論とは少しく別の見方を導入した。日本人がアジア人であるかどうか、今後も問われていくだろう。
2020・3・30(月)
◆このところ、千夜千冊エディションの入稿と校正、ハイパーコーポーレート・ユニバシティの連続的実施(ビリヤード、遠州流のお茶)、講談社現代新書『日本文化の核心』の書きおろしと入稿、角川武蔵野ミュージアムの準備、ネットワン「縁座」のプロデュース(本條秀太郎の三味線リサイタル)、九天玄気組との記念的親交、イシス編集学校のさまざま行事などなどで、なんだかんだと気ぜわしかった。
◆こういうときは不思議なもので、前にも書いたけれど、隙間時間の僅かな読書がとても愉しい。1月~2月はガリレオやヘルマン・ワイルなどの物理や数学の古典にはまっていた。この、隙間読書の深度が突き刺すようにおもしろくなる理由については、うまく説明できない。「間食」の誘惑? 「別腹」のせい? 「脇見」のグッドパフォーマンス? それとも「気晴らし演奏」の醍醐味? などと考えてみるのだが、実はよくわからない。
◆さて、世間のほうでも隙間を狙った事態が拡大しつつあるようだ。新型コロナウィルス騒ぎでもちきりなのだ。パンデミック間近かな勢いがじわじわ報道されていて、それなのに対策と現実とがそぐわないと感じている市民が、世界中にいる。何をどうしていくと、何がどうなるはかわからないけれど、これはどう見ても「ウィルスとは何か」ということなのである。
◆ウィルス(virus)とはラテン語では毒液とか粘液に由来する言葉で、ヒポクラテスは「病気をひきおこす毒」だと言った。けれどもいわゆる細菌や病原菌などの「バイキン」とは異なって、正体が説明しにくい。まさに隙間だけで動く。
◆定義上は「感染性をもつ極微の活動体」のことではあるのだが、他の生物の細胞を利用して自分を複製させるので、まさに究極の生物のように思えるのにもかかわらず、そもそもの生体膜(細胞膜)がないし、小器官ももっていないので、生物の定義上からは非生物にもなりうる超奇妙な活動体なのである。
◆たとえば大腸菌、マイコプラズマ、リケッチアなどの「バイキン」は細胞をもつし、DNAが作動するし、タンパク質の合成ができるわけだ。ところがウィルスはこれらをもってない。自分はタンパク質でできているのに、その合成はできない。生物は細胞があれば、生きるのに必要なエネルギーをつくる製造ラインが自前でもてるのだが、ウィルスにはその代謝力がないのである。だから他の生物に寄生する。宿主を選ぶわけだ、宿主の細胞に入って仮のジンセーを生きながらえる。
◆気になるのはウィルスの中核をつくっているウィルス核酸と、それをとりかこむカプシド(capsid)で、このカプシドがタンパク質の殻でできている粒子となって、そこにエンベロープといった膜成分を加え、宿主に対して感染可能状態をつくりあげると、一丁前の「完全ウィルス粒子」(これをビリオンという)となってしまうのである。ところがこれらは自立していない。他の環境だけで躍如する。べつだん「悪さ」をするためではなく、さまざまな生物に宿を借りて、鳥インフルエンザ・ウィルスなどとなる。
◆おそらくウィルスは「仮りのもの」なのである。もっとはっきり予想していえば「借りの情報活動体」なのだ。鍵と鍵穴のどちらとは言わないが、半分ずつの鍵と鍵穴をつくったところで、つまり一丁「前」のところで「仮の宿」にトランジットする宿命(情報活動)を選んだのだろうと思う。
◆ということは、これは知っていることだろうと思うけれど、われわれの体の中には「悪さ」をしていないウィルスがすでにいっぱい寝泊まりしているということになる。たとえば一人の肺の中には、平均174種類ほどのウィルスが寝泊まりしているのである。
◆急にウィルスの話になってしまったが、ぼくが数十年かけてやってきたことは、どこかウィルスの研究に似ていたような気もする。さまざまな情報イデオロギーや情報スタイルがどのように感染してきたのか、感染しうるのか、そのプロセスを追いかけてきたようにも思うのだ。
2020・2・25(火)










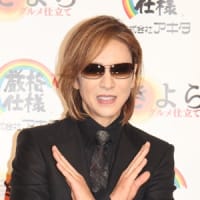


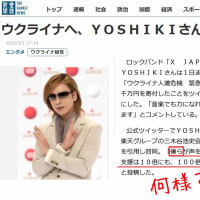


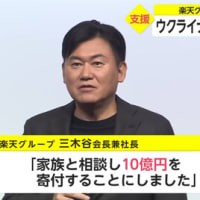
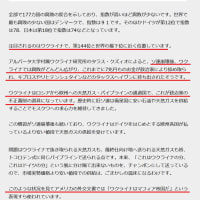



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます