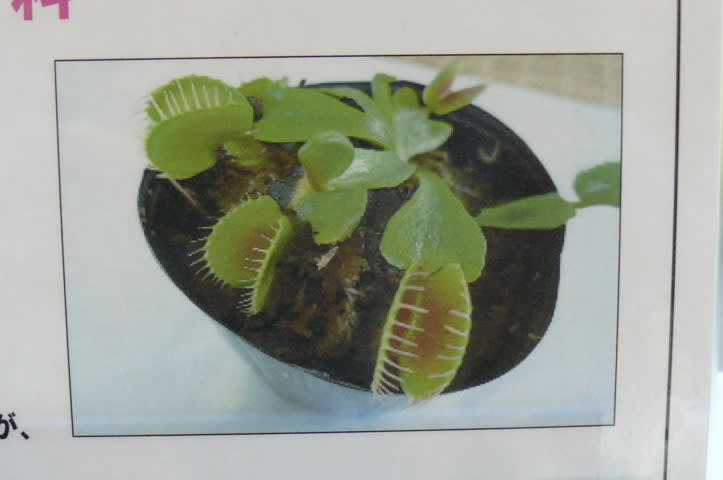2011年11月18日(金)、岩手県立花きセンター(胆沢郡金ケ崎町六原頭無2-1)の「花の館温室」から本館(管理棟)に行くため「連絡路」を通ったら、「水辺植物見本園」の表示がされている所に「コメツガ(米栂)」などが植えられていました。







コメツガ(米栂) マツ科 ツガ属 Tsuga diversifolia
日本特産の常緑高木。ツガ(栂)より標高の高い所(ウラジロモミジやシラビソなどと同じくらいの標高)に生え、純林をつくることもある。高さは普通15~20mになる。ツガに似ているが、樹皮は薄く剥がれ、若枝には褐色の毛があり、冬芽の先は丸い。葉はツガより短く、ほぼ長さが揃っている。球果のつき方もツガと違っていて、枝に真っ直ぐにつく。花期は6月。球果は長さ1.5~2.5cm。分布:本州(中部地方以北、紀伊半島)、四国、九州(祖母山)
[山と渓谷社発行「山渓ポケット図鑑3・秋の花」より]
http://blog.goo.ne.jp/pea2005/e/ac26d4a468666bb53692b085b5e0f92a [goo blog peaの植物図鑑:八幡平のコメツガ]
http://app.blog.ocn.ne.jp/t/app/weblog/post?_mode=edit_entry&id=33723048&blog_id=82331 [peaの植物図鑑:京都神護寺のコメツガ]
http://www.geocities.jp/ir5o_kjmt/kigi/kometuga.htm [コメツガ(米栂)]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%84%E3%82%AC [コメツガ(Wikipedia)]
http://had0.big.ous.ac.jp/plantsdic/gymnospermae/pinaceae/kometsuga/kometsuga.htm [コメツガ]
http://kaduno.in.coocan.jp/mediawiki/index.php?title=%C2%A7_%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%84%E3%82%AC [コメツガ(鹿角全科Wiki)]
http://www.ponnitai.com/database/wldata/tsuga_diversifolia/000069.html [コメツガ]