そういえば、随分大騒ぎでしたね。
煽られて?一度読んでおかなきゃと関係の本を2冊買ったことは買ったんですが、、
開いたことは開いたと思いますが、数ページ??
712年に世に出たらしいので、2012年、今から10年以上前になるんですね。
あっ、古事記編纂1300年という騒ぎの年(*^^*)
その時に出会っていたら、読んだかもしれないけれど、いや、やはり読んでないか(^^;;
大ベストセラー
手に取ったのは、当時、11万部以上売れたと最近読んだ本に書かれていたこと。
この類の本でのこの発行部数は大ベストセラーと言ったところでしょうね。
一度読んでおかなきゃと思っていたので、いい機会と手に取って読み始めました。 三浦祐之著「口語訳 古事記」(2002年刊)、ハードカバーの結構な大著なので、ちょっと見、引きそうになりますが、、、
三浦祐之著「口語訳 古事記」(2002年刊)、ハードカバーの結構な大著なので、ちょっと見、引きそうになりますが、、、
語り部のおじいが設定され、うまく誘導しながら読ませてくれる、そして、解説も随時読みやすく書かれている、字は小さいけど(^^;;
「古事記」、日本人なら一度は読みたいと思うけど、古典への苦手意識がありますよね、それが4ヶ月で12刷、読み始めて、そうなるわけだ、これは買い求めなきゃ、と思い始めているところです。
ローカル・アイデンティティの「古事記」
そうそう、「古事記」って、江戸時代、本居宣長が解説本を出すまでほとんど読まれることがなかったという、故に、偽書説がずっとついて回ったのだとか。
グローバル・スタンダードを目指した「日本書紀」とローカル・アイデンティティの「古事記」の違い故に、貴族の必読書とはならなかったとか。
対偶婚、縄文時代から古墳時代まで、いや、もっと長くあったのかもしれません。
簡単に言ってしまうと、婚姻や男女の関係において女性が主導的な役割を果たしていたというのか。
学術的に言われる対偶婚の特徴は、妻の性の非閉鎖、流動的結婚、女性による結婚と性関係決定権・求婚権・離婚権の保持、女性の合意を前提とする性慣行、性愛の独自なあり方、売買春の不在等であるとされています。
父系家族社会の価値観と正反対ともいうべき、女系家族社会でしょうか。
先住民族は殆どが女系家族社会と聞いていましたが、実は古代の出雲も日本もそういう社会だった、そして、農村社会などでは江戸時代までそういう社会だったようなんですね。
かねがね、政治に象徴されるように、今の社会は男主導で作られてきた結果、極度の制度疲労に陥ってしまっているように感じてきました。
僕的には、強欲資本主義克服や、平和主義貫徹には、女が主役で男は女性の直感的な思いを現実化させるブレーンに徹するのが良いのかな、って。
 詩人の高良留美子著「花ひらく大地の女神」で初めて知った“対偶婚”、女性が中心の婚姻と性の形態はまさに女系家族社会。
詩人の高良留美子著「花ひらく大地の女神」で初めて知った“対偶婚”、女性が中心の婚姻と性の形態はまさに女系家族社会。
対偶婚や古代の婚姻形態をもっと知っておきたいと、ネット検索した結果出会った関口裕子、古代史・女性史が専門の在野の歴史学者。
彼女の「日本古代婚姻史の研究」を読みたいとネットで探しまくる中で、この本への書評に答えるという論文。
よくぞここまで完膚なきまでにという、書評に対する反論。
お見事の一言に尽きると思ったし、2002年60代での逝去が惜しまれると思う一方、1994年の書評への答えは、この書評者の研究人生を暗転させたのではと、、、
梅原猛は、専門家が前言を撤回することの困難さに言及していましたが、本来、専門家の発言は相当の用意周到さが求められるのかも。
それで思い起こすのは、古代出雲に関して、東出雲と西出雲について、一方がもう一方を征服して一つの出雲となったとの見方が大勢?のような感を抱くのですが、それって根拠はおありですか?と。
前述の書評じゃないけど、専門家なんだから根拠を示しながら論理だてて示して欲しい、何て、、、
 出雲の古代史を学んでいくと、定説や「大勢」の大きな壁を感じることがよくあります。
出雲の古代史を学んでいくと、定説や「大勢」の大きな壁を感じることがよくあります。
それは、記紀以前の文献がほぼ消去され、専門家と言われる人たちも、作られた歴史という認識を持ちながらも記紀の中に真実の歴史の糸口を探る努力を余儀なくされていることや、記紀が作っている大和中心主義から抜け出せないからかもしれません。
今読み終わった山崎謙著「まぼろしの出雲王国」、出雲の歴史をさらっと撫でている感じで、学ぶものがないなあという印象でしたが、最後に来てやはり最後まで読んでよかった!
特に、三角縁神獣鏡に関する見方、日本海を介した交流国家像、地域王権、古墳に対する考え方など、今まであまり出会わなかった見方にガッテン!
「大勢」の危うさ
そして、「おわりに」では「大勢」というものの危うさと、歴史を考える視点、見る眼の大切さを再確認させていただきました。
荒神谷遺跡が出現する前は、出雲は考古学的には見るべきものはなく、神話だけが突出した世界であるという見方が大勢だった。
出雲大社境内遺跡から三本柱が出土する前は、「金輪御造営指図」は虚構だという見方が大勢だった。
旧石器時代に至っては、日本にないというのが考古学会の大勢どころか、定説であった。
縄文時代には農耕がないという見方も、かつては大勢だった。
縄文時代は狩猟採集の生活で、定住しないというのが縄文時代の大勢であり、定説であった。三内丸山遺跡のように千年にもわたって定住した遺跡が見つかるなど、想像もできなかった。
このように「大勢」というのは、学説を説明する時、何の根拠にもならないのである。
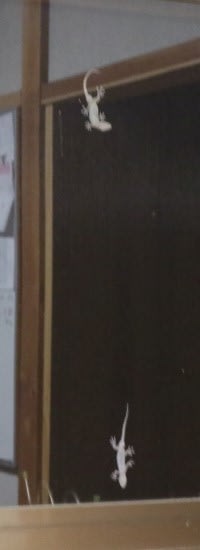 昨夜のことですが、視界の隅っこにするするっと降りて来た二つの物体が、、、
昨夜のことですが、視界の隅っこにするするっと降りて来た二つの物体が、、、
何だろうと目をやると、窓や網戸にへばりついているのは今年初めてのヤモリ、しかも、2匹一緒に。
見た目には、オスがメスを追いかけて来た、そんな雰囲気、カメラを向けて一枚、もう一枚と思っているとオスが恥ずかしがって?窓から離れてしまいました。
こっちも季節になってきましたね。
さて、4月の初め「極悪人、実は大功労者??」というタイトルで「スサノヲの正体」という関裕二の本を紹介したのですが、、
その本で一番響いたのは「縄文人はなかなか稲作を受け入れなかったし、弥生時代到来後も東漸が遅々として進まなかった」という個所。
著者がこの見方、考え方を取る拠り所は寺前直人著「文明に抗した弥生の人びと」などと紹介されていたので直ぐに借りて読みました。
なるほど!書かれてはいませんし、出雲の登場も極めて少ないのですが、「出雲の国の人びとは争いを好まなかった」事実とも強くリンクする話です。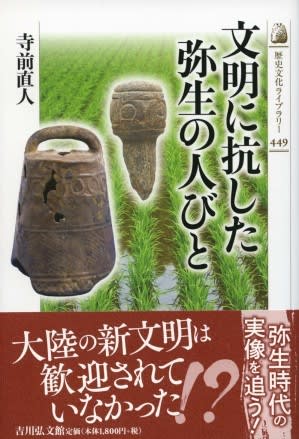 弥生時代って大陸から稲作文化や青銅器、鉄器が伝わり、我が国は“未開”の縄文から大きく文明化が進んだと大括りに喧伝されていますが、全く違うのかも。
弥生時代って大陸から稲作文化や青銅器、鉄器が伝わり、我が国は“未開”の縄文から大きく文明化が進んだと大括りに喧伝されていますが、全く違うのかも。
というのは、玄界灘に面した北部九州では、大陸からもたらされた磨製石剣や金属製剣などが厚葬墓を中心に階層的に副葬されていて、人々の階層化が進んだようだと。
劔などの武器が権力の象徴として、手に入れられる持つ者とそうでない持たざる者を峻別し、力をひけらかす象徴でもあった。
一方、本州島では、弥生中葉まで、磨製石剣や打製石剣、銅剣類は発見されるが、副葬品としてではないし、わざわざ刃先を丸くしていることや、手に入れた銅を武器や生活用具ではなく銅鐸として流通させている。
そして、石斧や石包丁などを使い続け、一気に文明化するのではなく、縄文文化を色濃く残している。
それは、縄文の祭祀で大きな役割を果たした石棒を使い続けたことや、銅鐸などに縄文からの文様を使い続けていることにも表れている。
争いに使う武器を優先するのではなく、祭祀を中心とした階層のない社会を継続するという強い意思が働いていたのかもしれません。
便利や力ではなく、少々不便でも皆で仲良く暮らすことを優先した本州島の弥生時代、学ぶものが多いように感じました。
良くも悪くも、我が国の古代史の大きな画期を担った人物だと思っていますが、、、
特に、古代出雲にとってはそうだろうと思いますし、日本の歴史にとっても注視すべき、というか、巨大な存在じゃないかと思います。
日本の古代史に関わる本を読み漁っているのですが、最近その事蹟が特に気になっている人物なんですよね。
それは、死を賭す覚悟で秦の始皇帝に取り入り、巨費を投じさせ、数千人の童男童女と百工を連れて“不老不死の妙薬”を得るミッションを持って日本に来たという徐福。
司馬遷の史記に何度か登場する徐福の足跡、中国では関係する多くの地域に徐副会があり、全土の徐副会を統括する?中国徐副会まであり、関係する地域の徐福を冠する事蹟がワンサカ、それぞれの徐副会の活動もビックリ(@@)
東渡の途中で経由したという事蹟がいくつかある韓国でも、徐福熱は僕の創造を絶するものかも。
ところが、我が国の徐福事情は、、、
最初に手に取った徐福関係の本、気鋭の研究家の本ですが、事蹟はあくまでも伝説扱いで、関係する地域の活動や思いなどを纏めたと思える内容で、1/5ほど拾い読みしてさっさと閉じましたが、、、
なぜ???本当に伝説のレベルなのか?? 気を取り直して借りてきたもう一冊、池上正治著「徐福」を開いて読み始めました。
気を取り直して借りてきたもう一冊、池上正治著「徐福」を開いて読み始めました。
事蹟を含めた中日韓の徐福事情、我が国の徐福事情が事細かく拾い上げられ、実在した徐福を確信する関係者の熱気が伝わってくるものです。
ただ、歴史書じゃないから?この本から徐福の実在を確信できませんし、出雲と徐福との関係、ヤマトの歴史の端緒となったという角度は見えません。
“徐福”と言う名は、原初の皇統を根底から揺さぶるものであるが故、記紀でも一切触れられず、研究者の間でも“伝説”の棚に置いておく方が当たり障りがない、という認識なのかなあと穿って見たりして。
それと、出雲に残る口伝では、“徐福”は出雲凋落の大きな要素であるのに、研究者は一切触れていません。
僕には、そこに触れることで出雲の価値観に大きな激震が走るのかも、と穿って見えるので、臭いものに幾重にも蓋がしてあるのかと思ったり。
徐福、我が国に足跡があるとしたら、、、2,200年余まりの間大きな宿題を残し続けているのかも。









