書庫から出して来てもらった本を見てドン引き~(^^;;
思わず、えっ!!こんなに厚い本なんだ~~(><
でも、ちゃんと借りてきました。
最近、傾倒気味の安田喜憲さんの本で引用されていた「照葉樹林文化論」に俄然興味が湧いてのことでしたが、、、
紹介されていた「照葉樹林文化論」学説を世に出した中尾佐助氏と佐々木高明氏の著作、蔵書検索でそれぞれ書庫にあるとのことで出して来てもらっての顛末。
流石に、厚さ5.5cm、840頁の中尾氏の大著にはすぐには飛びつけず、先ずは新書で手ごろそうな佐々木氏の「照葉樹林文化とは何か」を開きました。
二日余りで読み終わりましたが、これは!期待に余る手応えを感じました。
ある意味、興奮冷めやらぬ余韻の勢いで、恐る恐るでしたが開いた中尾氏の著作「中尾佐助著作集 第Ⅵ巻」、収められたシンポジウムが面白そう!まずはここから、、、
1万5千年前の大気候変動(温暖化)によって海水面が150mくらい上がり、植生が大きく変わってシイやカシなどの照葉樹林(常緑広葉樹)帯が形成され、アジアの一つの基調を成す豊かな文化の起源地となったとの学説。
その照葉樹林文化の起源地を、雲南省を中心とする文化のセンター・東亜半月弧と名付け、焼畑による雑穀農業(稲を含む)、モチ食、根栽類の水さらし利用、麹酒、納豆など発酵食品、絹、漆器、家屋(高床と吊壁)構造、歌垣、鵜飼いなど、多くの共通点が指摘されています。
その照葉樹林文化は、1)農耕段階2)雑穀を主とした焼畑段階3)稲作が卓越する段階の3段階に整理されています。
日本では1)2)が縄文時代となりますが、西日本は照葉樹林帯、東日本は落葉樹林帯、ひとくくりに照葉樹林文化とすることはできないよう。
東日本に偏っていた人口との関係は?とかの疑問もありますが、共通する文化要素が多く、太古の時代の人の交流など面白いなあと思います。
佐々木氏の「照葉樹林文化とは何か」の最後に納められた関係者の白熱した討論は、読む自分もハラハラドキドキ、歯に衣を着せずに思ったことを言い合う。
実に面白かったので、前述のとおり中尾佐助全集に納められたシンポジウムも興味津々。
楽しんで読み進めようと思っています。
最新の画像[もっと見る]
-
 アニミズムの世界観
4ヶ月前
アニミズムの世界観
4ヶ月前
-
 米離れなのにコメがキロ1000円で買えない
4ヶ月前
米離れなのにコメがキロ1000円で買えない
4ヶ月前
-
 焼畑で稲を作る
5ヶ月前
焼畑で稲を作る
5ヶ月前
-
 焼畑で稲を作る
5ヶ月前
焼畑で稲を作る
5ヶ月前
-
 「菊と刀」~「恥の文化」とは?
5ヶ月前
「菊と刀」~「恥の文化」とは?
5ヶ月前
-
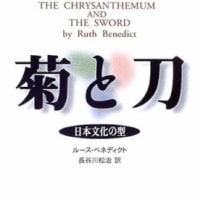 「菊と刀」~「恥の文化」とは?
5ヶ月前
「菊と刀」~「恥の文化」とは?
5ヶ月前
-
 照葉樹林文化論
5ヶ月前
照葉樹林文化論
5ヶ月前
-
 照葉樹林文化論
5ヶ月前
照葉樹林文化論
5ヶ月前
-
 ヒラリ、ハラリと
5ヶ月前
ヒラリ、ハラリと
5ヶ月前
-
 ヒラリ、ハラリと
5ヶ月前
ヒラリ、ハラリと
5ヶ月前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます