
二つの「ジェノサイド」を隠喩的に結びつける --パトリシオ・グスマン監督『真珠のボタン』
越川芳明
太平洋をはさんで日本と遠く斜めに向き合う南米のチリ。国土は南北に細長く、面積は日本の二倍である。それに比して、人口は日本の十三パーセントにすぎない。
「西パタゴニア」と呼ばれるチリの南端には、フィヨルドの中を自然の水路が網の目のように走り、ティエラ・デ・フエゴ島をはじめとする数々の島が点在する。
そうした群島には、一万年前から人類が住んでいたという。
彼らは海洋民だった。島の中に町を作ることなどしなかった。小さなカヌーを作って櫂を操り、帆を立てて、水路をあちこち移動して、食料となる魚介類を取って暮らしていた。
五つの部族が知られている。カウェスカル族、セルクナム族、アオニケン族、ハウシュ族、ヤマナ族だ。もちろん、南極に近い彼らの生活圏では、厳しい自然(暴風雨、飲み水不足など)と対峙しなければならないが、それでも、海は彼らには家族の一部であり、敵ではない。
十九世紀のパタゴニアには、まだ八千人の先住民が住み、三百艘のカヌーがあったという。特にオリオン座と南十字星を崇め、星座を読む(宇宙の中で自分の位置を確かめる)能力にすぐれていた。彼らの魂は死後に星になるという信仰があった。
二十世紀の初めに、あるオーストリア人司祭が撮ったセルクナム族の「ボディペインティング」の写真には、男女の裸体に白い点や線で表わした図が描かれている。現代詩人のラウル・ズリタは、「宇宙に自分を近づけるための手段だった」との仮説を述べている。
パタゴニアの先住民は「神話の時間」に生きていたと言えるかもしれない。
「神話の考えるところによると、私たち人間もほかのすべての生き物と同様この地球上を仮の住まいとしているだけで、ときがいたればそこから消滅していくことだってありうる(中略)、宇宙の中ではいたってか弱い存在にすぎないのです」(中沢新一『人類最古の哲学』24ページ)
グスマン監督は、レヴィ=ストロースが『野生の思考』の中で、先住民の思考の特徴だと述べた「神話的思考」を実践する。レヴィ=ストロースによれば、「神話的思考とは、一種の知的な器用仕事(ルビ:ブリコラージュ)である」が、グスマン監督は、チリの海を舞台にした時代の異なる二つの「ジェノサイド」を「ブリコラージュ」で一つに結びつける。ある意味、想像力を駆使した隠喩的な手法と言える。
一つ目は、いうまでもなく、一六世紀に始まるヨーロッパの植民地政策である。ポルトガル、オランダ、イギリスなど、ヨーロッパ諸国が軍隊、教会関係者、民間人をパタゴニアに送り込み海路を切り開く。「インディアン狩り」などをやって、先住民のある部族を絶滅させる。
十九世紀初頭に象徴的な事件があった。イギリスのビーグル号の船長ロバート・フィッツロイは、一八二六年から三〇年までの「南米航海」においてこのパタゴニアに旅をしているが、四人の「野蛮人」をイギリスに拉致した。船長のもくろみは、「野蛮人」を「文明化」することだった。そのため、「野蛮人」の一人の家族には、「真珠のボタン」を代金として渡した。そので、その男は「ジェミー・ボタン」と名づけられた。本作のタイトルはそこから採られている。ジェミー・ボタンは、一年後にパタゴニアに戻されるが、イギリスで培った「教養」や「産業文明」をかなぐり捨てて、パタゴニアの自然に戻ったという。
二つ目は、チリにおける「9/11」である。一九七三年九月十一日、ピノチェトによる軍事クーデターによって、アジェンデの民主政権が倒された。米国CIAが加担したその後のピノチェトの独裁政権下で、アジェンデ政権下の大臣やその支持者などが軍によって拉致され、拷問や虐待を受けたり殺されたりした。殺された者の行方は分からなかったが、約千四百の死体が海に捨てられたという。死体を鉄道レールに縛りつけて、ヘリコプターや船で海に捨てたという証言がある。最近、浜辺に死体が打上げられたり、海の底で錆びたレールが発見されたりしている。象徴的なのは、殺された人のものだと思われる真珠のボタンが腐食したレールに張り付いていたことである。ピノチェトの軍隊は、殺人を隠そうとして海に死体を投げ込んだが、この一件が示唆するように、まさに「海は語る」のだ。
『カオスの自然学』の著作もあるドイツの学者、テオドール・シュベンクの言葉が映画の中で引用されている。「人間の思考の原理は水と同じで、あらゆるものに適応できるようにできている」と。独断的な思考に囚われた植民地時代と独裁時代とを一気に結びつける水の流動性(思考の柔軟性)をこの映画は有する。
グスマン監督は、「失踪」とか「拉致」といったテーマに執拗にこだわる。数々の映画祭で絶賛された『光のノスタルジア』(2010年)でも、北部アタカマ砂漠で、ピノチェト独裁政権による「ジェノサイド」の犠牲になった家族がその親族の遺体を小さなシャベルで捜す絶望的な映像が印象的であった。
本作もまた、独自の詩学と倫理を兼ね備えた優れたドキュメンタリー映像作家監督の力作である。
*『すばる』(集英社)2015年10月号、p.400-401










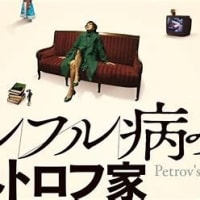
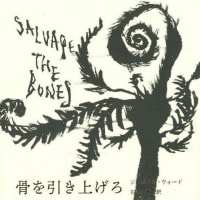

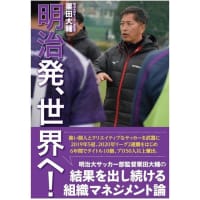






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます